
マイクロマネジメントとは「上司やチームリーダーが部下の業務を細かく管理するマネジメントスタイル」を指す。上司は「部下の教育のために」と善意でやっているつもりが、これをやるとハラスメントになったり、部下のモチベーションを削いでしまうという。
本人が気づきにくいその深刻な問題点と改善法を、橋本将功著『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン50』より抜粋・再構成してお届けする。
今の時代はマイクロマネジメントに陥りやすい
急に昇進したり、リーダーに抜擢されたりしてマネジメントを行う立場になると、人は不安に駆られます。責任を負うべき自分の部署やチームの目標を達成するために、部下やメンバーが適切にアウトプットを出せるのか、それに対して上司やチームリーダーである自分自身が何をするべきなのかについて苦悩するからです。
また、昨今では人手不足から自身もプレイングマネージャーとして手を動かして足を使わなければならないという状況に置かれ、精神的な余裕がないことも多いでしょう。こうした状況で発生しやすいのがマイクロマネジメントです。
マイクロマネジメントとは「上司やチームリーダーが部下の業務を細かく管理するマネジメントスタイル」を指します。たとえば、部下やメンバーを監視状態に置き、業務の進捗状況や進め方を一日中チェックしたり、どのように仕事を進めるか、どんな方法を用いるかまで細かく指示を出したりすることです。
マイクロマネジメントは実施する相手や組織に中長期にわたる悪影響を与えますが、実施している側(上司やリーダー)は自分の部署やチームのアウトプットの品質を担保したり、部下やメンバーの教育を行ったりしているつもりで、言わば「善意」で行っているために、その悪影響や修正方法に気づきにくいのが特徴です。
マイクロマネジメントは部下やメンバー、組織に次のような悪影響を生じさせる可能性があります。
●部下やメンバーの自主性が失われるため、人材が育たない
●部下やメンバーのモチベーションが下がり、パフォーマンスの低下や離職の原因となる
●部下に精神的なストレスを与え、ハラスメントとして認識されるリスクがある
●上司自身の業務量が増え、より本質的な役割である育成や戦略の策定などの業務に取り組めない
人は一挙手一投足に細かく指示を出されるようになると自分の頭で考えなくなり、言われたことをこなすことだけに専念するようになります。
また、自分の判断や試行錯誤によって成功や失敗を経験しなくなるため、スキルや実務経験が身につかなくなります。これが継続していくと、何年経っても上司やリーダーから指示がないと動けなくなり、事業を発展させる自律的な人材が育たなくなってしまいます。
また、もともと自主性が高い素質を持つ人材は自分自身で考えて動くことを望むため、マイクロマネジメントによって考えや行動に口出しをされるようになると、モチベーションが低下してより自発的に行動することができる環境を求めて異動願いを出したり、転職したりしてしまいます。
上司やリーダーが「あんなに面倒見てやったのに他所に行きやがって」と愚痴を口にするのを耳にすることがありますが、それはマイクロマネジメントが原因にあるのかもしれません。
さらに、マイクロマネジメントによる細かい指示出しはコンプライアンスの意識が高い現代においては「ハラスメント(相手を不快にする言動や行為)」と認識される可能性もあります。
マイクロマネジメントを行うマネージャーは良かれと思って「正しい考え方」や「正しい仕事の進め方」を伝えますが、その際に相手の考え方や仕事の進め方を否定する形になることで、それがハラスメントと受け取られるのです。
特に、プレイヤーとしての能力が評価されてマネージャーになった人の場合は自身のプレイヤーとしてのスキルが高いために指示が細かく、自分が良しとする方法以外の進め方を否定してしまう傾向にあります。
より深刻な問題は、マネージャーがマイクロマネジメントによって部下やメンバーに任せるべき作業レベルの仕事に多くの時間と注意力、労力を割いてしまうことで、本来やるべき仕事が行われずに組織の成長力が削がれることです。
本来マネージャーに求められる役割は、プレイヤー(作業)レベルでの業務ではなく、上層部が考える戦略を実現する体制や仕組みづくり、ビジネスの現場から出てくる課題や新しい展望を吸い上げて上層部が行う戦略立案のサポートを行うことなのです。
人ではなく、「プロセス」をマネジメントせよ
マイクロマネジメントの一番の問題は「人」を管理しようとすることです。自分自身が正しいと思うやり方を相手に当てはめてしまうために多くの問題が発生します。組織やプロジェクトには多くの人間が関わり、膨大な数の仕事が発生します。その仕事の方法をすべて型に嵌めようとするために、その手段として手近な人をコントロールしようとしてしまうのです。
しかし、その方法では前述の通りマネージャー自身の時間と意識、労力が奪われてしまうため、結果的にコントロールしきれなくなる可能性が高くなります。
適切なマネジメント方法は人ではなく、プロセスをマネジメントすることです。適切な期間を定めて、必要な目的や目標が達成されているかどうかを確認する時間を設け、その際に相手の考え方や抱えている課題、進捗状況を確認し、マネージャーとして必要な措置(他部署や顧客との調整や交渉など)を講じるようにすることで、プロセスをマネジメントするのです。
部下やメンバー、または作業が多い場合は定例の際に多くの時間を使わないようにするために、ツール(スプレッドシートやタスクマネジメントツール)を活用すると良いでしょう。
また、報告を受ける際は相手の考えを頭から否定しないことも重要です。仕事の進め方は唯一の正解があるようで、実はそうではないことも多々あります。
たとえば、マネージャーがプレイヤーだった時代には適切だった進め方が、時代(顧客の意識や環境)の変化によって適切ではなくなっている可能性もあります。
ビジネスは人と人が進めるものであるため、Aという顧客では正しかった対応が、Bという顧客では部下やメンバーが考える方法のほうが適切かもしれません。まず相手の考えをよく聞いて、妥当な場合はどんどん取り入れると、相手はより意欲的に働けるようになるでしょう。
文/橋本将功
『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』(ソシム)
橋本将功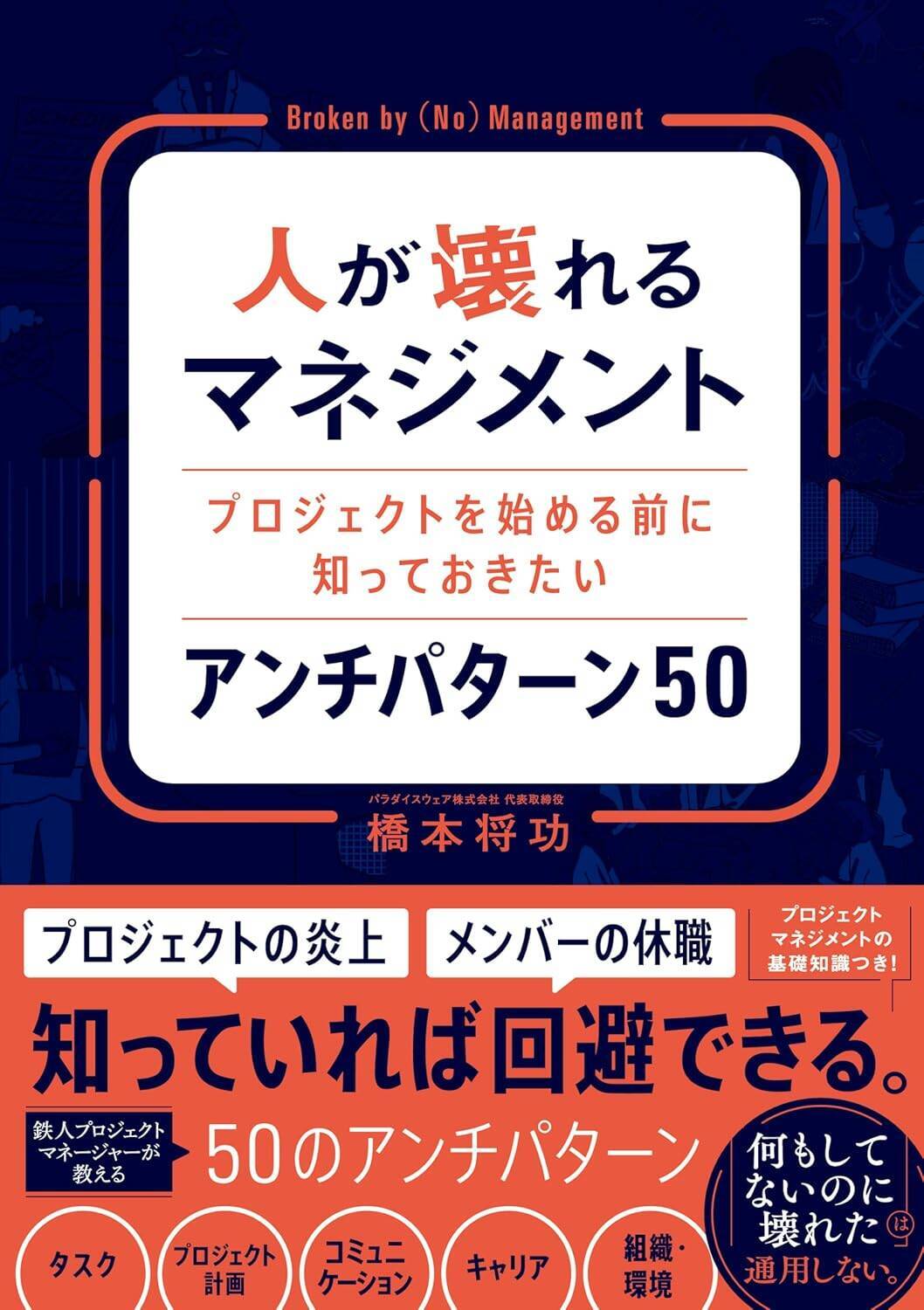
知っていれば避けられる!プロジェクト現場のマネジメント「アンチパターン」集
プロジェクトマネージャー(PM)一筋24年!500件以上のプロジェクトを経験してきた著者が、多くの組織・プロジェクトで見られる「人が壊れるマネジメント」の原因を体系化し、その回避法を具体的にご紹介します。
「目標の不明確さで壊れる」
「経営陣の無理解で壊れる」
「意思決定過程への非参加で壊れる」
「マイクロマネジメントで壊れる」
「組織文化とのミスマッチで壊れる」
「実行したタスクがキャンセルされて壊れる」
などなど、人が壊れやすい50のアンチパターンを紹介。
再現性の高い「正しいマネジメントの方法」をセットでお伝えします。

























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


