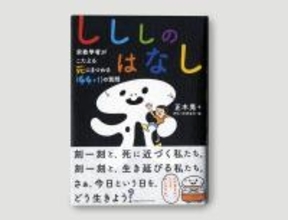いま読み返してみると、これまたずいぶん暗い1970年頃の『巨人の星』。星飛雄馬といえば、大リーグボールの華やかなイメージが強いが、実は活躍しているのは、ごくわずかな期間だったりする。
「万博」というと、今でも真っ先に当時の盛り上がりが語られる大阪万博。でも、世間が大いに浮かれた1970年頃に、実は異常に暗い歌の数々が存在していたのである(といっても、自分はまだ生まれてなかったので、よく知らないが)。
まず、第一人者は藤圭子。彼女は1969年に「新宿の女」でデビューし、1970年にこの上なく暗い「圭子の夢は夜ひらく」をシングルカット。なんたって「わたしの人生くらかった♪」である。もう二の句が次げない暗さである。ちなみに、彼女は当時の『巨人の星』(KCスペシャル『巨人の星(11)』)の作品中、星飛雄馬とテレビ番組「スター千一夜」に出演し、「いまいくらお仕事がいそがしく 睡眠時間が三時間でも あの流し時代にくらべたら 夢みたいに幸福だわ」などと暗いトークを披露している。
さらに、若いという字は苦しい字に似ているなどと歌った、タイトルから文字通り暗いアン真理子の「悲しみは駆け足でやってくる」。なにもせずに死んでゆくことを耐えられないと歌った、天地茂の「昭和ブルース」。愛もなく処女を捧げ、安い指輪をもらっただけでまた捧げ、挙句、好きでもない男に捨てられて、細いナイフを光らせて男を待つ、北原ミレイの恐ろしげな歌「ざんげの値打ちもない」もある。
それから、忘れてはいけないのは「JACKS」の存在。早川義夫、水橋春夫、谷野ひとし、木田高介の4人だ。
当時、グループサウンズやフォークで賑わっていた時代に、強烈なインパクトを持って登場した彼ら。そのメッセージはとてつもなく暗く、たとえば、「からっぽの世界」では、話すことができなくなり、死にたくないと訴えつつ、やがて「ぼく死んじゃったのかな だれが殺してくれたんだろうね」などと静かに結ぶ。
また、レコードライナーでは「あなたはあなた自身を映し出すために、鏡の底に下りていって下さい。見ている者がいつか見られる者に変ってゆく時の、恐怖を味わっていただきたいのです。(中略)暗やみの中で、まないたに横たわる鯉のよう、美しく死にたいものです」(1968.6.27レコード解説より)と書いてもいる。こわすぎます。
どんなに万博で世の中が浮かれても、反比例するように、沈み込む人たちだっている。世間が浮き足立つフレッシュな春に、ウツを訴える人が多いことにも似ているのかもしれないが。高度成長にあおられ、混沌とした時代が生んだ超ネガティブソング、注目してみてはいかがでしょうか?(田幸和歌子)
まず、第一人者は藤圭子。彼女は1969年に「新宿の女」でデビューし、1970年にこの上なく暗い「圭子の夢は夜ひらく」をシングルカット。なんたって「わたしの人生くらかった♪」である。もう二の句が次げない暗さである。ちなみに、彼女は当時の『巨人の星』(KCスペシャル『巨人の星(11)』)の作品中、星飛雄馬とテレビ番組「スター千一夜」に出演し、「いまいくらお仕事がいそがしく 睡眠時間が三時間でも あの流し時代にくらべたら 夢みたいに幸福だわ」などと暗いトークを披露している。
さらに、若いという字は苦しい字に似ているなどと歌った、タイトルから文字通り暗いアン真理子の「悲しみは駆け足でやってくる」。なにもせずに死んでゆくことを耐えられないと歌った、天地茂の「昭和ブルース」。愛もなく処女を捧げ、安い指輪をもらっただけでまた捧げ、挙句、好きでもない男に捨てられて、細いナイフを光らせて男を待つ、北原ミレイの恐ろしげな歌「ざんげの値打ちもない」もある。
それから、忘れてはいけないのは「JACKS」の存在。早川義夫、水橋春夫、谷野ひとし、木田高介の4人だ。
当時、グループサウンズやフォークで賑わっていた時代に、強烈なインパクトを持って登場した彼ら。そのメッセージはとてつもなく暗く、たとえば、「からっぽの世界」では、話すことができなくなり、死にたくないと訴えつつ、やがて「ぼく死んじゃったのかな だれが殺してくれたんだろうね」などと静かに結ぶ。
また、レコードライナーでは「あなたはあなた自身を映し出すために、鏡の底に下りていって下さい。見ている者がいつか見られる者に変ってゆく時の、恐怖を味わっていただきたいのです。(中略)暗やみの中で、まないたに横たわる鯉のよう、美しく死にたいものです」(1968.6.27レコード解説より)と書いてもいる。こわすぎます。
どんなに万博で世の中が浮かれても、反比例するように、沈み込む人たちだっている。世間が浮き足立つフレッシュな春に、ウツを訴える人が多いことにも似ているのかもしれないが。高度成長にあおられ、混沌とした時代が生んだ超ネガティブソング、注目してみてはいかがでしょうか?(田幸和歌子)
編集部おすすめ