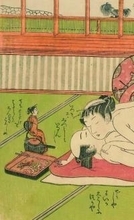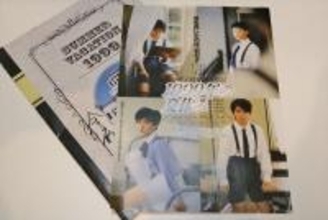そもそもほんの20年前までは鉄道はみんな切符を買って乗るというものだった。
それが1985年の国鉄時代に切符を購入できるプリペイドカードとしてオレンジカードが登場し、国鉄民営化後の1991年にはJR東日本から自動販売機で切符が購入できるほか、自動改札機に直接投入して自動改札を通ることができるイオカードが登場。現在、イオカードはスイカ(Suica)の登場ですでに使用はできなくなっているけれど、自動改札をそのまま通ることはできないが券売機で切符を買えるというちょっと不便なオレンジカードはまだ健在(使用できない券売機もあります)。
オレンジカードの場合、全国のJRで使えるというのがある意味便利と言えば便利?
JR境線(鳥取県)では全駅に設置している妖怪駅名をデザインした「JR境線水木しげるワールド」オレンジカードが発売され、水木しげるファンや鉄道ファンの間で大人気なのだとか。
私が初めて自分で切符を買って電車に乗った当時、ちょっと田舎ということもあるが、自動券売機はなく、駅の窓口で「○○まで大人○枚」という買い方。改札はもちろん有人で切符にハサミを入れてもらうスタイルだった。
と、ここまで原稿を書いていてふと思ったらあのハサミの名前を知らないことに気がついた。
あれは何と言うのか……。改札パンチとか検札パンチとかなんかそんな名前のような……と思っていたがちゃんと調べてみたら、「改札鋏(かいさつきょう又はかいさつばさみ)」ということが判明した。そして「改札鋏」によって切符の縁に刻まれた切り口は「鋏こん(きょうこん)」というのだそうだ。「鋏」を「はさみ」ではなく「きょう」と読むところが何とも特殊な道具という感じだ。これは鉄道関係者や鉄道ファンの方には常識かとは思いますが、すみません素人で。
でも「改札鋏」という名前がわかっただけでなぜか昔の改札の風景や音がより鮮明に思い出されるような気がするのは不思議。
そしてもうひとつ、駅や電車の中で見かけるあるものの名前が「改札鋏」がらみの検索でわかった。それは、新幹線や急行などに乗ったときに車掌さんが検札の時に使ったり、改札挟の代わりに駅名や日付をつけるスタンプ。あれは「チケッター」というのだそうだ。
改札鋏を使うのは手や腕にかかる負担も大きいらしく、けんしょう炎になるケースもあって大変な作業。改札鋏の代わりになるものはないかと考えていたJR東海と、連続して判を押せる技術と速乾性のあるインクの用途拡大を目指していたシヤチハタ株式会社との両社の思いがあいまって、誕生したのだとか。
身近な日常の中にある物の事、案外知らないことがたくさんあるようです。
(こや)