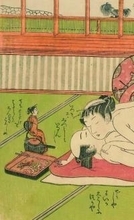実を言うと、事前に知ったそのコンセプトがそれだけで充分面白かっただけに、実物がその面白さを凌ぐものであるかどうか、少し不安な気もしていた。
これがダンボールによって作られているなんて、と、にわかに信じ難いのだが、見る角度を変え、真横から眺めてみると、様々な色や文字が散りばめられた、ありふれたダンボールの切れ端なのだった。ここだけを見ると、大変失礼ながら、夏休みに作った図画工作のようなガラクタ的な雰囲気すら感じるのに、視点を移動させていくと、ある瞬間、そのダンボール工作が思わず手を合わせてしまうような美しさを見せる。その劇的な変化が面白く、思わず長い間、会場内をウロウロしてしまった。
興奮さめやらぬまま、この魅力的な「仏像」の作者である本堀雄二氏にお話を伺った。もともと建築廃材を使ったオブジェの制作を行っていた本堀氏、仏像をテーマにした制作に取りかかる過程で、ダンボールというありふれた生活廃材に目が止まり、2005年から現在のスタイルでの制作を行っているという。
しかし、優れた仏像の持つなめらかな曲線を、ダンボールで作り上げるのは相当難しい作業なのでは……? 制作上、苦心する点について伺ってみると、「仏像というものは、正面以外の情報が少なく、全体像が把握しにくいんです。そこが難しいところではありますが、正面以外の部分がどうなっているのか、頭で想像しながら作業するのは楽しいですよ。また、 透明性を強調するために、少ないダンボールで強度を保つのが難しいポイントかもしれません」という。
素材として使用するダンボールの選び方に何か基準はあるのか、お聞きしてみると、「強度のある野菜・果物・ドリンクなどに使うダンボールを選んでいます」とのお答え。なるほど、ダンボールの自体の強度が重要なのだ。
展示されている仏像の内部には正円が透けて見え、この美しさも印象的だったのだが、これについては「平和、リサイクルの循環の輪を表しています。 後光が射すよう な、透過を強調するものでもあります」とのこと。また、仏像の胎内には、「胎内仏」と呼ばれる小さな仏像や経文などが納められていることが多いが、そのイメージを表現したもので、仏像に魂を込めるという意味合いでもある。「透過」という要素も本堀氏の作品において非常に重要なもので、一つの作品に向き合った際に、その背後にある複数の作品が透けて見える様子は、なんとも神秘的だった。
ちなみに、本堀氏に、お好きな“リアル”仏像について聞いてみると、「奈良・聖林寺の十一面観音像」というお答えだった。個人的にも大好きな仏像! 今回の展示にも、それをモチーフにした作品があり、数年前に拝観した実物に勝るとも劣らぬ迫力を感じた。
私が伺ったINAX ギャラリーでの展示は、残念ながらすでに終了してしまっているが、サイトに展示内容を撮影した画像がいくつかアップされているので、チェックしてみてほしい。
とはいえ、ギャラリーで本堀氏の作品に出会った人の声で一番多かったのは「実物を見に来てよかった」という感想だったという。これには心の底から同感! ぜひ多くの方に実物の迫力を目の当たりにして欲しいと思う。
本堀氏の次回展示は2010年10月25日~30日、大阪市北区・ギャラリー白にて開催予定だという。お近くの方はぜひ足を運んでみては!?
(スズキナオ)