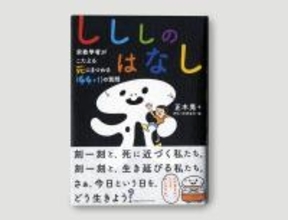だが、この団体はがっぷり四つ。聞くところによると、長崎には「長崎ねこ学会」なる研究組織が存在するそうなのだ。
ちなみに、この学会が研究しているのは、しっぽがお団子状になってたり、曲がっていたりする猫。“尾曲がり猫”である。
確かに、そんな猫を見たことはあるかもしれない。イヤ、そんなに頻繁じゃないのだけど。
そこで、2008年に学会を発足させた高島茂夫さんに、どうしてそんな猫を追っかけているのか伺ってみた。
「しっぽが曲がった“尾曲がり猫”は全国にいるんですが、長崎にいる猫のうち8割近くが尾曲がり猫なんです」
これは、きちんとした裏付けのあるデータ。元霊長類研究所所長で、現在は京都大学名誉教授・野澤謙先生の調査によると、長崎に棲息する猫のうち79%が尾曲がり猫。他地域と比べると、文句なくダントツ1位の確率である。
ここからは野澤先生の研究の成果なので、そのつもりで読んでいただきたい。
日本には、かつてはしっぽの長い猫しかいなかったらしい(鳥獣戯画絵巻に描かれている猫のしっぽは、どれもまっすぐ)。しかし、江戸時代後期の浮世絵(喜多川歌麿、安藤広重など)に、唐突に“尾曲がり猫”が出現する。
それは、どうして? これも野澤先生の研究による情報だが、“尾曲がり猫”は、東南アジアのマラッカ海峡周辺に多く棲息しているらしい。
そこで、“長崎”の理由である。江戸時代、オランダ貿易の拠点だった東インド会社は、ジャカルタに拠点を置いていたという。そこから荷物は木造船によって、長崎に運搬される。
当時の木造船は、猫を乗せないといけなかったらしい。船に乗せられる穀物の大敵は、ネズミ。その対策として、猫は必須。猫を乗せないと、航海の保険が降りなかったというほどだ。
こうした経緯により、オランダ人とともに猫が長崎に上陸。それをきっかけに、何百年という時を経て“尾曲がり猫”が全国に広まった。
以上、学会と野澤先生による独自の説(推測)である。
ちなみに、“尾曲がり猫”は茨城にも多く存在。これにも理由があり、
「当時、長崎と茨城には航路があったようです。このように、長崎と流通のある地域に“尾曲がり猫”が広まったと考えております」(高島さん)
協会の活動は、このような研究だけではない。
「猫さるく(“さるく”とは、長崎弁で“歩いて回る”の意味)」は、協会の会員達で長崎の街を散策。“尾曲がり猫”の棲息率の調査をする。
また、協会のマスコットとして“のんちゃん”なる猫のマスコットも誕生。「ゆるキャラ協会」にも登録済みの抜かりなさで、地元・長崎のイベントへの出演依頼も寄せられるという。
そんな「長崎ねこ学会」には、1つの目標がある。
「“海外に開かれた地域”としての長崎を今に伝えるものとして、アンティークとしてではなく現在もただひとつ生き続けているのが“尾曲がり猫”なんですね。これを我々は、長崎の地域資源にしたいと思っております」(高島さん)
“尾曲がり猫”には数々の呼び名(“かぎしっぽ”、“曲がりしっぽ”など)があるが、是非とも“長崎ねこ”という呼び方を普及させたい。
犬に“秋田犬”や“土佐犬”があるように、猫にも“長崎ねこ”。
学会の切なる悲願だ。事の経緯を見守っていきたい。
(寺西ジャジューカ)