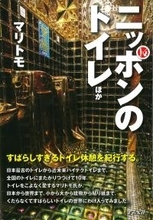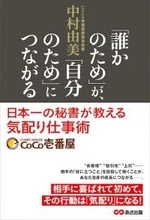でも、今、子どもに本を買うために書店に行くと、かろうじて『赤毛のアン』がある程度で、自分が親しんだような本はあまりない。
実際、小学生のわが子の友達などにも、海外文学を読む子はほとんどいないと聞くし、出版関係者も「海外文学は子どもに全然読まれない」という話をしていた。
いったいなぜなのか。ある編集者は言う。
「かつては海外への憧れが強く、海外の文化を吸収・模倣していましたが、海外が身近になって、憧れる存在ではなくなっているということはあるのでは?」
でも、近年は旅行・留学などで海外に行く若者がずいぶん減っていると聞く。自分の身近なものにしか興味がなくなっているということもあるのだろうか。
また、別の編集者はこんな分析をする。
「私たちが子どもの頃に読んでいたような児童文学は、どんどん絶版になってしまっています。あまり読まれないということもあるでしょうけど、挿画などの著作権料が高いなどの問題もあるのではないかと思います」
かつては海外の児童文学というと、原作とともに使われていた挿画がそのまま日本語翻訳版でも使われていた。挿画の独特の「異国のニオイ」みたいなものに、惹かれる部分も大きかった。
また、「訳者」によるテイストへの愛着やこだわりもあって、「○○さんの訳は良いけど、この訳はないよね」なんてエラそうなことを子どもながらに力説したものだ。
でも、今は、岩波書店が昔の挿画を残している程度で、他社からはメジャーな海外児童文学作品のみが、いまどきのマンガ・イラストなどの表紙で出版されていたりする。子どもが手をとりやすいように……という意図はあるだろうけれど、本来「児童文学」だったはずのものをわざわざ「子ども向け」に装丁替えなどして読ませようというのも、なんだか寂しい変化ではある。
また、あるマンガ編集者はこんな話をしてくれた。
「海外児童文学は日本に移行しなかったという面はあると思います。本好きの女の子はみんなかつて『若草物語』とか『赤毛のアン』とかを読んでから、後に日本文学に移行しましたよね。それは、日本文学はやはり男性を描いたものがほとんどで、女性を描くものがあまりなかったからだと思うんです。でも、そのかわりに海外児童文学を受け継いだのが、『少女マンガ』だったのだと思います」
子どもの意向・嗜好以前に、様々な事情で書店ではあまり見なくなった海外児童文学。でも、読んでみれば、きっと今の子どもの心にも響くものばかりだと思います。
(田幸和歌子)