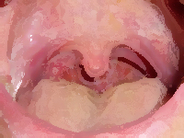向山さんは最初、アフリカと縁はまったくなかった。文化も知らない。言葉も分からない。まったくのゼロから、どのように唯一の女性ニャティティ奏者にまでなったのか。向山さんの体験談を通すと、海外で成功するコツが見えてくる。
――どういう経緯でケニア音楽に興味を持ったのですか?
プロ歌手を目指してバンド活動をしていた当初、憧れの場所といえばニューヨークでした。しかし、ニューヨークへ向かった日というのが、あの同時多発テロが起きた日でした。私を乗せた飛行機は、ニューヨークを目前に引き返すことになりました。1年半後に再渡米したのですが、今度はイラク戦争……。
――最初から語学はできましたか?
ケニアの公用語であるスワヒリ語は、行く前に1年間みっちり勉強しましたが、ケニアには42もの民族がいて、生活習慣も言語も異なります。首都ナイロビであればスワヒリ語か英語で何とかなるものの、地方に行けば通じません。ナイロビで私は、8本の弦でメロディーを奏でながら右足に付けた鉄輪と鈴で拍子を取りつつ歌える楽器、ニャティティに出会ったわけですが、師匠が住む村はルオ語しか通じない場所。それでもとにかく行ってみようと思い、スワヒリ語でルオ語を2週間ほど学んだだけで、師匠の住む村へ飛び込みました。
――ニャティティは男性だけに許された楽器ですよね。簡単に教えてくれましたか?
「外国人には教えない」「女性には教えない」とまったく相手にされませんでした。しかし毎日通い続け4日目に、師匠は「それだけ、言うのならまず村に暮らしてルオの生活を学びなさい。楽器を教えるかどうかは、あなたが正しい心の持ち主か分かってからだ」と言ってくれたのです。電気も水道もなく、毎日片道30分かけて水くみに行く生活が始まりました。
――思いが通じたのはいつですか?
2カ月後です。ある日、師匠は何も言わず、隣に座ってニャティティを弾いてくれたのです。そして「弾いてみなさい」と言いました。教えてくれるといっても手取り足取りではなく、師匠は1度しか弾かないので、それを必死に真似ます。できなければ、「あなたは、ニャティティに選ばれた人ではない」と言われて終わりなので、もう必死でした。しかも、師匠からの稽古は週2日のみ。後は毎日自主練習です。そんな村での生活が始まって8カ月後、認定試験が行われることになりました。集まったルオの村々の長老たちを前に演奏し、ニャティティの伝統奏者として認められることができました。
――まったく異なる環境の中で、物事を成し遂げられるコツはなんだと思いますか?
まずはやってみる! ニャティティは伝統弦楽器ですから、楽譜なんてありません。とにかく、師匠が言うとおりに素直にやってみて、スポンジみたいに吸収する。頭で理解できなくても、体で身に付けることが大切だと思います。一人っ子でしたので、病気にかかるかもしれない、言葉も苦労するだろうと、父も母もケニア行きには大反対でした。簡単でないことは私にも想像できましたが、それに以上に、音楽の修業をしたいという気持ちが強く、半ば家出状態で飛び出しました。成し遂げるまでは日本に帰らないつもりでした。
――現地メディアでも大きく取り上げられました。
現地の楽器を奏で、現地の言葉で歌う外国人女性ということで、ケニアの新聞やTVでも大きく取り上げられました。国連主催STOPエイズコンサートでは5万人を前にして演奏もしました。日本に帰国してからもアフリカ開発会議の式典で演奏したり、フジロックのワールドミュージック部門のベストアクトに選んでもらったり、ニューズウィーク誌(日本版)で「世界が尊敬する日本人100人」に選ばれたりもしました。しかし、ここが終わりではないです。認定試験の日、師匠は私に合格証を手渡しながら、「アニャンゴ、ここから先は遊びじゃない」と言ってくれました。
――これから海外で行く人にアドバイスはありますか?
どんな人にも可能性はあります。弟子入りを断られた時、マラリアになった時、言葉の壁があった時、うまく弾けなかった時、めげていたら今のアニャンゴはありません。どんな逆境であっても、それぞれの夢に向って、あきらめずに頑張り続ければ、道は開けてくると思います。
(加藤亨延)