ニューヨークの大学病院で活躍する加藤医師は、最先端の臓器移植手術を数多く手がけるとともに、ほかの病院では「手術不可能」と診断されたがん患者を救ってきた。
■おなかの臓器を一度全部、外に出す!
彼の名を世界に轟(とどろ)かせた手術のひとつが、世界初の「多臓器体外摘出腫瘍切除手術」だった。
つまり、「もう切ることができない」と診断される場所にできた腫瘍を取り除くために、おなかの内臓をいったん全部、体の外に出して(当然、血管も全部切り離す)、腫瘍を取り除いた後、再び臓器をおなかの中に戻す(当然、血管も再び縫い合わせる!)という、「本当にそんなことができるのか!?」という手術である。
この手術は2008年、2009年と2人の患者(1人目は当時63歳の女性、2人目は当時7歳の女の子)に行なわれ、『ニューヨーク・タイムズ』、CNN、ABCといったアメリカの主要メディア、さらに世界中の報道機関が「日本人天才ドクターが世紀の大手術に成功!」と大々的に報じた。(その後、さらに2名の患者にも同様の手術を行ない、成功している) このたび、一時帰国した加藤医師に、その「奇跡の手術」について詳しく聞いてみた。
***
―おなかの中を全部、外に出しちゃったそうですが……。
加藤 胃、膵臓(すいぞう)、脾臓(ひぞう)、肝臓、大腸、小腸ですね。
―おなかは空っぽになるんですよね?
加藤 完全に空っぽです。普通の外科手術では見たことのない景色ですね。術後、患者さん本人にも写真を見てもらったんですが、かなりびっくりしていました。
―そんなに出してしまって、体は危なくないんですか。
加藤 一定の時間であれば問題ありません。体外に臓器を摘出するためには、まず、すべての臓器を体に付着している部分から剥がさなければいけません。これは、細かく丁寧に剥離しては止血する作業になります。最終的には大動脈(全身の血液循環の大本となる一番太い動脈)、大静脈(同じく一番太い静脈)以外を完全にぶらぶらになるところまで剥離してから、このふたつの大きな血管(大動脈と大静脈)を切ります。そして6つの臓器と、腫瘍に絡みついた血管部分を、一緒に体の外に出してしまうわけです。
―太い血管も細い血管もすべて切って、ひとつひとつ止血。
加藤 臓器を出した後、重要な血管は「ゴアテックス」という、レインウエアなどにも使う素材の人工血管で置換し、血流を再開します。そうすると、心臓からおなかのほうへいっていた血流が再び足先までも流れるようになる。
―血液は、おなかの内臓をスルーしても、ちゃんと全身を循環していれば問題ないんですか?
加藤 最長6時間、少なくとも4時間は問題ないと思っています。万が一、体外で腫瘍を切除する時間が延び6時間を超えた場合も、低温冷却することで対処は可能です。ただ、そのときは人工心肺の準備が必要になる。
―2度の手術で、心停止の危険は実際にあったんですか。
加藤 その2例では、人工心肺を使うような事態は起きませんでした。ただ、命の危険がある手術であることは間違いなくて、そういったときに大切なのは、常に「バックアッププラン」を用意しておくことなんです。特に初めての取り組みのときほど、事前に代替案を準備していくことで、より冷静な決断ができるようになります。
―体外に出された臓器はどんな状態になっているんでしょう?
加藤 内部に残った血液をすべて抜いた状態で、4℃に保った特殊な保存液に漬けておきます。
―では、腫瘍の切除は保存液に漬けたままやるんですね。
加藤 そうです。体外に摘出した臓器にも、体にもダメージを残さない時間内に、腫瘍を切除して血管を再建する。そして臓器を患者さんの体に戻し、血管を吻合(ふんごう)し、血流を再開させるという発想です。
―しかし、おなかの臓器をすべて体の外に出しても元気って! 人間の体って……。
加藤 不思議でしょう(笑)。この手術の1回目の患者さんの病名は「平滑筋(へいかつきん)肉腫」といって、決して難治性ではないのですが、彼女の場合は腫瘍のできた場所が悪かった。約7cmの腫瘍が、大動脈から腹部の内臓に血液を送る大きな血管を巻き込んでいたんです。しかも背中に近い、体の深い場所に腫瘍があって、たどり着くことが極めて難しく、ほかの病院で切除不能と診断されたんです。ではどうするか。そこで僕は、腫瘍を臓器ごと外に一回出してしまえばいいと考えたわけです。
―あらためて聞いても、やはりとっぴな発想に思えますが。
加藤 話だけを聞くとそう感じるかもしれませんが、それほど発想の飛躍はないんです。というのも、僕はそれまでに多くの移植手術を手がけていました。日本に比べ移植手術の件数が圧倒的に多いアメリカでは(日本では年間約300件、アメリカでは年間約2万2000件)、臓器をすべて取り出す多内臓移植手術も珍しくない。
一方で腫瘍の外科手術においても、臓器を体外に取り出す手法はあった。僕は、臓器移植と腫瘍、双方の外科手術を経験してきたから、両方を組み合わせる発想ができたんだと思います。
■気づいたら手術は24時間を超えていた
世界を驚嘆させた奇跡の手術だが、加藤医師はあくまで「基礎の組み合わせ」だったと謙虚に語る。実際、彼は“神の手”といった呼び方(この特集でもそう呼んでいるが)に対しては、少なからず戸惑いを感じているようだ。
そうはいえども、いったん切り離した太さ1mm以下の血管を縫い合わせ、細かく丁寧に針糸をかけて止血していく(最も多いときは一度の手術で5000本!)、その技術は、やはり“神の手”と呼びたくもなる……。
***
―先生はやっぱりもともと器用だったんですよね?
加藤 器用なほうだったとは思いますし、確かに外科医には、繊細さや器用さは不可欠です。しかしそれも才能ではなく、やはり基礎の積み重ねなんです。実際、若い研修医を見ていても、将来、力を発揮できるかどうかは見えてきます。例えば(傷口の)ガーゼ交換ひとつとっても、完璧にこなそうとしている人は将来伸びる。点滴の針を刺すことにおいても同様で、針の入れ方で、患者さんの感じる痛さもだいぶ変わるんです。
入れた瞬間に、針が血管の奥側に触れると痛いんですよ。この微妙な力加減を意識して練習できるかできないか。だから大切なのは、その場その場で、自分に与えられたことを完璧にこなすことです。人より早くではなく、人よりうまく丁寧にやれと。
―先生の手術は、12時間を超えることもあるそうですが。
加藤 先ほどお話しした手術の場合、腫瘍の切除と再移植にかかったのは1時間半でしたが、トータルの手術時間は15時間でした。これは臓器を体の組織から丁寧に剥がし、1mm以下の血管に至るまで丹念に止血するといった細かい作業に時間をかけるためです。というのも、手術が長時間になっても、出血が最小限に済むと、その後の回復が早くなるんですよ。
―今のところ最長記録は?
加藤 30時間ですね。
―30時間って一日以上ですよ! 集中力ってそんなにもつものなんですか?
加藤 僕も、以前は12時間を超える手術はすべきでないと思っていたんです。だけどあるとき、非常に困難な腫瘍切除を引き受けて、実際に開けてみたら状態が予想以上に悪くて。12時間では収まりそうもなかった。それでも僕がやらない限り、この手術は誰もやってくれないわけです。終わってみたら24時間を超えていました。このとき、自分の中の12時間というリミットが一気に吹っ切れた。
―自分で外したのでなく、経験によって自分のリミッターを外されたと。休憩は取るんですよね。
加藤 15分から20分の休憩を何度か。少し横になったり、何か食べたりします。
―何を食べるんですか。
加藤 ポテトチップス、チョコレート……ジャンクなものが多いな。食事というより栄養補給です。
―眠くならないですか。
加藤 不思議とならないんですよ。手術ではないときに24時間連続で起きているのはつらいんですが、手術室では違うモードに入るんでしょうね。トイレにも行きたくならないから。
―先生はそんなハードな手術を日常的に行ないながら、週末には夜の便でベネズエラへ飛び、休日を使って現地の医師に移植医療を伝えているそうですが。
加藤 初めて訪れたのが2005年だから、8年になりますね。
―それはなんのために?
加藤 僕が持っている技術を伝えたいというのが第一です。「あれは加藤だけの特殊な技だ」と思われたら医療全体のためになりません。難易度の高い手術を行なえる医師が増えれば、それだけ助かる患者さんも増えます。ベネズエラに通っているのは、マイアミの病院の頃のベネズエラ人の患者さんがきっかけです。アメリカ人以外がアメリカで移植手術を受けると、法外な医療費になってしまうんですね。やはり、世界中の患者さんが、自国で公的制度を使い手術を受けられるようになるべきです。今後はもっと多くの国に広げていくために子供の移植医療のためのNPO財団も立ち上げました。
―それは一種の使命感なんでしょうか。
加藤 技術は修練で磨かれるものですから、できるだけ自分の経験をいろんな国に伝えていきたいとは考えています。でも、これは僕自身のためでもあるんですよ。というのも、人間は経験を積めば積むほど、どうしても「枠」から外れにくくなる。技術は経験の積み重ねによって磨かれますが、それとともに、新たな発想を得るには「過去の経験」を疑うことも必要なんです。スケジュールをやりくりしてベネズエラに行く。あるいは、手術不能と診断された患者さんの相談に乗る。前例のない環境では、思わぬことも起き得ます。それはリスクでもあるけど、「過去の経験という枠」からはみ出せる機会でもあります。
―どんな分野もそうですが、特に医療は最先端になるほど専門性が高くなります。でも加藤先生は、「移植」と「がん」のふたつの分野をまたいで仕事をしてきた稀有(けう)な存在だったからこそ、前例のない手術も成功できたわけですね。
加藤 僕の場合、どんなオファーでも簡単には「NO」と言わなかったことで得られたものがいくつもあるんです。人生の幅も広がりました。先ほどお話しした手術も、きっかけは先輩の医師からの相談でした。プレイボーイを読んでいる若い方にも、ぜひ試してもらいたいのは、ダメだなと思っても、何か方法はないか、少しは考えてみる癖をつける。既存の考え方にこだわらず、時には枠からはみ出して考えるということです。そのためには、簡単に「NO」と言わない。そうするとその先に、自分のスタイルが見えてくるかもしれないと思うのです。
(取材・文/佐口賢作 撮影/本田雄士)
●加藤友朗(かとう・ともあき)
医師、コロンビア大学医学部外科学教授、コロンビア大学付属ニューヨーク・プリスビテリアン病院肝小腸移植外科部長。1963年生まれ、東京都出身。東京大学薬学部卒業、大阪大学医学部卒業。95年に渡米し、マイアミ大学移植外科に勤務。米国で脳死ドナーからの肝臓および小腸の移植手術を多数手がける。著書に『移植病棟24時』『移植病棟24時 赤ちゃんを救え!』(ともに集英社文庫)。コミック『GUY~移植病棟24時~』(全4巻・集英社)の原作も手がけた
■最新刊『「NO」から始めない生き方』(集英社)では、本記事でも触れた手術を含む“奇跡の手術”のエピソードを紹介しつつ、加藤医師の発想スタイルを述べている



















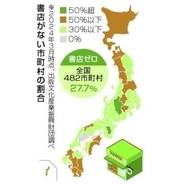







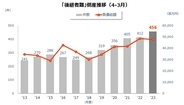


![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)

![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークアイボリー/ホワイト RYST5040H(AIV/WH2) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41bUm2zOxIL._SL500_.jpg)






