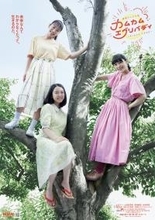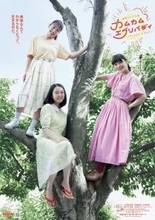先週放送の第5回はこんな話
けっきょく原稿は行きづまり、毎度おなじみ“近松脳内劇場”「赤穂義士」ではとうとう近松自ら義士に扮して、ミュージカルよろしく「赤穂浪士の場合は~」と歌い出す。元歌は新谷のり子の「フランシーヌの場合」(1969年)だ。歌声は美声ながら、物語がすでに破綻していることはあきらか。その書きかけの原稿を母・喜里(富司純子)に見られ、「もはやまともな筋を書く気はありませんね」とあきれられる始末。
しかし竹本座の座主・竹本義太夫(北村有起哉)は、劇場が経営危機に陥っているだけに、近松の新作をいまかいまかと待っているはず。さっきも家まで義太夫が催促に来ていたと喜里から知らされ、近松はあわてていつもの遊郭・天満屋に避難する……のだが、さすがにそのへんは義太夫も心得たもの。店のなかでも近松は逃げ回ることに。その途中、ひょんなことから遊女のお初(早見あかり)が身の上を告白する場面に遭遇してしまう。
平野屋の若旦那・徳兵衛(小池徹平)と恋仲だったはずのお初だが、じつは徳兵衛の父・忠右衛門(岸部一徳)こそ彼女の父親を死に追いやった張本人であった。
お初の父・結城格之進(国広富之)は蔵役人で、商人の忠右衛門とは同じく人形浄瑠璃好きということもあって公私にわたり親しくしていた。あるとき彼は忠右衛門が不正な取引を行なっていることを知り、友人として忠言する。
すっかりお初の話に惹きこまれた近松、こうしてはいられないと紙と筆を探し出し相関図を書き留める。物書きの性であろう。だが、そこからいかに物語を展開させるかはまた別問題。翌朝、近松が図とにらめっこしながら、ああでもないこうでもないと考えあぐねていると、万吉が横槍を入れてきた。この男、一瞬しか見なかったはずの相関図の内容をたちまちのうちに理解して、近松をたじろがせる。
そして何を思い立ったか万吉、家を飛び出す。彼に誘われるがまま近松も同行すると、行き先は何と平野屋。ここで万吉は忠右衛門にその日の申の刻(午後4時ごろ)に天満屋に来るよう伝え、承諾させてしまう。次いで天満屋に赴けば、今度はお初に匕首を渡して仇討をけしかける。
これで舞台は整った。さて、お初はどうする? そして忠右衛門はどう出るのか? 物語は急転直下、シリーズ最大の山場を予感させながら今夜放送の第6回に続く! Don't miss it!!
今回のうんちく――浄瑠璃の人形、昔といまとどう違う?
第5回は、前半では先述のとおり「フランシーヌの場合」を替え歌してみたり、近松が『出世景清』をハリウッド映画の予告編風に紹介してみたりと、毎度ながら遊びをふんだんに盛りこみつつ、その後お初の告白からグッとシリアスな展開となった。
ちなみに「フランシーヌの場合」で歌われるフランシーヌは実在のフランス人女性で、1969年、当時激化していたベトナム戦争などへの抗議の意を込めてパリで焼身自殺した。歌詞に出てくる「三月三十日の日曜日」とはフランシーヌの命日であり、「ちかえもん」の劇中ではこれを「元禄十六年の二月四日」と赤穂浪士切腹の日付に換えていた。
それはともかく、第5回では、幼き日のお初が父に連れられ竹本座で「出世景清」を観る場面があった。そこで、小野姫の人形を操る人形遣いが一人だったことに気づかれただろうか。現在の人形浄瑠璃(代表的な流派の名から文楽とも呼ばれる)では、1体の人形を3人で操るのが一般的だが、じつはこれは近松の生前にはなかった手法だ。よって、劇中に出てきた一人遣いの人形は、時代設定に忠実に則したものといえる。
もっとも、一人遣いの人形の操作法についてくわしい史料は残っていないらしい。ドラマでは国立文楽劇場で資料用に復元した人形に、あくまで想像のうえ「差し金」をつけて動かしているそうだが、「当時はもっと複雑な構造だったかもしれない」と人形遣いの桐竹勘十郎(本作でも人形遣いとその監修を担当)は語っている(『NHK ウィークリー ステラ』2016年2月12日号)。
「ちかえもん」ではまた、竹澤團七(本作では義太夫指導も担当)の三味線に合わせて、竹本義太夫演じる北村有起哉が、吹替えではなく自ら義太夫節を語っている。
その義太夫、第5回では、同志である近松にこれ以上無理して原稿を書かせるわけにはいかないと、竹本座を閉める心づもりを万吉に打ち明けていた。この流れからの次回のサブタイトルはずばり、「義太夫些少活躍(ぎだゆうわりとかつやく)」。義太夫はんがどないな活躍を見せてくれるんか、そこも注目だっせ!
(近藤正高)