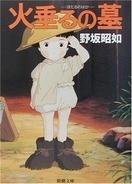いちおう説明しておくと、オオサンショウウオは世界最大の両生類で、3000万年近く姿を変えていないことから「生きた化石」ともいわれる。日本ではニホンオオサンショウウオという固有種が西日本の各地に分布しているものの、その希少性から国の特別天然記念物に指定されている(日本以外では中国と北アメリカにしか生息しない)。これまで日本での生息地の東限は岐阜県郡上市といわれてきたが、近年の瀬戸市での調査にともない、『広辞苑』での記述も、2008年発行の最新版(第6版)では従来の「岐阜県以西」から「愛知県瀬戸市以西」にあらためられた。ただし最近になって、瀬戸市の北東に位置する岐阜県東白川村(この村はツチノコ伝説でも有名)にオオサンショウウオが新たに生息・繁殖していることが確認されたというので、この記述もいずれ変わるかもしれない。
「日本オオサンショウウオの会」は、オオサンショウウオとの接し方について、動物園・水族館関係者、研究者や保護活動家や団体、河川行政や河川工事の関係者などが気軽に情報交換できる場として2004年に設けられた。一言でいえば、オオサンショウウオを愛し、その保護に取り組む人たちのネットワークである。年に1回、大会が生息地で開催され、昨年は岡山県真庭市にて開かれた。
さて、その「日本オオサンショウウオの会」は、瀬戸市の公式ページによると、参加費が必要ではあるが一般の参加もOKだという。せっかくの地元開催だし、ここはちょっと覗いてみようと申し込んでみた。1日目、10月1日の会場は名鉄・尾張瀬戸駅のほど近くにある文化施設「瀬戸蔵」のつばきホール。
基調講演ののちプログラムは各地からの報告に移り、次々と「日本オオサンショウウオの会」の会員が壇上にあがって発表を行なった。そのテーマはさまざまで、広島市安佐動物園が、河川改修工事におけるオオサンショウウオへの配慮を紹介したかと思えば、京都大学の研究者からは、賀茂川における外来種(チュウゴクオオサンショウウオ)と在来種であるニホンオオサンショウウオの交雑が起こっているとの報告がなされた。また、山口県岩国市を流れる錦川(支流・宇佐川)のオオサンショウウオについて、高川学園中学・高校の科学部の部員たちが研究発表を行ない、宇佐川堰堤の直下に住むオオサンショウウオをめぐりフィラリア寄生やエサ不足などさまざまな問題が起きていることが報告された。同学園は、オオサンショウウオの調査により今年の「日本ストックホルム青少年水大賞」の優秀賞も受賞しているという。すごい。
これらのテーマとくらべるとちょっと柔らかめの内容の発表もあり、たとえば最近結婚した研究者夫妻が、新婚旅行でオランダ・ライデン市の国立自然史博物館を訪れ、江戸時代にドイツ人医師シーボルトが持ち帰ったオオサンショウウオの標本を見せてもらったという話には、ロマンを感じた。また、愛知県在住の下村俊孝さんは、「オオサンショウウオダイビング」と題して、自ら川に潜って撮ったオオサンショウウオの映像(これが玄人はだし!)を上映。それとともにオオサンショウウオのどこががかわいいのかを熱く語った。オオサンショウウオは、平べったい体といい、小さな目といい、指先が球形になってるところといい(下村さんはこれを「いくらボール」と命名していた)、萌え要素の多い動物でもあったのだ!
終盤では、三重県伊賀市の木津川上流域で計画されている川上ダムについて、水資源機構・川上ダム建設所の担当者が、同地域に住むオオサンショウウオの保全への取り組みを説明したのに続き、オオサンショウウオの保護のためダム建設そのものの中止を求める団体(伊賀の特別天然記念物オオサンショウウオを守る会)の代表が、あらためて反対意見を述べた。この並べ方だけとっても、「日本オオサンショウウオの会」の間口の広さがうかがえよう。自然保護、歴史、民俗、観光、さらには萌えと、オオサンショウウオへのアプローチの多様さには感心させられた。
すべての報告が終え、このあと会場を瀬戸蔵の多目的ホールに移して交流会が行なわれた。急遽駆けつけた東山動物園の橋川央園長の音頭により乾杯となったのだが、ぼくはといえば会場に知り合いがいるわけでもなく、一瞬途方に暮れる。そこへ話しかけてくれたのが、島根県奥出雲町の「加食オオサンショウウオ保存会」の会長だった。聞けば、昔は川で魚釣りをしていると、針に引っかかってくるぐらいたくさんオオサンショウウオがいたのだが、改修工事で川がコンクリートで固められたため激減してしまったという。同様の現象はほかの生息地でも起こったのだが、現在ではオオサンショウウオの住む河川で改修工事を行なう場合、岸底に人工巣穴を設置したり堰にオオサンショウウオ用の通り道をつけるなどの対策がとられるようになっている。
交流会ではこのほか、たまたま隣りにいらっしゃった橋川園長に、オオサンショウウオの年齢を測定する方法について質問してみたり(その答えは「方法はない」だった。
蛇ヶ洞川はそれほど幅も深さもない、おだやかな流れの川だった。観察会が始まって15分ぐらい経ったころだろうか、花川橋という橋のたもと近くでオオサンショウウオが見つかった。そう伝えられるや参加者たちがいっせいに集まり、写真の撮影をはじめる。しかしこれだけ人が来ても、オオサンショウウオは急いで逃げ出したりせず、じつにおとなしい。やがて東山動物園のスタッフが捕獲して大きさを測定を始める。
ともあれ、野生のオオサンショウウオを初めて目の当たりにしてすっかり大満足。オオサンショウウオを愛する人がこんなにもいること、その世界の奥深さもわかって新鮮だった。興奮しながらぼくはこの日いったん帰宅する。ほかの地方から来た人たちなどは、この日は旅館などに宿泊。あとで聞いたところ、朝5時近くまで話しこんでいた人もいたとか……。
翌日、10月2日。朝9時前に尾張瀬戸駅前からバスで昨晩同様、下半田川町に向かう。
オオサンショウウオは夜行性の強い動物だというので、昼間の観察会ではついに現れなかったが、それでも昨晩ははっきり見えなかった人工巣穴(岸辺にマンホール状のふたがあり、それをとると巣穴の内部が見られる)やオオサンショウウオの通り道が確認できた。何より、まわりを山々に囲まれ、田畑が広がる地区の風景には心がなごんだ。昼食には、細かく刻んだマコモダケを混ぜて炊いた「マコモめし」とお吸い物がふるまわれる。レンコンのようなタケノコのような不思議な感触ながら、おいしくいただいた。
午後は東山動物園の自然動物館を見学。両生類や爬虫類の展示室のバックヤードも見せてもらう。バックヤードには、2007年に瀬戸市で死体が見つかったという1メートルを超すオオサンショウウオの骨格標本も保管されていた。動物園で飼育されているオオサンショウウオもやはりおとなしく、ほとんど動かなかった。パッと見ただけでは動物とは気がつかないほど。
来年の「日本オオサンショウウオの会」は山口県岩国市で開催されるという。動物園での別れ間際、前出のつまきさんや下村さんから来年もぜひ! と誘われたのだが……とりあえずそれまでに旅行資金をためておきますっ。(近藤正高)