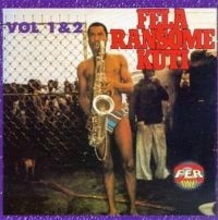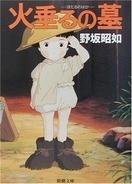西川のりおの野太い歌声をBGMに、トランポリンのような草原の上でピンクのクマやらリスやら、オカピやら黄色いムササビやら着ぐるみの動物たちがピョンピョン踊っている。そのCMを初めて見たとき、何じゃこりゃ!? と強い衝撃を受けたものだ。
このCMをつくったのは、野田凪というアートディレクターにして映像作家だ。野田は2000年代に数々の話題作を発表したが、2008年の9月、34歳の若さで亡くなっている。その突然の訃報から早3年、彼女の手がけた作品を集めた「野田凪展」が現在、東京・銀座のリクルートGINZA8ビル内にある「クリエイションギャラリー G8」で開催中だ(会期は11月18日まで)。つい先日足を運んだところ、平日の午前中にもかかわらずけっこう多くの人が来ていた。
展示されている作品は多様で、ポスターをはじめ映像、CDジャケットのほか、服やぬいぐるみなど立体のものまで含まれる。そのなかで本人が自信作と語り、世間的にもおそらくもっとも有名だと思われるのがYUKIのCD『Commune』(2003年)のポスターだ。これは画面の右から左へ少しずつ違うポーズをとったYUKIを並べることにより、全体を通して動いたり変化したりしているように見せかけたものなのだが、よく見るとYUKI本人は右端と左端にしか登場しておらず、そのあいだにはYUKIと同じ髪型のウィッグをつけたそっくりさんが並びそれぞれポーズをとっている(やはり野田が手がけた同アルバム収録の「センチメンタルジャーニー」のミュージックビデオも同じ手法で撮られている)。おそらくCGを使えば、もっと楽に撮れそうなものだが、そうせずにあえて手間暇をかけることで見る人に驚きや楽しみを与えるというのが、いかにも野田らしい。
「いかにも野田らしい」と書いたのは、こうした手法はほかの作品でも採られているからだ。たとえばアメリカのバンド、シザー・シスターズの「SHE'S MY MAN」のミュージックビデオ(2006年。
思えば彼女が活躍したのは、コンピューターによる映像の加工・編集が当たり前となっていた時期でもある。受け手もまた、ちょっと変わった映像を見ても「どうせCGだろう」とたかをくくり、めったやたらに驚かなくなった。そんな風潮に対して野田はずっと抗っていたのかもしれない。くだんの四姉妹の広告の制作直後、野田は次のように語っている。《私が仕事をしていて楽しいのは、現場で作り込んでいざ撮影というときに、それをみんなが見て「ワッ!」って驚く瞬間。普通の生活の中では絶対体験出来ないような、結構ショックなビジュアルをスタッフ全員が目に出来る瞬間が一番面白い。そういうものをどんどん作りたいんです》(クリエイションギャラリーG8 Webインタビュー、2002年12月)。
もうひとつ、この展覧会でぼくが印象に残ったのは、全日空の広告ポスター(2002年)である。中国便の大増発により、以前にもまして気軽に移動できるようになったことをアピールしたこの広告には、「目のクマがすっかりとれたパンダ」とのコピーが入り、文字どおり目のまわりの黒縁がとれたパンダが登場している(これはさすがにCG加工によるものだが)。クリエイティブディレクターの佐々木宏は展覧会に寄せたコメントで、この広告の案が通るまでには紆余曲折があったことを明かしている。じつは、このアイデアは、最初のプレゼンでは「パンダは中国の神聖な動物だから」との意見が出てボツになったというのだ。これを受けて野田は抑制するどころかさらに過激に、中国の国旗の星の部分をピカチュウにした案を提出する。さすがにこれには担当者も「中国の国旗をいじるのは勘弁してください。絶対無理です」と泣きつき、結果、これだったらパンダのほうがいいか……ということになり最初の案が採用されたのだとか。佐々木は《普通だったらプレゼンでボツになったら、次はおとなしいものを出してくるのだが、野田さんは逆》と振り返っているのだが、むしろ野田は最初の案を通したいがあまり、絶対に通らない案をあえて出すという“奇策”に打って出たともとれる。
この展覧会の会場はさほど広くはないのだが、上映されている映像をひととおり観たりしているうちについつい長居をしてしまった。そこでどうしても考えてしまったのは、野田がいま生きていたらいったいどんな作品を見せてくれたのだろうか、ということだ。そういえば、前出のYUKIのポスターについて野田は《たぶん十年後も好きだと思う。自分の中で、あれを超えるものはしばらくできないかもというくらい気に入ってる》(「広告批評」2003年4月号)と語っていた。
なお会場には、撮影現場を撮ったスチール写真やインタビュー記事のスクラップを収めたファイルブックのほか、野田の両親が幼少期の彼女に見せた映画や舞台のタイトルをリストアップしたノートが置かれ、自由に閲覧できる。なかには「こんな作品まで子供に見せていたのか!」というものもあって面白い。会場に行ったらぜひチェックしてみてください。(近藤正高)