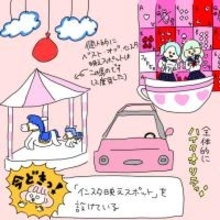つい先日、新聞の集金の際に販売店さんが、来年度の高島暦の本を置いていってくれた。
私がいただいた暦は、高島暦出版本部から出されている神正館蔵版で、鑑定は神正館の橋本一鑑氏によるもの。高島暦は、明治の時代に中国の「易経」をもとに独自に高島易断という易法を開発した高島嘉右衛門氏の暦の流れを汲んでいて、人間の運勢や吉凶の判断に実際の天体上の星とは関係なく五行説の基準である木、火、土、金、水と7つの色を組みあせた九星を用いたものだ。運勢の他にも大安、仏滅など六輝(六曜)が載っていて何かと便利に使える。
私はこの高島暦をいただくと、真っ先に見てしまうのが九星のところに書かれていることわざとイラスト。こういっては失礼だがちょっと今風でないイラストに書かれたことわざは秀逸。はっきりいってわかりやすい。
時には、ちょっとレトロで脱力感を覚えるようなものもあるが、それでもやっぱり分かりやすい。
ちなみに、平成17年度版では五黄土星が「運根鈍」。これは「うんこんどん」と読む。大辞林によると「運根鈍とは成功するためには、幸運と根気と粘り強さの三つが必要であるというたとえとある。広辞苑では、全く同じ意味で「運鈍根」と書かれていた。
気になる来年度の平成18年度版は、二黒土星が「短気は損気、堪忍五両」の文字とともに迫力のイラスト。四録木星は「起きて働く果報者」。
それにしても、このイラストとことわざは一体誰が考えているのかと高島暦出版本部に問い合わせると、詳細は神正館の橋本氏へということで、直接橋本一鑑氏にズバリうかがった。
「私が暦を書くようになって40年ほどになりますが、イラストとことわざを入れるようになったのは途中からで、10年いやもうちょっと前かな、20年くらいかな。ことわざが入れば分かりやすいかなと思って入れたんですよ。評判がいいので今も継続しているんです」
とのこと。
色々調べているところ「高島易」「高島易断」と「高島」の名がつく団体が数多くあることに気がついたのでそのことについて橋本さんに伺うと、
「高島易断は一度途絶えているんです。高島易断を作った嘉右衛門さんは82才で亡くなっていますが、4人の子どもがいたにも関わらず易は自分一代のものと考えていたようで後継ぎは作らなかったんですよ」
とのこと。どうやら今ある「高島」と名のつく易は高島易断を作った嘉右衛門さんとは直接は関係ない団体のようだ。
今年で76才になるという橋本氏、神正館蔵版の暦は再来年の19年度をもって引退し、その後は娘さんに引き継ぐのだそうだ。でも、たとえ娘さんにバトンタッチしてもこのイラスト&ことわざのレトロテイストは是非残していただきたいなぁと思います。
(こや)