死のかたちから見えてくる人間と社会の実相。過去百年の日本と世界を、さまざまな命の終わり方を通して浮き彫りにする。
■1929(昭和4)年フェミニズムの花園の礎は6歳での留学にあり津田梅子(享年64)
令和6(2024)年から5千円札の顔が、津田梅子に代わる。津田塾大学の前身となる女子英学塾を設立して、女子教育に貢献した女性だ。その人生は6歳で決まったといっていい。
明治4(1871)年、岩倉使節団に随行して米国に留学。
「私が良い娘になったら、アメリカの人はこぞって、この娘は良い父と母をもっているというでしょう。
しかし、多感な成長期を異国ですごしたことは、彼女を特殊なマイノリティにした。帰国後は日本語がうまく話せず、アメリカナイズされた性格も日本的な価値観と相容れないものになっていた。特に、結婚をせきたてられることに辟易し、その後、再び渡米。生物学(カエルの研究)に打ち込むなど、試行錯誤を経て、日本でアメリカ的な女子教育を行なうという自分にしかできない道を見いだすわけだ。
こうして設立された彼女の学校には、その理想が色濃く反映され、それは津田塾大となってからも受け継がれた。
もっとも、津田自身はその成果を見届けることはできなかった。52歳の頃から糖尿病を患い、やがて塾長を辞任。体調は回復しないまま、64歳のとき、脳溢血で他界した。英文で書き続けられた日記には、亡くなる日の朝にも「Storm last night.(昨夜は嵐だった)」という一文が綴られており、勤勉な人柄がうかがえる。
ただ、5千円札の顔が樋口一葉から彼女へと受け継がれ、女性枠のようになっているのも、一種のフェミニズム効果だろう。6歳の留学から、女子教育に捧げた人生はそんなかたちで報われたともいえる。
■1930(昭和5)年天才と狂気、愛と孤独を行き来した文学少年少女島田清次郎(享年31) 金子みすゞ(享年26)
『天才と狂人の間』(杉本久英)という伝記小説がある。主人公は「島清」こと島田清次郎。19歳で書き始めた自伝的長編『地上』がベストセラーとなり、ハタチにして時代の寵児ともてはやされた石川県出身の作家だ。が、自分のファンだった海軍少将の娘を誘拐して告訴される(のち、取り下げ)というスキャンダルや奇行(大言壮語やDVなど)で人気と信頼を失い、25歳のとき、統合失調症と診断されてしまう。
これほど短期間に、絶頂とどん底を味わった作家は日本文学史においても類がない。その成功した理由について『島田清次郎 誰にも愛されなかった男』を書いた精神科医・風野春樹は「若者たちの代弁者」「中二病」といった言葉を使って分析している。おそらく、のちの尾崎豊(こちらはミュージシャンだが)現象の先駆けのようなことが起きたのだろう。
では、失墜の原因となった統合失調症についてはどうか。風野は「確かに一時は『狂人』と呼ばれても仕方ない精神状態にあった」としつつも「精神全体が妄想に支配されてしまうようなことはなかった」と見て(診て)いる。
マスコミにも、同情的な見方がなくもなかった。文藝春秋の編集局長は、
「一体、清次郎はほんとに狂気していたのかしら。(略)どうせ清次郎のことだから、なんのかのと、うるさいことだらけだから、いっそのこと四捨五入して狂人組へ編入さして了え、というようなことで、あわれびんぜんにも病院へ送られることになったのじゃないのかしら」
と書き、元凶はむしろ「誇大なこけおどしの広告でもって」「彼を喰い物にした本屋だ」と、新潮社を批判した(今も続く文春VS新潮の対立構図がなかなか興味深い)。そういえば、現代の書評家・豊崎由美も、
「新潮社なんか、この作品で大儲けしたくせに最後は門前払いだったらしいよ」
と、対談で言っている。実際、凋落後の島清は『地上』の利益で建ったとされる新潮社の新社屋に金策で訪れたが、冷たくあしらわれたという。
さて、彼の死の前月には、金子みすゞが帰らぬ人となった。こちらは島清とは対照的に、没後半世紀もたってから脚光を浴びた童謡詩人だ。山口県の生家が書店で、幼時から読書に親しみ、ハタチのときに雑誌投稿を始めて、第一人者の西條八十に激賞された。「イマジネーションの飛躍」「ふっくりとした温かい情味」とはその評の一部であり『大漁』『私と小鳥と鈴と』などの作品が知られている。
しかし、3年後に周囲の勧めで結婚した相手とは折り合いが悪く、創作と文通を禁じられてしまう。また、この男は遊郭通いが趣味で、性病を伝染されたりもした。結局、彼女がひとり娘を引き取ることを条件に離婚したものの、夫が心変わりをして連れ戻されそうになり、死の抗議を行なうのである。
「どうしてもというのなら、それはしかたないけれど、あなたがふうちゃんに与えられるのはお金であって、心の糧ではありません」
と、遺書に記し、娘と入浴して一緒に童謡を歌い、母や叔父を含めた家族4人で桜餅を食べたあと、カルモチンを飲んで自殺。26年の短い命と引き換えに、娘はみすゞの母が育てることになった。
その死をもたらしたのは、理解の欠如した結婚だが、そもそも、大漁の日に鰯の弔いを心配するような魂がこの世に向いているだろうか。彼女の「みんなちがって、みんないい」が儚い理想でしかないことを示す最期でもあった。
(宝泉薫 作家・芸能評論家)














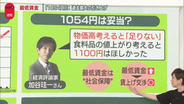



















![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークブラウン/ブラックRYST5040H(ABR/BK4) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/413mi56isML._SL500_.jpg)





