何が起きるか予測がつかない。これまでのやり方が通用しない。
エル・スール』アデライダ・ガルシア・モラレス著/野谷文昭・熊倉靖子 訳" />
「視点が変わる読書」第11回 人間の聖と俗
■父親に実は妻以外の女性がいた
2月9日に封切りされた、スペインの映画作家ビクトル・エリセの新作『瞳を閉じて』を見た。エリセは寡作で知られる。1968年に監督デビューしてから、長編作品はこれでようやく4作目。
日比谷のTOHOシネマズシャンテの11時からの回に行くと、200ほどある座席の7割がうまっていた。六十代以上とおぼしき人がほとんどで、恐らくエリセのファンなのだろう、館内の空気から、31年ぶりの新作への期待と興奮が伝わってきた。
私が初めて見たエリセ作品は彼の長編第一作の『ミツバチのささやき』で、大学2年生の時、映画好きの友人に誘われて映画館で見たのだが、娯楽大作ばかり見ていたその頃の私の頭の中は「?」で埋め尽くされた。
出版社に入って映画への意識が高まり、レンタルビデオで『ミツバチのささやき』を見直すと、主演の少女アナの可愛さ、映像の美しさ、描かれている世界の奥深さに打ちのめされ、すぐに長編第二作『エル・スール』を借りて見た。
暗い部屋の右上の窓から光が差し込むシーンでこの映画は始まる。
少女には父が二度と家に戻ってこないことが分かっているのだ――。
スペイン北部の村に住む一家の日常を描いた映画だが、とにかく映像が美しい。光と闇のコントラストが強く、一つ一つのシーンにまるで宗教画のような神々しさが感じられる。絵画的な構図を使うのはスペイン映画の特徴だというが、ボール遊びをしている子供や編み物をしている女性をこれほど神秘的に撮れるのはエリセだけではないだろうか。
もっとも『エル・スール』は物語自体にやや神がかりなところがある。主人公の少女、エストレリャの父親は医者で共和派であったが、南部の地主でフランコ派の彼の父と対立して家を出、北部に移り住んだ。彼には霊力があり、振り子を使って、色々なことを占う。
この映画に原作があることは知っていたが、これまで読もうとは思わなかった。映画の完璧なまでの美しさを壊されたくなかったのだ。それが今回、新作が封切られることを知り、エリセへの関心が高まって、一体どんな小説からあのような映画が生まれたのか、知りたくなった。
映画と同名の小説『エル・スール』の著者は、アデライダ・ガルシア=モラレス。
設定は映画とほぼ同じである。スペイン北部の村の人里離れた家に父、母、娘の三人家族が女中とともに住んでいる。父親は学校でフランス語を教えて生計を立て、母親は家事をしながら娘のアドリアナの家庭教師をしている。父親には霊力があり、鎖のついた振り子で様々なことを占う。
大きく違うのは、主人公の少女の性格だ。映画のエストレリャは従順で控えめだが、小説の主人公アドリアナは反抗的で攻撃的だ。「母さんは嫌い!」と言い放ったり、女中を魔女呼ばわりしたり、近所の子供と二人でジャンヌ・ダルクごっこをしていて、その子を木の幹に縛り付け、枯草や枯れ枝で足元を囲んで火をつけたり……。
しかしそんな二人も、神秘的な力を持つ父親に憧れるのと同時に畏怖の念を抱いているところは共通している。
ところがその父親に実は妻以外の女性がいた。
■人間は聖と俗を合わせ持った存在である
女性の名前は映画ではイレーネ・リオス、小説ではグロリア・バリュと異なっているが、かつて恋人で女優ということは同じだ。
映画の父親も小説の父親も、時間的にも距離的にも離れているにもかかわらず、かつての恋人への思いを断ち切れず、家族を捨てて恋人とやり直そうとするが恋人に拒絶され、猟銃自殺してしまう。
映画は、父親が夜中に家を出て自殺したことを家族が知るシーンから始まり、エストレリャが父の故郷であるスペイン南部の町に向かうところで終わる
「エル・スール」はスペイン語では「南」を意味する。
「私は興奮をおさえきれませんでした。初めて南を知るのです」
ラストシーンのエストレリャの台詞だ。映画において、「南」は憧れと謎の地のままだ。ところが小説では父の死後、アドリアナは実際に父の故郷であるセビーリャを訪れ、父親に届いたグロリア・バリュの手紙を頼りに彼女の家(セビーリャにある)まで行くのだ!
そこでアドリアナはグロリアとその息子、ミゲルと会う。グロリアはアドリアナがかつての恋人の娘だと気づき動揺するが、アドリアナは冷静に対応する。ミゲルはアドリアナよりも一つ年下だが、背が高く大人びた少年で、二人はお互いに引き付けられる。ミゲル自身は知らされていないようだが、アドリアナはミゲルの父親が自分の父親であることを確信する。
いかにも俗な展開ではあるが、これはこれで興味深い。
今回原稿を書くにあたり、『エル・スール』に関する資料を読んでいたら、実はエリセはエストレリャが「南」を訪れるところまで撮る予定だったが、興行の都合で撮影が打ち切られたことが分かった。しかもエリセは後半の「南」の部分を喜劇にして撮るつもりだったという。つまり、映画『エル・スール』は「北」と「南」の「北」だけ、「聖」と「俗」の「聖」だけを描いた未完の作品だったのだ。
映画の世界を壊されたくないと小説を読まなかったわけだが、読んで、正直ほっとしたような気持ちになった。
人間は聖と俗を合わせ持った存在である。ある時は聖人のように見える人間が、ある時はとてつもなく俗な人物になる。そこが人間の面白いところだ。
ところが、映画『エル・スール』は人間をあまりにも「聖」として描き過ぎている。だからこそ、完璧なまでに美しかったのだ。
■人間とはかくも身勝手なもの。しかし同時に…
『瞳を閉じて』は初老の映画監督ミゲルを主人公にしている。かつてミゲルが監督した作品の撮影中に失踪したフリオという主演俳優がいた。失踪して22年後、テレビ番組が昔の失踪事件を取り上げると、フリオがある高齢者施設で働いているという情報が寄せられる。本人であるか確かめるためミゲルがその施設に赴くと、果たしてそれはフリオだった。ところがフリオは記憶を喪失していて、ミゲルのことも覚えていない。ミゲルは昔の写真を見せたり、彼の娘を呼び寄せたりして記憶を取り戻させようとする。
フリオの娘役を演じたのはアナ・トレント。『ミチバチのささやき』の主演の少女だ。現在58歳の彼女の顔に7歳の少女の面影が重なり、魔法を見せられているような気がした。
結局娘に会っても記憶が戻らなかったフリオに、ミゲルはある決定的なものを見せる――。
何故フリオが失踪したのかは最後まで分からない。どんな理由があるにせよ、彼のせいで、映画は完成せず、多大な損害を出し、彼の友人ミゲルは映画を撮ることをやめた。さらに残された妻と娘のその後の人生に耐えがたい哀しみと苦しみを与えた。この事実は変わらない。
人間とはかくも身勝手なものなのだ。
しかし同時に、人間は聖なるものでもある。
その両面をエリセの新作は見事に描ききっていた。
文:緒形圭子














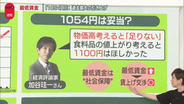



















![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークブラウン/ブラックRYST5040H(ABR/BK4) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/413mi56isML._SL500_.jpg)





