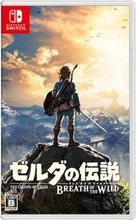ゲームマニアじゃなくても、誰だって、どこかで触れているに違いない「遊び」を生み出した男、横井軍平。
その展示会が開催中だ。
場所は「原宿VACANT」。
竹下通りを抜けて、もうちょい先。
【「横井軍平展 -ゲームの神様と呼ばれた男-」】
期間:2010年8月18日~29日
時間:平日13時~21時、土・日12時~21時
(最終日のみ18時まで)
入場料:300円(税込)
展示スタイルも、すばらしい。
実際に触って遊ぶことができるものも有り!
「ゲーム&ウオッチ」が全て電源が入った状態で展示されている!
しかも写真撮影OKなのだ。
軍平展の関連イベントとして、8月21日(土)に「私たち、僕たちの横井軍平」というトークショーが行われた。
最初は、牧野武文(『横井軍平ゲーム館 RETURNS』『ゲームの父・横井軍平伝 任天堂のDNAを創造した男』)と田中宏和(軍平さんの元で働いていたクリエイター)のトーク。
牧野「部下への優しさとプレッシャーってどうでしたか?」
田中「プレッシャーはなかった。オープンで自由」
牧野「でも、仕事してるわけですよね?」
田中「やぁ、ここは、ほんま会社かなと思うぐらい」
牧野「でも、プロデューサとして目を光らせてたのでは?」
田中「うーん光らせてなかったなー」
牧野「でも、そうじゃないと仕事にならないですよね」
田中「いや、全部あそびだった。仕事だと思ってやったことがない」
当時のゲーム開発現場を知ってると「全部あそびだった」という感覚は「そうそう!」ってすぐ共感できるのだけど、知らない人には「それでだいじょうぶなの?」って印象を与えるようで、牧野さんのネバりが楽しかった。
他にも、当時のモノヅクリの現場を伝える発言がいくつも飛び出した。
「『レッキングクルー』作ってたころとか、まだ(職種が)細分化されてない。
「開発は20人ぐらい。工作室でスイッチ作ったりツール作ったり。ゲーム&ウォッチも手作りですよ。横井さんは、プロデューサーになっても、ひたすら作っては壊してた」
「トランプさえ売れてたら大丈夫やねん、って冗談で言ってた。でも、金と切り離された開発というのがビッグバンのキーだったと思う。金の話はしなかったけど、(製品の)コストを下げることに関しては、すごく努力した」
「アイデアが連鎖することを重視してた。それで、なになに君ちょっと描いてくれるか、って言って、すぐ絵にしてた。視覚化するんです」
次は、真鍋大度(メディアアーティスト)によるプレゼン。
ファックス音のようなルールを持った音の命令を受け取って点滅するキューブを実演した。
実はこれ「ファミリーコンピューターロボット」(1985年:開発横井軍平)にインスパイアされた作品。
ロボットは、コードでつながっていたりするのではなくて、無線。
「ビデオアートのフィールドで活動しているので、ナムジュンパイクの影響を受けてますか? とか聞かれることがあるのですが「製作のコンセプトや哲学で影響を受けているのは横井軍平です」と答えてます」
最後に岩井俊雄。
テノリオンの実演からスタートして、過去にさかのぼっていく構成。ワンダースワン版のテノリオンは、「WonderWitch」というプログラミングツールを使って、2001年自作ソフトとして個展で100コ販売。マニュアルも手作り、ラベルもプリンターで印刷して貼りつけ。そのころすでに1000円ぐらいに暴落していたワンダースワンを秋葉原を徘徊して100コ購入して、セットを自作したそうだ。
さらに、諸事情により発売中止になった幻のスーパーファミコンソフト「サウンドファンタジー」! 手廻しオルゴールから発想を得た音楽と映像を一致させる試み。
グンペイズムが根っこにあって、幾度もトライしていく楽しさや力強さを感じさせるプレゼンだった。
「いちから自分で作るのっていいんですよ。ワンダースワンのテノリオン作ってるときって、とても楽しかった」
軍平プロダクトは、カラクリのおもしろさに満ちている。手に取って、さわっていることがおもしろい。ものすごくベーシックで原初的な楽しさがそこにはある。
そして!
8月27日(金)、山崎功(任天堂コレクター/本展示の所蔵者)、米光一成(ぷよぷよ開発者/立命館大学映像学部教授/コレ書いてる俺!)、杏野はるな(ゲームアイドル)、川田十夢(AR三兄弟)の緊急トークショー「私たち、僕たちの横井軍平2」が20時から開催です。(米光一成)