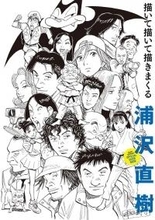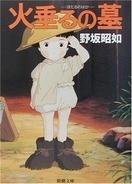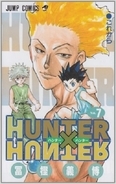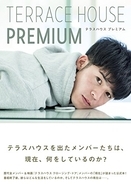中世にあったような「ナントカの変」だとか「ナントカの合戦」なんていうのが起こらない戦後の日本では、人々の不満や憎悪、あるいは社会の軋みなどが犯罪という出力方式に集中しやすい。犯罪が世相を映し、社会の問題をあぶり出し、それと戦うことによって国の統治能力や警察の捜査能力、国民のあらゆる意識が訓練される。犯罪は罰せられる悪であり、その犠牲はとても悲しいものではあるが、戦後日本の急速な社会発展は、犯罪が影響した側面も多いにあると思う。ゆっくり発展していく社会では比較的問題は予見しやすいし対策も事前に打てるけど、急成長していた日本では事件が起こって初めて社会病理が明らかになることが多かった、ということだ。
たとえば三億円事件は、単に白バイを使って「警察に化ける」という大胆な手法が通用してしまっただけの高額強奪事件ではない。犯人が逮捕されなかった背景には、犯人が警察組織に近い人間であった場合の捜査の鈍化があったのではないか、というような説もある。また、当時事件が起こった多摩地区で、三億円事件犯人を探すという名目で大規模な「活動家狩り」が行われたことも有名だ。
宮崎勤が繰り返した幼女誘拐・殺人事件も、「ビデオ収集が趣味のオタクが同年代の女性とまともな交流を持てずに幼女へ思念が向いた」というような単純な話ではない。いびつに急成長する社会で、狭い田舎社会での古い慣習に縛られたまま近代的な大学や企業へ入っていく犯人の世代に、色々なストレスが与えられていた。また、犯人は自分の殻にこもる性格がある一方で、雑誌の文通欄で知り合った録画ビデオ交換仲間がいたり、今のインターネット社会に通じるような「気に入った人間とだけ付き合う」という生活スタイルがあった。そういう人間が理解を得にくかった当時の社会で、彼らがどういう扱いを受けて来たのか、そのような部分も読んで考えてみる価値があるだろう。
グリコ・森永事件に関する本も、日常の生活用品が何でも大量生産されるようになり、コンビニやファミレスが町に現れはじめた頃の日本、今ある日本の原点の1つを詳しく見ていくようで面白い。
歴史は事件や事故、災害が積み重なって出来ている。そのなかでも犯罪は、人間の意識と無意識が強く活発にはたらく分野だと思う。この社会で起こった最近数十年の犯罪を深く理解しておくことは、今と将来この社会で生きていくことに大きな意義があるんじゃないかなと、僕は思う。多くはないが僕が読んだ本の中からおすすめする文庫本は以下の5冊。
・『三億円事件』一橋文哉
この人は他にも色々な事件について本を書いているので知っている人も多いかもしれない。退屈せずに読ませるのがとても上手い本が多いと思う。
・『M/世界の、憂鬱な先端』吉岡忍
宮崎勤事件だけでなく酒鬼薔薇事件などを扱いながら、まさに社会病理といったものを書いていく。長いけれど犯人の供述も豊富に書かれている。
・『グリコ・森永事件』朝日新聞大阪社会部
犯人からマスコミに届いた挑戦状や、事件現場の地図が詳しく、世の中全体を人質にして遊び続ける犯人とのやり取りがよく解る。
・『連合赤軍「あさま山荘」事件―実戦「危機管理」 』佐々淳行
事件当時の警備幕僚長という、他者では書けない視点で書かれた最凶のゲリラ立てこもり事件の表と裏。この事件は鉄球作戦以外にも注目すべきことが多い。
・『昭和・平成日本テロ事件史』別冊宝島編集部
一つ一つの事件については詳しくないが、40以上の有名無名のテロ事件が写真付きで列記されている。
当たり前だが、どの本も十分に資料を分析し、考察を行って書かれている。通して読むだけでも、ウィキペディアで事件の表層を調べるだけでは得られない深い理解と思索が、読んでいるうちになされると思う。
(香山哲)