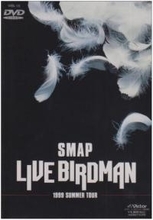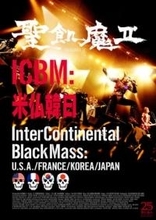今年で開館10周年を迎える、東京・お台場の日本科学未来館。スペースシャトルで二度の宇宙飛行を体験した、毛利衛さんが館長を務める、科学技術がテーマの博物館です。
その常設展示に、ゲームクリエイターが参加したと聞いて、さっそく取材してきました。「アナグラのうた~消えた博士と残された装置~」。「情報科学技術と社会」エリアで、10年ぶりにリニューアルされた展示物です。
演出は「ディシプリン*帝国の誕生」の飯田和敏さん。コンテンツディレクションはeスポーツプロデューサーとしても活躍中の犬飼博士さん。サウンドシステムは「ルミネス」シリーズなど多数のゲームサウンドを手がけた中村隆之さん。先日インタビューをお届けした「災害復興祈願サウンドゲームソフト『なぎ』」を手がけた面々なんですよ。
周囲を壁に囲まれた、長方形の展示スペースに足を踏み入れると、自分の情報が「ミー」という影に似た姿で足下に現れます。体験者の移動と共に足下について回り、他の体験者に近づくと、互いに手をつないだりすることも。
一応、展示スペースには人々の生体情報を24時間モニタリングする「絆創膏型センサー」など、最新の情報科学技術が学べるビデオ再生装置が、あちらこちらに配置されています。入場者の動きがモニタリングされているディスプレイなどもありました。でも、これらを視聴するのが目的ではないみたい。なんだか、普通の科学展示とは一線を画しすぎていて、大きな「?」マークが頭上に浮かんでしまったんですよ。
同館の科学コミュニケーター、小沢淳さんによると、本作は空間情報科学と社会の新しい関係を考える展示なんだとか。空間情報科学とは、コンピュータがセンサなどを介して、人やモノのふるまいを理解し、自分によりそってくれる技術のこと。そうした技術が普及した近未来は、どんな社会になるのか、考えを巡らせられる展示なんだそうです。
展示作品は今から1000年後の、かつて空間情報科学の博士たちの研究所だった、通称「アナグラ」という設定です。足下に表示される「ミー」は、コンピュータが見守ってくれて、「もうそろそろ時間ですよ」「こっちの展示をまだ見てませんよ」などと、控えめにナビゲートしてくれる案内人。
実はこれ、博士達が死に絶えた後も、残されたコンピュータが自律的に研究を続け、ついには人々を楽しませるために、自分たちで歌を紡ぐようになった……という設定なんだとか。なるほどねー。
というわけで、一見するとまったくそんな感じには見えないんですが、本作は最新技術のオンパレードです。位置測定にはレーザーセンサーが導入され、最大20名程度の動きを同時に計測できます。体験者の動作を元に歌詞が自動生成され、全10曲のダンスミュージックの伴奏に乗せて、ボーカロイドが自動演奏。体験者の条件が合うと、「祭り」と言われる特別な映像と音声が流れるなど、裏技的な仕掛けもなされているようですよ。
犬飼さんによると、未来館から個々の科学技術を展示するだけでなく、一つの「物語」にパッケージングして「体験」させてください、と提示されたのだとか。それこそ、要素技術をまとめ上げ、一つの「遊び」に昇華させて、プレイヤーに届けることを生業とする、ゲームクリエイターの真骨頂です。犬飼さんは、まず体験として欲しい。その意味をどう捉えるかは、それぞれの自由で良いと語ります。
未来館では本作と共に、もう一つ常設展示のリニューアルが行われました。
市民と会話すると、内容によって「技カード」がもらえます。ひととおり市を回ると、集めた技カードの中から、自分が市のために活用したいものを選んで、具体的に何をしたいか選択します。するとカードと行為の組みあわせによって、市の特性がさまざまに変化していきます。
同館科学コミュニケーターの嶋田義皓さんによると、人間の願いが科学技術の礎となり、社会貢献を通して、新しい価値観や文化を創り出していく、という思想を下敷きにしているとのことでした。
こんなふうに、二つの展示は共に「体験」というキーワードでまとめられるんですが、方向性は見事にばらんばらん。「2050年くらしのかたち」には科学まんが的な、お行儀の良さが感じられる一方で、「アナグラのうた」には既成概念を打ち破る、アバンギャルドなエネルギーが感じられます。
その一方で共に、映画やゲームといった日本のポップカルチャーを下敷きとした、世界に類のないユニークな展示であるという特徴も。説明し忘れましたが、「2050年くらしのかたち」では、「イノセンス」「キル・ビル Vol.1」などを手がけた美術監督の種田陽平さんが、制作に加わっているんです。
というわけで、ゲームクリエイターや映画・アニメの美術監督が、国の博物館の展示制作に係わるなんて、一昔前では考えられなかったことです。でも「体験」を演出するなら、彼らの右に出る者はいませんよね。実は両作品の制作期間中、あの東日本大震災があったんです。それだけに自分たちは何ができるか、改めて問い直す良いきっかけになったのかもしれません。一方で社会もまた、彼らの活躍を受け入れる準備ができはじめた、ということなのでしょうか。
ま、そういった小難しいことは脇においておいて、単に体験するだけでも楽しめますので、ぜひ夏休みのラストは未来館に足を運んではいかがでしょうか。言うまでもなく、子どもからお年寄りまで、誰もが楽しめること、請け合いです。
(小野憲史)