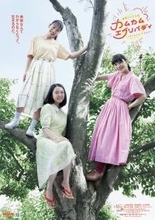いや、勝手にそう呼ばせてもらっているだけなのだが、映画や物語のなかで“風車”が効果的に登場し、まるで主要登場人物のように名演技を見せてくれる作品だ。
例えば、アカデミー賞も受賞した名作「レインマン」。映画の冒頭、父の死を知ったトム・クルーズ演じるチャーリーが土煙を上げながら車をUターンさせるシーンで、アメリカらしい赤土の上に並ぶ白い風車群が登場する。何百もの風車がぐるぐるとまわるその姿は、そこから物語が大きく動き出すことを示唆してくれる。
例えば「マッハ!!!!!!!!」の監督プラッチャヤー・ピンゲーオの作品として人気も高い「チョコレート・ファイター」この映画ではヒロインの少女ゼンが日本人の父親と新たな人生を歩みだすラストシーンの舞台として、北九州にある響灘風力発電所が描かれる。それまで終始暗いトーンで描かれていたこの映画の中において、青空の下、風車に向かって歩き出す二人の姿が前向きな未来を連想させる。
このように物語の中で登場する風車は、一般的に連想されがちな「エコ」といった短絡的なイメージではなく、「未来」もしくは「未知なるもの」の象徴として描かれることが多い。その点を把握してから作品鑑賞に臨むと、映画の見る視点も変わってくるのだ。
そんな風車映画のジャンルに新たな作品が加わった。風車で村の電力をまかなうことを夢見る電気工の姿を描いた映画「明りを灯す人」だ。
生きること、真面目に生活をしていく苦労、そしてそこに必然として存在する電気、という構図はエネルギー問題に揺れる日本にとってはまさにタイムリーな映画だ。
舞台は天山山脈のふもと、遊牧民の暮らしが残るキルギスののどかな村。「明り屋さん」と呼ばれる電気工の男が家々に電線と電球を取り付けていく。
こう書いていくと人情系ほのぼのムービーのようだが、作品内容はのどかな情景とはウラハラに政変でゆれ貧困問題にあえぐキルギスの社会背景もあってなかなか重い。その中にあって未来への希望として象徴的に描かれるているのが、主人公が独学で作ったオンボロ風車だ。だが、村の人々は「明り屋さん」を信頼しつつもこの風車を奇異なものとして扱い、村全体の風車がまかなえるほどの大規模風車群を作る計画もバカにされていた。
これらのシーンを見たとき、私は『風をつかまえた少年』というノンフィクションを思い出した。アフリカに住む少年・カムクワンバは、図書館で借りた本を読んで独学で研究し、自転車のチューブや廃材置場から拾ってきた金具などを集めて粗末な風車を作り始める。ほとんどの家に電気など通っていない村にとって少年の語る風力発電による電気のある暮らしはバカげた奇行でしかなかったが、失敗を重ね、試行錯誤を繰り返して完成させた手作り風車が生み出した電力によって、村の生活と少年の未来が開けていく。
フィクションとノンフィクションの違いはあれど、アフリカの少年にもギルギスの電気工にも共通することは、風車が「異質なもの、奇異なもの」として周囲に受け止められている点だ。いくら設計図を書いて説明しようとも、想像すら出来ないことは「未来」ではなく「奇行」でしかない。その奇行に注がれる周りからの冷たい視線に打ち勝ってこそ、本当の意味での未来が切り開かれていくのだ。
映画の中で、明り屋さんの数少ない理解者である村長にある政治家がすごむシーンがある。
<俺が当選すれば後悔はさせない。
だが、そこでの村長の切り返しがステキだ。
<この土地は不毛じゃない。人が生きている。子供が生まれ育っている>
受け継いできた大地への誇りと未来へのかすかな希望。そんなキルギスの大地に立って風を受ける風車は、健気で無骨だけれども、やっぱり未来に向かってまわっているのだろう。
そう考えるとこの作品、「電気泥棒(Light Thiever)」という英題よりも「明りを灯す人」という邦題のほうが間違いなくいいタイトルだ。未来を予感させるタイトルこそ、風車映画にふさわしい。(オグマナオト)