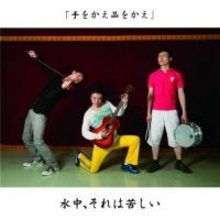ぼくが会場に着いたのはちょうど、『最弱球団 高橋ユニオンズ青春記』の出版記念も兼ねて開かれた著者の長谷川晶一氏とユニオンズOBの佐々木信也氏とのトークセッションが始まるところだったので、まずそれを観ることにする。佐々木氏はユニオンズのチームメイトとの思い出のほか、自身と新人王の座を競った西鉄ライオンズのエース・稲尾和久の豪快伝説(ダブルヘッダーの直後に博多湾へ釣りに連れて行かれたという話には驚嘆した)も披露。さらに会場からの質問に答える形で、大毎オリオンズから退団を通告されたのちジャイアンツの水原茂監督から誘いを受けていたことを明かしたり、また最近の野球解説者は選手を持ち上げるばかりで毒舌を吐かない、これじゃテレビ中継が面白くないのは当たり前! とバッサリと斬り捨てたりと、佐々木節は78歳になったいまも健在であった。
トークセッションが終わるとさっそく会場をまわる。ブースじたいはけっして多くはないのだけれども、売る人の熱意はあちこちから伝わってきた。レプリカユニフォームを着た人が目立ったのもこのイベントならではだろう。こんなことなら、ぼくもひいきの中日ドラゴンズのユニフォームを用意しておけばよかった……とちょっと後悔。このイベントらしい光景といえば、受付に置かれたノートPCでは、ちょうど北海道日本ハムファイターズと埼玉西武ライオンズによるパ・リーグのクライマックスシリーズ・ファーストステージのCS中継が流され、試合の山場ともなると参加者が自然と集まっていた。
で、気がつけば、ぼくの手元には本がどっさり。もともと野球本が好きなだけに、あれもこれもとついつい買いこんでしまったのだ。最初に買ったのは、広島の文工舎という出版社のブースで販売していた『全身野球魂 長谷川良平』という本。長谷川良平は初期の広島東洋カープを代表する投手で、のちに監督も務めている。じつは長谷川の出身地は愛知県半田市ということで、同じ知多半島出身者のぼくは親近感を勝手に抱いていたのだ。ちなみに文工舎は、著述業の堀治喜さんが経営する個人出版社で、ブースにはこのほか『衣笠祥雄は、なぜ監督になれないのか?』(この12月には増補版が洋泉社の新書yから刊行予定だという)や『球場巡礼』など堀さんの著書が並べられていた。続いて買ったのは「嫁に来ないか」というミニコミ誌で、これまた特集は広島東洋カープ(編集長のハッチモさん自身は東京ヤクルトスワローズのファンらしいのだが)。球団のグッズ担当者にインタビューしているということで帯には「広島東洋カープうっかり非公認」と銘打たれていた。特集以外にも、「女子野球観戦部」と題して野球の基本的なルールの解説、あるいは各チームの特色についてそれぞれ女子ファンが紹介している。女性の視点からプロ野球をとらえるというのが斬新だ。それにしても会場にはなぜかカープ関連の本、ファンが目立った。カープは文化系との親和性が高いんでしょうかねえ。
今回の“戦利品”のなかでも個人的にとくにうれしかったのは、スポーツ本に強い古書店としてその筋では有名なビブリオのブースで買った、杉並区立郷土博物館での特別展の図録『上井草球場の軌跡』。これは西武新宿線沿線にかつて存在した上井草球場の歴史をたどったもので、同球場を本拠地としたプロ球団・東京セネタースのOBとして野口二郎がインタビューに答えていたり、同球場での大学野球の思い出を法政大OBで近鉄などで活躍した関根潤三が語っていたりと野球史ファンにはたまらない内容だ。ちなみに上井草球場の跡地にはいま上井草スポーツセンターが建ち、その一角では球場に関するパネル展示も行なわれている(ぼくも『私鉄探検』という本を書いたとき訪ねたことがある)。
このほかにも、『野球部あるある』著者で白夜書房の雑誌「野球小僧」の編集部員である菊地選手からサインしてもらったり、“野球DJ”のファンタスティック・ピッチング・マシーン中嶋とヨシノビズムの両氏(イベント「プロ野球 音の球宴」を主催)が、会場でプロ野球関連のさまざまな名曲・珍曲をかけ続けたりと、さまざまな趣向に楽しませてもらった。
さて、このブックフェアは、「野球小僧」誌の編集部員から最近フリーの編集者に転じ、前出の書籍『最弱球団』などを手がけている林さやかさん(横浜ベイスターズファンという林さんは、大洋ホエールズ時代のブルゾンを着ていた)が企画、ほかにも野球好きの編集者たちも実行委員に加わり準備を進めてきた。林さんに訊いたところ、この日11時の開場前にはすでに、スポーツジャーナリストの安倍昌彦氏のトークイベントをめあてに参加者が行列をつくっていたとか。その後も、前出の『最弱球団』及びえのきどいちろう・ながさわたかひろ両氏の各トークセッションの直前になるとまた新たな来場者が詰めかけたりと、終了時間の18時まで客足は途絶えることはなかった。
そういえば、エキレビ!ライターのひとりで古書コレクターでもあるとみさわ昭仁さんと今回のイベント開催を前に、こういうあるジャンルに特化したブックフェアが増えると面白いですよねと話していたのだった。たとえば、旅本やグルメ本、タレント本でもこういうイベントがあってもおかしくないだろう。
ともあれ盛況のうちに終わった東京野球ブックフェア。来年も開催を予定しているというので、さらなる発展が楽しみだ。