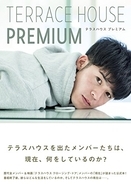もちろん使い方は様々。
さて、オタクという言葉が生まれたのは1970年代。80年代になってアニメやSFのファンに対しての呼称として使われ始め、90年代に定着しました。自嘲的だったり否定的な意味合いが強くなったり、時には「こだわりがある人」というプラスの側面が追加されたりとうねうね変わる不思議な言葉です。
不思議な言葉っつーことはですよ。ようは便利な言葉なんですよね。とりあえず使っておけばいい、みたいな。
ではこの「オタク」という言葉が定着していなかった80年代、なんと呼んでいたのかってことですよ。
ん! そこのあなたもうお分かりのようですね。 ん! そこのあなたまだ生まれていない! そういう人も多いですよね。
80年代一部のマニアの間では「ビョーキ」という言葉が使われていました。
使用例。
「ほんとお前、クラリス(「カリオストロの城のヒロイン」)コンプレックスで、ビョーキだからなあ」
「そちらこそ大概ビョーキでしょう、弁天(「うる星やつら」)のビキニ甲冑至上主義ですしなあ」
「いやいや、私など足下にも及びません」
オタクと入れ替えてもそのまま通じます。
自嘲を含みながらも、ある一定のプライドを持った「マニアの共通言語」的な意味合いのある言葉です。
こんな「ビョーキ」な人々の80年代の青春を描いた作品が、一本木蛮の自伝的作品『同人少女JB』です。
なんせ表紙からしてラムちゃんのコスプレですからね! 最近は同人誌を描く少年少女の作品が増えたとはいえ、80年代の実体験を描いた作品はそうそうありません。
男性版でプロを目指す作品だと、島本和彦の『アオイホノオ』があります。作者の一本木蛮は島本和彦イズムを受け継ぐ、漫画家でありコスプレイヤー。コスプレ黎明期としては非常に目立つ人でした。
大雑把な内容としては、80年代の投稿職人であり同人活動に足を踏み入れた少女の物語。なんですが、いかんせん出てくるガジェットがいちいち80年代の匂いを濃厚に漂わせすぎているから面白いんですよ。
まず基本的なことですが、ネットがありません、ケータイもありません、パソコンも普及していません。
はがきは一枚20円。コピーはサイズによって値段が違う。
ネットという情報源がないとなると、飢え渇いたオタク……ビョーキでマニアな人たちは何を漁ったかというとアニメ雑誌です。
アニメージュは今もありますが、他には「ジ・アニメ」「マイアニメ」「アニメック」「OUT」「ふぁんろーど」。まさにアニメ雑誌黄金期。
この時代を知っている人にはゾクゾクするような80年代マニア文化の細かいディティールがこれでもかと盛り込まれているんです。キャラクターの部屋一つとっても、ネタの宝庫。
まぎれもない、これは80年代マニアの「記録書」だ!
投稿職人からプロになった人も多くいたこの時代、彼女はマニアの集う書店で運命的な出会いを果たし、「同人誌」の世界に足を踏み入れます。
今でこそ夏・冬のコミケ(コミケット・コミックマーケット)は一大イベントとなっていますが、当時は年三回。1975年冬から開催されはじめたばかりで、まだまだ黎明期でした。晴海や川崎市民プラザ、と言われて懐かしくなる人もおられるんじゃないでしょうか。
規模は今よりはるかに小さいですが、情報のない世界に生きてきたヒロインにしてみたらもうカルチャーショックなわけですよ。
「うわぁ……これ全部…?! ビョーキの人?!」
そう。褒め言葉なんですよね、ビョーキ。熱心なファンだよ、と。
時代は変われど、ファンの熱意はどの時代も変わりません。
しかし情報への渇望、できないことへの挑戦心は今よりも大きく、爆発力も巨大。若さゆえの過ちの空振り感も巨大。
少女の青春記録としても面白いのですが、80年代の貴重な記録としての価値が高い作品なのです。
正直自分も「ハマトラ」「ニュートラ」は知りませんでした。
これ、NHKの朝の連続テレビ小説になりませんかね。
(たまごまご)