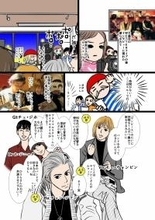ビールを飲んでいたらいきなりお経がはじまった! 思わずグラスを持つ手が止まる。自分だけじゃなく、隣に座っていた女性もビールを飲んでいいのか迷っていた。
ここは、ニフティが運営するイベントハウス「東京カルチャーカルチャー」。
お経の主は浄土真宗東本願寺派緑泉寺・青江覚峰住職。
2月17日に開催されたイベント「『お寺ごはん』実食ナイト」の冒頭での出来事。
このイベントは、以前レビューでも紹介したレシピ本『『お寺ごはん』の著者である青江住職が、素材や料理工程の一つひとつの考え方・ポイントを説明。そして実際にその料理も味わってしまう! というもの。でも、料理が出てくる前に「オープニングお経」ですっかりひき込まれてしまった
青江住職は、「料理僧」を名乗り、食を通して仏教の教えを伝える活動をしているお坊さん。その教えの根底にあるのが<向き合う>ことだ。
以前インタビューした際にも、「素材と向き合うこと、作る相手と向き合うこと、そして自分自身と向き合うこと(略)…<向き合うこと>の大切さをこのレシピ本を通して見直してもらえれば」と述べていたのだが、この日もその教えは変わらず、数々のレシピを生み出すため、日々いかに食材と向き合っているかを語っていく。
象徴的なのが、『お寺ごはん』の肝でもあり、料理の基本「だし」づくり。
精進料理であるため、当然カツオや煮干しといった魚介系のだしはNG。じゃあ、何でだしを取るのかといえば、「昆布」「しいたけ」「わかめ」などの乾物系をベースとして押さえつつ、住職のオススメは「大豆だし」。
「この時期、節分で余った大豆がご家庭にたくさんあると思います。ぜひ、大豆と向き合ってください。トランス状態になれますよ」
なんでも大豆からダシを取るためにフライパンで煎ると、5分~10分くらいで「カラカラ」という音が「コロコロ」に変わり、さらに30分ほど煎り続けると再び「カラカラ」という軽い音になるんだとか。焦がさないように丁寧に大豆と向き合うことで、畑の肉・大豆の旨味が引き出され、かつおだしよりも力強い味のだし汁を作ることができるという。さらに、ひたすら同じ行為を繰り返すことでトランス状態にもなれるオマケつき。
例えば、普段のみそ汁でも、大豆だしで作ると豚汁のような厚みのある味になる。と聞いて早速家に帰って試してみた。でも、大豆への集中力が足りなかったのか、見事に焦してしまい、苦いみそ汁に……。30分も煎り続けるって結構な修行であることを実感する。
「だし」の話はまだまだ続く。
レシピ本の中でも紹介され、この日特別メニューとしても提供された「一石三鳥精進鍋」(※イベントでのメニューは精進汁)。豆乳と赤みそ&白みそのやさしい味わいがたまらないこの料理のだしはなんと「野菜の皮」!
人参や大根などの野菜の皮を捨てずに天日干しにし、それを水に戻して沸騰させるといいだしが取れるという。
この日のイベントでは他にも、「人生で一番古い“食の思い出”と向き合う」「食と音の関係性と向き合う」というワークショップを通して、生きる上での「食べることの重要性」を説いていく青江住職。
住職自身、お寺の息子として生まれたものの、お坊さんになるのが嫌でアメリカに渡りMBAを取得したという異例の経歴の持ち主。ところが「9・11」に遭遇したことで改めて自分自身と向き合ったことで、日本人であること、お坊さんという職業を改めて見つめ直し、今日に至った経緯を語る。
そして、それは「食」も同じ。
「美味しい」と漫然と味わうだけでなく、何が美味しいのか、どんなシチュエーションで食べることがより思い出に残るのか、一生懸命考えながら食べることが重要なことなのだ。
「料理は舌だけじゃなく、記憶と心で食べるもの」という教え、ごちそうさまでした。
(オグマナオト)