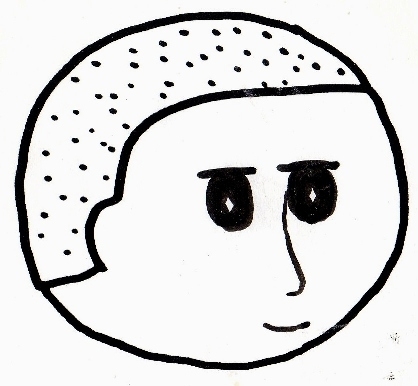――露骨に太鼓持ちしてる人って、いますねぇ~。
「太鼓持ちっていうと、『媚びる』『へつらう』『よいしょ』といったイメージで、太鼓持ちや太鼓を叩く人は一段下に見られる傾向があります。しかし、それは『太鼓の持ち方』に問題があるからで、正しく太鼓を持って正しく叩けば、同僚や後輩から『あいつ、必死じゃねーか』と影口を叩かれなくなります。目指すは、誰からも愛される太鼓持ちというわけで、そのための解説書です」
溝端さんによると、しょせん、出世できる人なんて、毎週のように引き抜きのオファーがある人か、社長の息子ぐらいのもの。それでも出世を望むのならば、身のほどを知ることが大事で、自分が子分(凡人)であることを認めてしまえば、媚びることの抵抗はなくなるとのことだ。
「誰からも愛される太鼓をもって、叩き鳴らしましょうよ」
ということで、4つの例を紹介していただくことに。
一つめの“太鼓”から。
●「何やっても品がありますよね!めっちゃ言われません?」
――けっこう、デカい太鼓ですね~(笑)
「あたかも言って当たり前!逆に今さらこんなことを言ってスミマセン感を出せればGoodです」
――この太鼓使う上での注意点は?
「このフレーズは、太鼓としてはいたって平凡ですが、ポイントは誰からも褒められたことのないところを褒めること。新鮮で嬉しいですからね。
――でも、中には褒められてないというか、褒め言葉さえ疑ってくる上司もいません?
「確かにいます。特に褒められ慣れていない上司にありがちです。『こいつ、適当に言ってるだけかも…』という疑惑が上司の脳裏をよぎるかもしれないので、満を持して『めっちゃ言われません?』を付け加えるんです」
――おお!部下からすると「言って当たり前感」ですね。
「疑惑を解消すると共に、自信をもたせてあげるわけです」
続いて…
●「行ったら、絶対楽しくて 帰りたくなくなっちゃいますもん!」
――初めから「行きたくない感」を出さないという感じですね。
「そうです。あとは注意点がありまして、お金がないからとか、禁酒してるからという理由で断らないこと。この理由で断ってしまうと、他の人とは飲みにいけなくなっちゃうんです。後日まで引きずるような断り方は、あとのこともしっかり考えておかないと、つじつま合わせでボロが出てしまうので気をつけましょう」
――なかなか、断るにしても気を使いますねぇ~。
「断るのも3回中1回にしましょう。相手に『こいつは断る』という印象を付けてしまってはいけません。太鼓持ちにとって、飲みの席は一番の腕の魅せどころなのに、誘われなくなったら、太鼓持ちとしては『もう終わり』ですからね」
続いて…
●「○○(上司の名前)チルドレンで、ホントよかった~」
――確かに、言われたら嬉しいですね。言う時のポイントは?
「誰に言うでもなく、大きめの独り言っぽくつぶやきましょう。
――じんわりと沁みてくる感じがいいですね。
「ただ、仲の良い同僚や後輩の前でいきなり使うと不自然なので、上司のいないところで使っておいて、同僚や後輩達の耳を慣れさせておくことが重要です」
――確信犯的!!(笑)
「上司の照れ笑いが横目で確認できれば大成功です」
――この太鼓を使うと、とりわけ持ち上がりやすい上司はどんなタイプですか?
「単細胞上司です。おだてにめっぽう弱く、『さらに上司』や同僚、挙げ句は部下にもいいように使われるような上司ですね。しかも、単細胞上司は『みんなが』という言葉にめっぽう弱いので、『自分だけじゃなくて、みんなの意思』であるかのように伝えると、より効果的です」
――なるほど~。思わずメモをとっちゃいました。
最後は…
●「あぁ~、これは童貞卒業した時以来の感激です」
――これは言う時のハードルが高そう…
「言葉を発する前に、少し無言の“間”を作るといいです。この間も大切なので、目を閉じる。ため息をもらすなどで注目させるとGoodです」
――「童貞卒業」を用いてくるインパクトは大きいですね。
「男にとって、童貞卒業ほど人生の感激はありませんからね。使う場面としては、とんでもなく美味しい料理をごちそうになった時や、誕生日や結婚祝いをしてもらった時がいいでしょう。
――あと、多用しない方がいいかもしれませんね。
「やはり、インパクトが大きいので、1人1回しか使えないのが難点ですが、ハマればこの一言で『こいつの表現力、スゲーな』となること、間違いなしです!」
今回はサラリーマンの太鼓持ちの例だが、中には奥さんの太鼓持ちをしているという「二重太鼓持ち生活」の人も多いかもしれない。となると、定年退職した後も、一生、太鼓持ち生活を送ることとなるわけであって…。もしも旦那さんがこの本をこっそりと買っていたら、奥さんは少しでも癒してあげてください。
(取材・文/やきそばかおる)
『正しい太鼓の持ち方~上司を転がす35の社交辞令』
著:トキオ・ナレッジ
お山の大将上司、無計画上司、マニュアル上司、ワンマン上司、七光り上司、正論上司、ストイック上司、年下上司、叩き上げ上司、おちょこ上司 etc.――ひとクセもふたクセもある上司を転がすコツが満載。(上司だけでなく、取引先の人はもちろん、言い回しを変えれば部下にもつかえます) 「太鼓持ちの心得7カ条」「覚えておきたい相づち集」も堂々の掲載。