第1回配本、第1巻は『からたちの花』(1933)です。
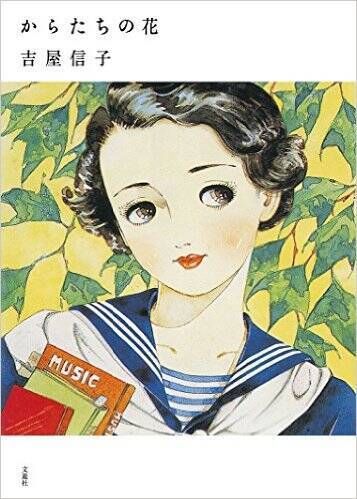
表紙画像にダマされないこと
少女小説というと、表紙絵が中原淳一や藤井千秋なんかの叙情画の、かわいらしい少女というイメージがあります。
この作品も、表紙に松本かつぢ(1904-1986)描く美少女が用いられています。
けれど、大正・昭和初期の少女小説は、ライトノベルではありません。叙情画もまた、現在の萌え絵とは少し違うものです。
どういうことかというと、表紙画は、必ずしも作中のキャラクターの姿ではないのです。
というのも、『からたちの花』は、容貌に恵まれないことを気に病む少女が主人公なのです。
少女小説版『ジェイン・エア』?
吉屋信子の少女小説の特徴は、「異性愛」の気配を必ず消していることです。出世作『花物語』しかり、私の大好きな『わすれなぐさ』しかり。
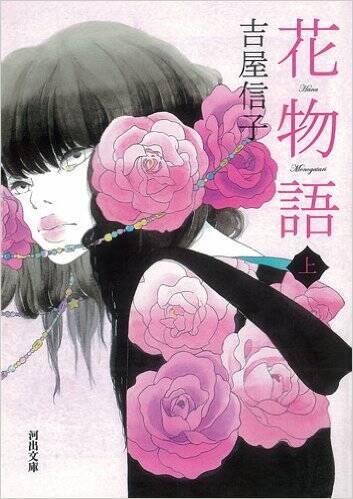
にもかかわらず、吉屋信子の少女小説の多くは、ロマンスの香気を漂わせています。
恋愛なしでロマンスの香りを出すには、ヒロインが美少女である必要があるわけですが、『からたちの花』は、そこを敢えて封印した、ビターな作品なのです。
ヒロインが不美人という設定のロマンスというと、シャーロット・ブロンテの『ジェイン・エア』(1847)がそうですが、その集英社文庫版の表紙画が美人の絵なのと同じくらい、内容とかけ離れた表紙だと思ってください。
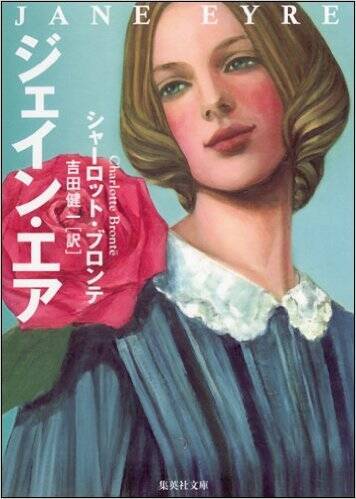
容貌というより、自己評価の問題?
今回10年以上ぶりに読み返して発見したのは、これは不美人の話というより、自己評価の低い人の話として読めてしまう、ということです。
ヒロイン麻子の母は、娘に美しくあってほしいあまり、妊娠中に小野小町の掛軸を掛け、リリアン・ギッシュなどのハリウッド女優のブロマイドをピンナップするという、ちょっとヘンな胎教を実行する人です。この当時は産まれる前に性別はわからなかったのではないかと思いますが、男でも美少年がほしかったようです。
自分の子どもは美しくある「べき」であると思いこんでいるこの母は、だから生まれた次女・麻子の顔を見て、〈この子へんじゃない?〉と言うのです。自分の理想が正しくて、現実の娘のほうがまちがっているという把握。ひどい話ですね。
毒母の呪いで自己評価が低迷!
姉・蓉子や妹・桜子は美しいのに、自分は美しくない──このことが幼い麻子を苦しめ、長じてもなお彼女の性格を暗くしてしまいます。
じっさい、彼女は姉や妹に比べたら地味な容貌だったのでしょう。
けれど、それに駄目押しするのが母の言葉です。
〈あの子には、なにを着せても引き立たないものだからねえ〉
それだけではなく、姉の蓉子や、麻子に慕われている(麻子の唯一の味方という設定ですらある)麻子の名づけ親の若い叔母さえ、言葉のはしばしに、「お前は容貌以外で頑張れ」的なニュアンスを帯びてしまう。
悪夢のような容貌重視社会!
周囲の評価を内面化した麻子は〈存在のうすい子〉〈かまわれない子〉となり、〈愛されたい努力〉をするようになるのです。たとえば、遠足で足が痛いと仮病を使っていたわられようとするが、嘘がバレて顰蹙を買うとか。……ツラい。
言葉のDVが止まらない
毒母の呪いで自己評価が低迷した麻子は、嫉妬に満ち、またどんどん自意識過剰になり、周囲の自分への視線を勝手に邪推するようになっていくのです。
妹・桜子が死病にとりつかれたとき、
〈桜ちゃんあまえっ子できらい。死んじまっても、かまわないや〉
なんてことを言う。これもたいていひどいんですが、桜子が死んだときに姉の蓉子が、
〈麻ちゃんが、あんなひどいことを言ったもんだから、桜ちゃんは死んじまったのよ〉
と言うのも、もっとひどくないかこれ? この一家、言葉の暴力が甚だしすぎます。
愛に飢えると、世界は敵に感じられる
このあと小説は、麻子の女学校への進学や友情、姉の結婚など、少女のライフステージを追って進みます。
とりわけ、愛されて育ったらしい明るい少女・藍子との友情と、彼女への反撥は、作品の背骨となっています。
なお、『からたちの花』という題は、北原白秋作詞、山田耕筰作曲の同名の曲から取られています。この歌が、麻子と藍子とを出会わせることになるのです。

小説のクライマックスには、〈人の未来のすがたがうつる〉という言い伝えのある鏡なんてものが出てきます。嵐の晩に、麻子はそこになにを見るのでしょうか?
今回読んでみて、吉屋信子の臨床心理学的直観に驚きました。なにしろこの小説は、麻子がどのようにして
〈わが心をだきしめ、いつくしむ『自愛』の感情〉(最終章にある言葉)
を持つにいたるか、つまりどうやって精神的に自立するか、という小説だったのですから。
愛に飢えると、「他者が自分を愛してくれるかどうか」で世界が決まってしまい。つまり世界は敵に感じられる。その飢えを満たすのは、他者からの愛ではなく、まずは〈自愛〉(=自己承認)である。──これってほとんど、二村ヒトシ『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』の「心の穴」仮説ではありませんか。

「みっともない子」(仮)
少女小説というと、なんだか「リアリティ」のない作り話のように思う人もいるでしょう。
しかしこの作品は、愛を求める人間の「心の世界地図」を、きちんと反映していて、極端な話なのに奇妙な説得力があるのです。
掲載誌《少女の友》で当時編集長だった内山基の回想エッセイ「『からたちの花』の思い出」が、巻末に再録されています(私が最初に読んだポプラ社版にも収録されていたと思います)。
〈ひとりの容貌の美しくない子の魂の発展を主題に書いてみようと思う〉
と言って、
「みっともない子」
という題で連載しようと言い出した(笑)ので、内山編集長はその〈あまりにリアルでありすぎる〉題にたじろぎ、お願いして題を考え直させたという。
しかしこの「みっともない子」という題は、主人公の愛に飢えた僻みっぽい局面をズバリ言い当てた題だと、いまとなっては思いますねえ。
貴重な作品が続刊
21世紀にはいって、国書刊行会の《吉屋信子乙女小説コレクション》全3巻(『わすれなぐさ』、『屋根裏の二処女』、『伴先生』)、ゆまに書房の《吉屋信子少女小説選》全5巻(『暁の聖歌』、『返らぬ日』、『紅雀』、『三つの花』、『毬子』)と、吉屋信子の小説の復刊が続きました。そして今回新たに文遊社から《吉屋信子少女小説集》全5巻が刊行されることになります。
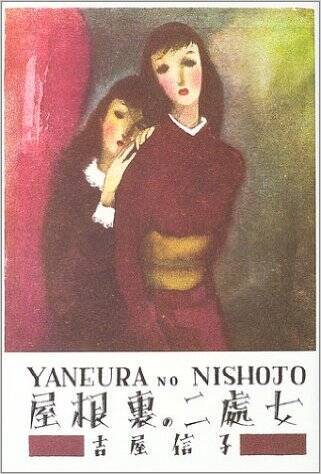
今回私が期待しているのは、第2巻『青いノート 少年』、第3巻『白鸚鵡』という、読んだことのない作品が入っていること。また第5巻『七本椿』(これも傑作)に、短篇シリーズ『小さき花々』の単行本未収録作が併録されるということです。楽しみです。

(千野帽子)




























