文学フリマ事務局は目下、「文学フリマ百都市構想」の目標を掲げ、各地で文学フリマを開催したいという有志を支援している。一昨年より始まった大阪での文学フリマはこの9月に第3回が行なわれ、すでに定例化している。前後して今年4月には第1回文学フリマ金沢が開かれた。今回の福岡は、それに続く新たな都市での開催ということになる。さらに来年、2016年には7月に岩手、9月に札幌でそれぞれ初となる文学フリマが予定され、北から南まで開催地は着実に広がりつつある。
私が福岡を訪れるのは、6月のヤフオクドームでのAKB48選抜総選挙および著書の取材以来4カ月ぶり。今回の文学フリマには1人での参加とあって、ブースをなかなか空けられなかったため、客として会場を回ったのは駆け足になってしまった。それでも、熱気は十分に感じられた。ここで、会場で購入した本のなかから、とくに印象に残ったものを紹介したい(以下、見出しに本のタイトルのあと、カッコ内にサークル名を記す)。
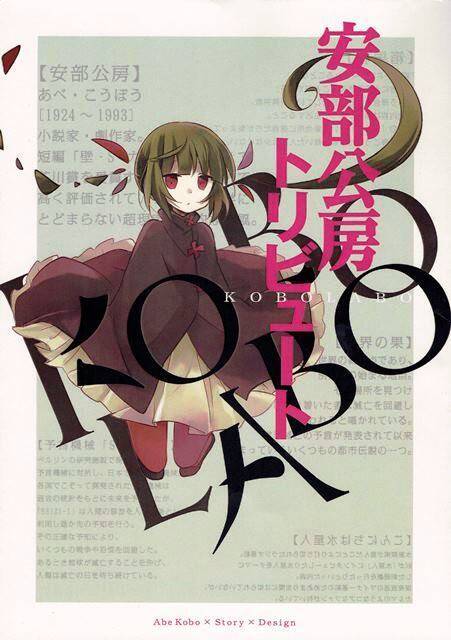
『安部公房トリビュート・KOBOLABO』(misosio)
今回、出店サークルのカタログを見ていて、まず興味を抱いたのがこの本。タイトルのとおり、作家・安部公房(1924~93)の作品を題材に、その作中人物のキャラ化、あるいは作品に登場する架空の昆虫「ユープケッチャ」をモチーフとしたサイドストーリーなどを収録している。サイドストーリーは、文章の配置も凝っている。小説にとどまらず、写真や演劇、映画とビジュアル面でも多くの作品を残した安部公房にふさわしいアプローチの仕方といえる。
そういえば、ここ数年、坂口安吾の小説をベースとしたアニメ「UN-GO」など、文学作品の現代アレンジが盛んだが……と書こうと思ったら、この本のなかでも「オタクと文学の関係、本書に至るまでの経緯を語る。」と題して近年の動向にちゃんと言及されていた。安吾が採用されるのであれば、現代の都市生活者たちを主人公とした公房作品はもっと現代風にアレンジされてもおかしくないだろう。
この本にはまた、《「KOBOLABO」をきっかけに、公房作品もついでに読んで頂けたら幸いです》という一文があり、制作者たちの自信をうかがわせる。その言葉どおり、巻末には主要作品リストが付され、短評とともに読みやすさが星の数で示されるなど、非常にとっつきやすい入門書となっている。
『嘉村礒多選集 私小説の極北的な』(ヴィリジアン・ヴィガン)
『安部公房トリビュート』が変化球としたら、こちらはストレートな作家へのアプローチ。嘉村礒多(1897~1933)は、福岡とは関門海峡を挟んでお隣の山口県出身の小説家で、自らの経験を赤裸々に告白した私小説を数々残した。この本は、中西祐介さんが同郷である嘉村の短編から選りすぐったものをまとめたもので、現在までに2巻刊行されている。
最初の巻のあとがきによれば、生家が現在も保存されるなど、嘉村のゆかりの地をまわるのは比較的容易らしい。だが中西さんは、作品を読むまでのハードルが高いと感じたことから短編集の制作を思い立ったのだとか。嘉村を世に知らしめたいという熱い情熱を感じる。
ちなみに収録作品のなかでも私が一番興味深く読んだのは、「恋文」という一編。嘉村が勤務先の女学校の同僚にあてた手紙に加筆したものらしく、短いながらも苛烈な想いがつづられている。しかし実際に出したラブレターを作品として発表してしまうとは、激しい……。

『珈琲千話 ―ジェノバの珈琲ものがたり―』(つきしろ)
イタリア・ジェノバに住む「私」が「君」に宛てた手紙という体裁で、街のバーで見聞きした話を店ごとにつづった本。これは一体、小説なのかノンフィクションなのか。巻頭の「注」には、《話は長年の間に書き留めたものであるので、メニュー、料金等、変わっている可能性が(高く)有り》とあるので、どうやら出てくるバーはすべて実在し、書かれているエピソードも実話のようだ。
それにしても、出てくる話がいちいちおかしくて、つくってるんじゃないのかと思わせるほど。たとえば「アッティリオのバー」と題する一編には、バー(厳密にはバーではないのだが)に行くまでのバスの行程が書かれているのだが、「私」が人から聞いた話としてこんな信じがたいエピソードが出てくる。
あるとき山のくねくねした道を進んでいる途中、運転手が急にバスを停め、車体の側面をガンガン蹴り始めたことがあったという。乗客たちがその様子をあっけにとられて見ていると、連絡を受けてやって来た別の運転手が恐縮ながらこう説明した。「すみません、ノイローゼ気味になっちゃって。このコース、難しいんです」。ほんとかよ! とツッコみたくなる一方で、まあイタリアならありうるかもと失礼ながら思ってしまったりもする。
本書の著者は月魄なゆたさん。熊本のgoodbook出版より刊行。喫茶店で熱いカプチーノをゆっくり飲みながら読みたくなる一冊だ。
『片隅』01(伽鹿舎)
「九州発」「九州限定配本」という触れこみの文芸誌の創刊号。巻頭には谷川俊太郎氏が「隅っこ」と題する詩を寄せているのが豪華。
ほかにも建築家・作家の坂口恭平氏による詩と写真、お笑いコンビ・キリングセンスの元メンバーの萩原正人氏による小説、また、九州各地から作家やさまざまな職業の人たちが寄稿している。このうち大分の古書店・カモシカ書店の店主である岩尾晋作さんのエッセイ「古書市のない都市から」につづられた、本の買い取りに訪れた家で老婆とその亡くなった夫の人生の一端に触れるエピソードなどドラマチックで魅入られた。
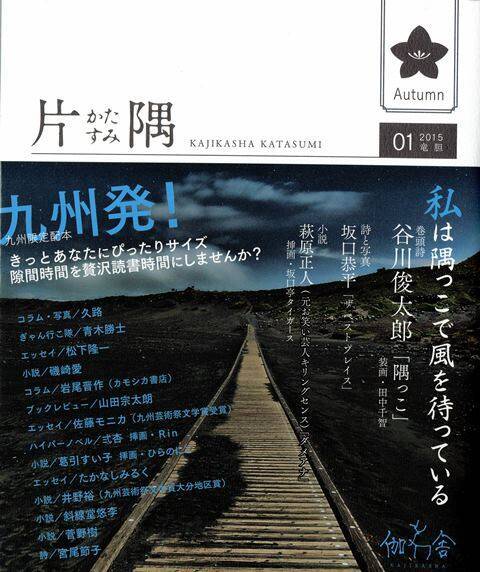
福岡の人たちは温かかった
文学フリマ福岡の会場には午前11時のオープンより客足が絶えず、盛況を見せていた。閉会の30分前、15時半すぎには、入場者への配布用に用意されたカタログ600部すべてがはけたとのアナウンスがあった。
私が出店するのはいつも評論のサークルとしてだが、今回の文フリではこのジャンルでの参加は少なく、会場では小説・詩歌などの創作系のサークルとは別の部屋があてられていた。入場時にそのことを知り、こちらまでお客さんが流れて来るのかちょっと気がかりではあった。もちろんそれは杞憂に終わった。
出店中には、拙著『タモリと戦後ニッポン』を読まれた人が、ブースにいる私がその著者だということに気づいて、励ましの言葉をかけてくださったり握手を求めて来たりと、得がたい体験もした。福岡の人たちは温かいなとあらためて実感した。この場を借りて御礼を申し上げたい。
なお、今回の文フリ福岡参加に乗じて、ご当地アイドルのライブを見に行ったり、屋台で飲んだりと久々に旅行を満喫した。
今月23日(月・祝)には東京流通センターで第21回文学フリマ東京が開催される。そして冒頭に書いたとおり、来年も各地での開催が予定されている(詳細は公式サイトを参照)。私としてもできるかぎり、新規開催地も含め今後もこのイベントを追いかけていきたい。
(近藤正高)




























