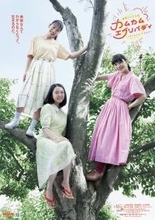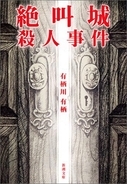本題に入る前に、まずは失礼して個人的な昔話をするのをお許しいただきたい。

有栖川有栖と鉄道趣味
はるか昔。全日本大学ミステリ連合(というものがあるのです)の大会ゲストを有栖川有栖さんにお願いしたことがある。会場は千葉・房総半島の外房線沿いのどこかであった。約束の時間、私は幹事の学生とJRの駅に行き、有栖川さんを待った。有栖川さんは関西から来られる。きっと東京駅から外房線に乗られるに違いない。したがって外房線の下り電車に乗ってこられるはずだ。しかし、目当ての電車に有栖川さんの姿はなかった。
おかしい。まさかと思うが乗り遅れられたのか。
さらに待ち続けることしばし。「やあ、お待たせしました」と言いながら有栖川さんが現れた。駅の時刻表を見ると、まさに今上りの電車が着いたばかりである。
ああ、噂には聞いていたが有栖川さん本当に鉄道ファンなんだ、と思った瞬間である。
「准教授の身代金」の原作は「助教授の身代金」(『モロッコ水晶の謎』所収)である。題名が異なるのは原作が発表された2004年から現在までの間に大学職員の職制が改正されたからだ。それはともかく題名から「えっ、火村が誘拐されちゃうの?」と思った方は多かったのではないかと思う。これについては作者自身が「あとがき」に書いている。
──「助教授の身代金」は、発表してから「この題名は、あざとかったかな」と思った。火村英生が誘拐される物語か、と誤解されるのを期待しているかのようで、別にそういうわけではなくて、この題名がふと頭に浮かんで、〈助教授〉を他の言葉に変えようとしたら、何故か思いつかなかった、というだけである。
冒頭で語られる誘拐事件が次第に変貌して、という複雑な構成を持った作品で、中途にオリジナルのおもしろい謎が呈示される。ぼかして書いてしまうと、誰かがやったかではなくて、どうやったかがわからない、というタイプの謎だ。その前段回として誘拐事件が描かれるのである。身代金を持った被害者の家族に、犯人がJRに乗るように支持する。
有栖川有栖と時刻表トリック
鉄道ミステリーといえば時刻表トリック、というのが往年は通り相場だった。それが現在では流行らなくなったのは、ひとえにネット検索で誰でも知能犯的な「乗り換え」を見つけてしまえるからだろう。鮎川哲也らの先人を尊敬する有栖川が鉄道ミステリーを書くことを考えなかったはずがないが、残念ながら現在ではこのジャンルは作家にとって困難なものになっている。「助教授の身代金」にも被疑者のアリバイを検討する場面はあるが、やはり添え物的な扱いだ。作家アリスシリーズで鉄道ミステリーといえばなんといっても『白い兎が逃げる』の表題作を読むべきだろう。書きにくい題材に正面切って取り組んだ意欲作だ。
その他ではノンシリーズの長篇だが『マジックミラー』もお薦めしたい。現在のミステリーで時刻表トリックを書くことの難しさを逆説的に示した内容といってもよく、ツイストの効いた形でこの題材を処理している。時刻表ではなくて地図を主題とした珍しいトラベルミステリーが作家アリスシリーズの『海のある奈良に死す』である。また、『赤い月、廃駅の上に』は、鉄道怪談という新しいジャンルを開拓した作品集だ。
日本の誘拐ミステリー
ドラマの話題に戻る。第3話では、原作だと中盤以降で明らかになる事実をまず読者にわからせてしまう、という大胆な改変が行われた。
誘拐事件の部分が前半の山となった。ここで使われる身代金受け渡しのトリックは、黒澤明監督の映画「天国と地獄」(1963年)で有名になったものだ。「天国と地獄」のタイトルはドラマ内でも出てくるが、原作にはさらにその元ネタについての言及がある。アメリカの作家エド・マクベインが1959年に発表した『キングの身代金』だ。この作品には身代金受け渡しトリック以外にもう一つのおもしろい趣向があった。犯人は富豪の子供と間違えてその使用人の子供を誘拐してしまう。にもかかわらず、同じように身代金を要求してくるのである。支払いを拒否して子供が殺されれば、富豪の社会的名声は失墜する。それがいやなら金を出せ、ということだ。
日本作家の書いた誘拐ミステリーとしては、ユーモアミステリーとしても大傑作の天藤真『大誘拐』、私立探偵が事件に直面する原りょう(本来はオリジナルの作字)『私の殺した少女』などが有名で、乱歩賞作家の岡嶋二人も「人さらいの岡嶋」と言われたほど誘拐ミステリーを量産している。謎解き小説の興趣と誘拐ミステリーのサスペンスを融合させた法月綸太郎『一の悲劇』も未読の方にはぜひお薦めしたい作品である。
テクノロジーとミステリー
原作「助教授の身代金」はもう一つ、最新の技術情報を謎解き小説はどこまで吸収していけるか、という小さいけれども大事な課題が実践された作品である。有栖川はこのことに敏感な作家で、近刊に収録された短篇でもグーグルアースやNシステムなど、ネットワーク社会ならではのギミックに挑戦し、そこから逃げない姿勢を示した。科学捜査技術が進展し、情報収集のシステムが高度化していくと、人間の頭脳など必要としないほどに犯人検挙の効率は挙がるかもしれない。探偵の存在意義が脅かされそうな時代であり、それにどうやって適応していくかは、作家にとっての重要事となる。少なくとも有栖川有栖は、逃げないと表明しているように見えるのだが、「助教授の身代金」はそうした姿勢を早期の段階で示した作品でもあった。それがこうしてドラマ化されたというのが感慨深い。
ドラマのほうは今回、火村とアリス以外のキャラクターの出番が少なめだった。ただしシャングリラ十字軍を率いる諸星沙奈江と火村が初めて対面を果たすなど、動き始めた部分もある。第4回の原作は、初めて長篇が使われる。
(杉江松恋)