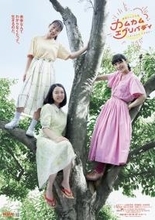花山のモデルが昭和を代表する編集者でデザイナーの花森安治であることは、もうみなさんご存知だろう。

花森はのちに、《暮しの手帖》に書いたシリアスな文章を『一戔五厘の旗』(暮しの手帖社)にまとめ、これで1972年に読売文学賞(随筆・紀行部門)を受賞した。

しかしいっぽうで花森には、とくに1950年代には、《暮しの手帖》以外の雑誌に、もっとふざけた文章をいっぱい書いていた。
そのなかから今回は、『暮しの眼鏡』(1953)に収録された「サラリィガール十戒」をご紹介したい。

これは第2次世界大戦後、男女同権が強く言われた時代の、非常にアイロニカルな文章である。
サラリィガールは働くなかれ
「サラリィガール十戒」は、〈まことに我汝らに告げん〉という文語訳『聖書』のパロディで始まる。

第1戒。〈サラリィガール〉は職場の花である。雇い主も、同僚の男性社員も、みなそう思っている。
花なら花らしく、意味なくにこにこ笑い、綺麗に化粧して歩き回り、ばかばかしいことを可愛らしくしゃべること。
働いてはいけない。
〈人並に一生けんめい勉強して、男と同じように働こうなどと思えば、かならず、女史とかオバサンとか言われ、やがて言うに言われぬ悲しい目に〉会うだろう。
ふざけている。
しかしそのあとを読んでみよう。
〈つとめて見られて美しく、チョン切られてイタイと言わず、いつまで咲いていようなどと思わぬのが上分別、家へ帰れば、よい娘とほめられ、外へ出れば、よい子だともてはやされる、それでゼニがもらえるというのだから、幸せなるカナ。
そんな暮し方をケイベツする僕みたいな者の言うことなど、決して気にしてはならぬのである〉
(改行・太字強調は引用者の責任でおこなった)
花森は、「職場の花」という生きかたを軽蔑していたのだ。
花森に軽蔑されたくなかったら、「男が期待する女性社員像」を演じることなどせず、女史とかオバサンとか言われることも辞さず、人並に一生けんめい勉強して、男と同じように働く必要があるというわけ。
サラリィガールは社畜になるなかれ
花森は、〈サラリィマン〉とは鵜飼の鵜のようなものだという。
朝決まった時間にたたき起こされ、飯もゆっくり食えぬまま職場に駆け込み、しじゅう上司の顔色を伺い、同僚の声をさぐり、給料もらって家に帰れば袋ごと吐き出させられて、また翌朝たたき起こされる。
水に潜らせられて、魚を咥えてきては、綱を引かれて魚を吐き出させられ、そしたらまた水に戻されて魚を追うことを強要される鵜となにが違うのかと。
当時は社畜という言葉がなかった。この語を考案した安土敏(のちのサミット社長)が作家デビューしたのは1980年代のことだ。
第2戒。〈サラリィガール〉はこのような暮しをしてはならない、と花森は言う。
せめて食費ぐらい入れてくれると助かるんだけど、と親に言われたら、児童福祉法を盾にして断れ。
男の同僚が、男女同賃金の新憲法に反対し、男と女の賃金に差をつけなければならない、などと言っていたら、憲法改正してもいいんですか(=日本がまた戦争できる国になってもいいんですか)と訊け、という。
男性社員の身なりがみすぼらしかったとしても、同情してお茶を奢ったりするな。できるだけ高いものを奢らせろ。男が男女同権を言い出したら、笑って軽くいなせ、とまで書いている。かなり乱暴だなー。
黙るなかれ、がんばるなかれ、GHQに与するなかれ
第3戒。〈サラリィガール〉の口は、口紅を塗るため、ものを食うため、しゃべるためにある。黙ってはならない。
職場では仕事以外の、ファッションやメイクのこと、映画のことなどをあれこれしゃべり、電話を使ってよその職場の同志ととしゃべり、電車では同僚上司の悪口を叫びたて、乗り合わせた人に仕事熱心をアピールしろ、という。
第4戒。仕事で意地を張ってがんばるなかれ。
同僚の男を見ろ。
そうまでしてやった上で、上司にはこんなんじゃダメだと言われ、ボロボロになって家に帰れば、帰りが遅いと妻に怒鳴られる。あほである。
〈サラリィガール〉は、面倒な仕事を持ち込まれたら、男子社員のように「承知しました」なんて言ってはならない。
できるかしら、だってできないわあたし、と言うべし。
それで済まなければ、いい加減にやれ。
時間までに終わらなければ、さっさと引き上げよ。
それで仕事の出来のにケチをつけられたら、「だからできないって言ったでしょ」と言ってのけろ、というのだ。これもずいぶん乱暴な話だ。
第5戒。GHQ(〈ゴー・ホーム・クイック〉)に与するなかれ。
シゴトが終わったからと言って、急いで家に帰るなかれ。
退社時間には1秒たりとも遅れるな。そして家に帰ることを考えるな。
アフターファイブは銀ブラを決め、ウィンドウショッピングや映画鑑賞に時間を使い、〈若き日を使い果たすべし〉。
いまなら炎上必至だけど
こうやって見てくると、いまならフェミニストと反フェミニストの両方から怒りを買い、炎上すること間違いなしの戯文だ。
このような、冗談とはいえ極端な文章を花森が書いたのは、ほんの10年足らず前の軍国主義下の総力戦体制にたいする嫌悪感と、自分自身がかつて大政翼賛会で国策協力標語の策定にかかわっていたことについての自責の念があったのかもしれない。
戦争が終わっても、総力戦体制自体は終わらなかった。日本人は戦時下の総力戦体制を戦後も続けて、驚異的な経済復興を成し遂げた。現在のブラック企業やブラックバイト、出生率の低下は、こういった「総力戦体質」が産み出したといっても過言ではない。
そうやって考えると、いまとなっては男女問わずすべての働く人が、この文章を読んでもいいように思える。もちろん、問題の多い文章だから、どういう感想を抱くかはみなさんの自由。だって戯文だもの、顰蹙は買ってナンボでしょう。
文章の〆はこうなっている。
〈以上五戒、すべて僕の誤解ならば、幸いなり。五戒とゴカイ、合わせて十戒まことに汝らに告げん、ざまァみろ〉
ふざけんな!
(千野帽子)
参考/「とと姉ちゃん」唐沢寿明演じる編集長創刊の「暮しの手帖」全巻展示中、手にとって読めます