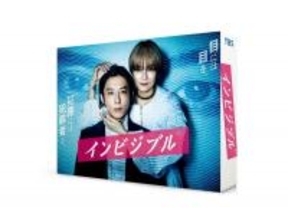今回のドラマには原作から変更されたところも多々あった。
原作との違いは、その後、両者が和解にいたった時期だ。原作では、できあがった『解体新書』が玄白から直接良沢に渡され、そこで和解する。これに対し、今回のドラマでは、『解体新書』が世に出たあとも、良沢と玄白はわだかまりをずっとひきずり続ける。それがようやく溶けたのは、それから18年もあと、玄白の還暦とともに良沢の古希を弟子たちが祝う会においてだった。そのシーンは、それまでに経た歳月の分だけ重みを感じさせるものであった。
キャラの立った人物が続々と登場
原作との違いは、良沢の家族の描き方などにも読み取れた。ドラマでは、原作のなかで頻繁に登場していた次女の峰子(岸井ゆきの)ばかりでなく、長女の富士子(中島亜梨沙)、妻のたま子(たまの正しい字は「王」に「民」。長野里美)にも物語上、重要な役割が与えられていた。このうち富士子は若くして亡くなるが、その日も良沢は玄白たちと翻訳作業に打ち込み、一晩だけでも富士子のそばにいてほしいという妻の申し入れも聞こうとしない。翻訳を完成させることこそ、亡くした娘への何よりの手向けという良沢の思いがより伝わってくる脚色だった。その後、良沢が玄白と和解するにあたっても、たま子は病床にあって夫を後押しする大切な役を担うことになる。
良沢の家族以外にも、登場する人物にはそれぞれ三谷幸喜なりの解釈でキャラクターが明確に設定されていた。たとえば、桂川甫周(迫田孝也)は、幕府奥医師・桂川甫三(中原丈雄)の息子であることから、ボンボンらしいのんきな性格が強調された。甫周は玄白に連れられて翻訳作業に参加したものの、当初は、原本となる『ターヘル・アナトミア』に載った女性の裸体像を興奮して眺めるばかりで、まるで役に立たない……と思いきや、そのスケベ心が意外な発想をもたらし、作業に貢献することになる。
このほか、同時代を生きた高山彦九郎(高嶋政伸)や林子平(高木渉)、それから平賀源内(山本耕史)といった人たちも、時間の都合もあり、原作とくらべるとさすがに出番は少なかったが、それぞれに見せ場が与えられる。とりわけ源内は、さまざまな分野で才能を発揮し、誰よりも時代の先を行きながらも、目標に向かってひたすらに邁進する良沢や玄白を内心うらやましく思っていたりと、良沢たちとは対照的に描かれていた。
良沢と玄白、その性格の違いが『解体新書』を生んだ
準主役である杉田玄白にしても、前野良沢との性格の違いが原作以上に際立っていたように思う。ドラマにおける玄白は、『解体新書』を世に出すため、ときに手を汚すこともいとわない。初めての腑分け(解剖)では、刑場の役人に袖の下を渡していたし、幕府老中・田沼意次(草刈正雄)に『解体新書』の出版を認めてもらうため、パイロット版にあたる『解体約図』を進呈、その下にこっそりと小判を忍ばせる。これに気づいた意次の反応がまた、よく言われる強欲な金権主義者とも、かといって清廉ともいえない、彼の割り切れない人物像をよく表していた。
ともあれ、頑固な完璧主義者である良沢と、どこかちゃらんぽらんながら社交家で人脈豊富な玄白(そもそも翻訳グループに幕府奥医師の息子を入れたのも、玄白の政治的な思惑からであった)と、今回のドラマではそのキャラクターの違いをより際立たせることで、両者のうちどちらが欠けても『解体新書』が世に出ることはなかったのだと、つくづく感じさせた。
なお、良沢や玄白らが『ターヘル・アナトミア』を翻訳するきっかけとなった、刑場での腑分けに立ち会うシーンでは、役人の新蔵と執刀にあたった老人・国松に、それぞれ三谷作品の常連である近藤芳正と小林隆が扮した(小林隆は特殊メイクでほとんど素顔がわからなくなっていたが)。さらに原作者のみなもと太郎も、平賀源内から戯作を受け取りに来た編集者・覚三の役で登場していた。
三谷幸喜の「原点」に捧げられたオマージュも?
今回のドラマでは、『ターヘル・アナトミア』で鼻の説明文にあった単語「フルヘッヘンド」をめぐる有名なエピソード(ただし原作の『風雲児たち』ではとりあげられていない)について、そもそもこの語は同書には出てこず、現在では完全な創作と考えられているということも紹介されていた。
とはいえ、このドラマは大河ドラマではなく、よって時代考証はおおざっぱであると、冒頭のナレーション(有働由美子アナウンサーによる)であらかじめ告知されていた。映像に関しても、登場人物たちが、文章とともにマンガのコマ風に紹介されたり、杉田玄白の『蘭学事始』の文章がそのまま引用されたりするなど、大河ドラマとはひと味違う工夫があちこちで見られた。
そこで思い出したのが、いまから約45年前に同じくNHKで放送された連続時代劇「天下御免」(1971~72年)だ。「風雲児たち」にも出てきた平賀源内を主人公に据えたこのドラマは、必ずしも時代考証に忠実ではなく、ときには現代の街を源内たちが歩いたり、コマーシャルソングの歌詞を採り入れるなど遊んでみたりと、かなり冒険した作品だったという。《「天下御免」の素晴らしさは、時代考証などドラマ作りの根幹をなす部分はキッチリと守りながら、これをベースに現代を江戸の風俗に置きかえる工夫を重ね、許される範囲の、言い換えれば、あっても不思議のない一定のリアリティをもったアイディアを採用していること》だと評したのは、フジテレビで「鬼平犯科帳」などのヒット作を生んだ時代劇プロデューサー・能村庸一である(能村庸一『実録テレビ時代劇史』ちくま文庫)。
この評は、みなもと太郎の『風雲児たち』、そして三谷幸喜の時代劇作品にもそのまま当てはまりそうだ。それも当然で、三谷は少年時代に「天下御免」を夢中で観ていたのだから。かつて彼は《『天下御免』は僕の原点。早坂暁さんが書かれたシナリオ集はバイブルです。/いつか僕もあんなドラマが書きたい!NHKで書きたい!》とも語っていた(NHKアーカイブスHP「あの人のとっておきセレクション」)。
早坂暁は「天下御免」のメインライターとして、当初、橋田壽賀子と佐々木守とともに参加したが、ほかの二人は早々に離脱、結局は彼だけで大半の回の脚本を手がけることになったらしい。早坂はその後「夢千代日記」「花へんろ」などの名作ドラマを生み、昨年12月16日に88歳で死去した。
平賀源内については、みなもと太郎の『風雲児たち』からドラマではとりあげきれなかったエピソードも多々ある。いずれスピンオフというか、源内はじめほかの風雲児たちを主人公に据えた続編も観たくなった。連続ドラマとまではいかなくても、年に1~2回、ドラマ化するということはできないものでしょうかねえ。
(近藤正高)