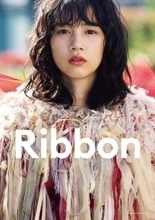1989年、宮崎駿監督の劇場アニメーション作品。

『魔女の宅急便』は、ジブリ作品としては特殊だ。
この作品は、宮崎駿が監督をやる予定ではなかった。
宮崎駿の発案でもない。
外部からの持ち込み企画なのだ。
タイトルに「宅急便」とついておりクロネコが登場する。
わかりやすいほどのタイアップだ。
制作が、徳間出版+ヤマト運輸+日本テレビ放送網の異業種企業間の大合同プロジェクトなのである。(映画、企業、テレビ局のタイアップは、このころからスタートした)
宮崎駿監督自身もこう語っている。
「しばらく休みたいと思って『魔女の宅急便』をやって。これは休むために若いスタッフを立ててやってもらうはずの作品だったんですよ」
もちろん、宮崎駿監のことである。
若いスタッフを立てて作るというもくろみは頓挫する。
『ジブリの教科書5 魔女の宅急便』によるとこういう経緯だったらしい。
宮崎駿がプロデューサーで、監督は若手でやるという方向で進んでいた。
シナリオも外部に頼んで書いたもらった。
だが、宮崎監督はシナリオを評価しつつも納得できない。
そこで宮崎自身がシナリオを手がけることになる。
だが、できたシナリオがまた大変なものだった。
若手監督でやる80分ていどの小品が想定されていたのに、その規模を超えていた。
飛行船からトンボを救出するスペクタクルシーンもあり、80分ではおさまらない規模なのだ。
若手監督がやるには荷が重すぎる。
しかも、宮崎駿色が濃い。
というわけで、当初のもくろみは崩れ、宮崎駿監督本人が監督することになった。
テーマも「自分探し」だとアピールされ、八十年代のマーケティングのにおいがプンプンする。
だが、作品がそういったマーケティング的な予定調和を大きく超えているのは、観た人には説明する必要もないだろう。
『月刊アニメージュ』で、まだ作画インして一ヶ月ぐらいの時点で、監督はインタビューにこう答えている。
「自分の才能は自分ではわからないですよ。ぼくはこの年になってもわからない(笑)。その人の才能てのは、他人とのかかわりのなかで生まれてくるものだと思う。それは、この映画の内容にもかかわることですね。ただ今の時代は、才能が一種の商品価値と考えられているでしょう」
だから、単純なハッピーエンドの物語ではない。
これから先も、落ち込むだろう。そして、また元気を取り戻すだろう。
そう思うことで勇気づけられる。(米光一成)