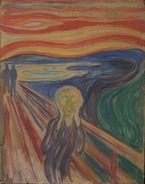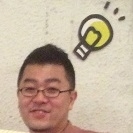VRの避難体験はコンパクトさが長所
画期的な「避難体験VR」を開発したのは、新宿に本社がある「理経」。昨年創業60周年を迎えた歴史あるITソリューションベンダーで、近年では「Jアラート」受信機などを自治体へ納めています。

その縁から各自治体の担当者と話す機会が多く、「避難訓練の参加人数が伸び悩んでおり、特に若者が少ない」という悩みを耳にしていたとのこと。そして2年前にVRと組み合わせた「避難体験VR」を開発しました。
時代の技術とニーズとが見事にマッチして、今年度は既に約50回も避難訓練で活用されそうです。1回で100人程が体験できるので、のべ5000人以上がこのVRで避難訓練をした計算に。
そして従来はパソコン版だったものが、このほどスマホアプリによるモバイル版も完成。これにより持ち運びや設置が簡素化され、電源やネットワーク環境の心配もなくなり、より多くの人が体験できるようになるそうです。

では、さっそく装着してみましょう。必要な機材はスマートフォン・VRヘッドセットのみです。


今回は特別に、見ている画像を別途モニターに表示してもらいした。そもそも筆者はVR初体験でしたが、首を動かすたびに視界が変わるので、違和感なくこの空間の中へと入りこめました。
VRで火災から避難してみた
さあ、いざ体験です。目的は燃えさかるオフィスビルから、2分以内に脱出すること。

今回、事前に教えてもらったのは「火災避難では煙がネック」ということ。従来の避難訓練では発煙筒での白い煙がよく使われますが、実際の火災での煙は黒く全く視界が開けないそうです。


しゃがむともちろんVR内の視界も変わります。煙が少ないので、視界が開けてきました。

火災によりさまざまなものが崩れ、破片が散らかっているのがリアルですね。暗い廊下を進むと、炎に遭遇。

この時には、完全に世界に入りまくっていたので、思わずビビる……! VRとは分かっているのに、ついつい慎重になります。

同製品は、企業からも社員向け避難訓練としてのニーズが多いそうです。マップをその企業ビルにするというカスタマイズも可能ですが、地図が頭に入っていると逆に避難訓練には向かないこともあるのだとか。
また、外出先で火災に遭遇した際、避難経路を知らないビルにおいて、どのように対処するのが大事かを体感してほしいそうです。

暗く煙が充満する火災現場では、どこに向かっていいか分かりません。そうなると頼りになるのは非常灯。
ただ残念ながらここでタイムオーバー。ABC三段階でCという結果でした。ちなみに、A判定は全体の5%弱ということから、いざという時の的確な行動がいかに難しいかがわかります。
VRで「避難訓練」を啓蒙したい
そして同じ機材で「VR消火体験シミュレータ」もできます。こちらは理経とMXモバイリングが連携したもの。今回はコントローラーと実際の消火器を合わせて持つことで、安全栓を引き抜く、ホースを火元に向けるといった、より実際の消火に近い動作ができるものにしてみました。

消火訓練として実際に消火器を噴射して火を消すとなると、準備や体験に時間がかかり体験できる人数が限られてしまいます。さらに後始末も大変……。一方VRであれば、何人でも何回でも消火活動を体験できます。もちろん、周りが汚れる心配もありません。

こちらは一応合格点でホッ。

石川さん
「VRを活用することで、火災の煙などを再現したリアリティのある災害現場が体験できるようになります。さらに、この『避難体験VR』の前後で火災避難に関するレクチャーを行うことで、VR体験の学びがより印象強く残ります」
確かに。筆者が過去に体験した避難訓練は、前の人の背中についていくだけでした。
石川さん
「災害時には、自分で判断をすることが大事です。『避難体験VR』では、火災時にエレベーターは使わない、など自分で考えて行動する場面があります」
自分の動きにより視界が変わるVRならではですね。頭では分かっていても、実際に行動できるかは確かに違っていました。
最後に今後の予定などあれば、教えてください。
石川さん
「多くの自治体や企業が、防災訓練の参加率低迷に頭を悩ませているとお伺いします。それだけ日常の中で、災害を自分事として考える機会が少ないのが現状です。本VRの取り組みを通じて、日頃から防災について考え、防災を身近なものに感じる方が増えればと思っています。また今後に向けては、災害体験の質を高めるという意味で、触覚などの五感に連動したVR研究も進めております」
同社では他にも、超高層ビル街でドローンを使った情報収集のインフラ活用なども行っています。
「避難体験VR」製品ページ:https://www.rikei.co.jp/product/623/
(高柳優/イベニア)