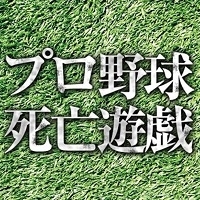インタビューは難しい。
例えば、たまにプロ野球選手のインタビュー取材へ行っても、自分の場合は毎日顔を合わせている記者の方々とは違って、基本的にお互い初対面。
人はシリアスな話をするときほど一定の時間が欲しくなる。以前務めていた会社では、勤務査定や給料交渉で上司、または社長との30分程度の面談が年に1度はあった。恐らく、スマダン読者もこの手の交渉の席が苦手な人も多いのではないだろうか?
正直、俺は苦手だった。ボスに対してあまり強気に出てもその後気まずくなるし、弱気になりすぎても舐められる。どっちに転がっても自己嫌悪。結果、少し揉めるといきなり「じゃあ辞めます」なんて自分でも驚きの結論出しがち。

球団にたびたび物申していた小宮山悟
その点、元プロ野球選手・小宮山悟の球団との交渉の姿勢は参考になる。書籍『最強チームは掛け算で作る』(KKベストセラーズ)の表紙では、満面の笑みにスーツできめる元ロッテのエース小宮山の姿。同書には、所々に球団関係者とやり合う様子が描写されているのだ。
89年ドラフト1位でロッテ入りも、90年代前半は黄金時代真っ只中の西武ライオンズに大きく負け越し、オフになるとフロントの人間に「ライオンズに勝ちたいから、あんなチームを作ってほしい」と訴えるも空回り。
もちろん個人事業主の野球選手と会社員は事情が違うが、それでもほとんどの選手はサラリーマンと同じくチーム内での衝突を恐れて(もしくは引退後の身の振り方を考えて)ここまでは口にしない。他にも同学年の西武のエース渡辺久信より、数字は劣るが同等の能力はあると考えていた小宮山は、なんと「自分の能力を証明したいので、試しにライオンズへトレードへ出してください」とか「ライオンズだったら、何勝できると思いますか」と球団フロントを困らせるガチンコ発言を繰り返す。
もちろん評価とは、お金のことだけではない。当時の球団フロントがプロ野球チームを持つだけで満足して、真剣にチームを強くしようとしないことに腹を立てたのである。そうして90年代チーム最大の功労者は99年に7勝を挙げながら、マリーンズから自由契約を通告されるわけだ。
妥協せず全うした現役生活
いや小宮山の交渉が参考になるって言い過ぎてクビになってるじゃねえか……なんて突っ込みは野暮だろう。重要なのはそこではない。注目すべきは、この男の“プロフェッショナルとしての姿勢”だ。
組織に対してだけでなく、小宮山はグラウンド上でも妥協しない。
こうして小宮山の哲学を見ていくと、一定の成功を収めた自信過剰な野球選手と勘違いされがちだが、自らの野球の才能は、天才や怪物と称された選手たちと比べると豊かなものではなく、乏しいと言った方がいいくらいだと語っている。
早稲田大学に入るために2年浪人、さらに30代後半にメジャーから帰ってきた翌年も所属が決まらず1年浪人。恩師バレンタイン監督との出会いに感謝し、38歳でロッテに戻ると44歳まで現役生活を続けた。通算117勝の内、04年からのマリーンズ復帰後にあげた白星は10勝だけ。晩年はローテを外れ、中継ぎとして時に敗戦処理のような場面でも黙々と仕事をした。
元エースのプライドなんかどうでもいい。ただ試合で投げたかったから。
自分の主張を臆することなく組織にぶつけ、ひとつの会社(球団)に依存することなく日米を渡り歩き、どんな環境に置かれようが、周囲からどう思われようが現役生活を全うする。
【プロ野球から学ぶ社会人に役立つ教え】
仕事でミスっても自分を正当化して、すく他人のせいにしないこと。
(死亡遊戯)