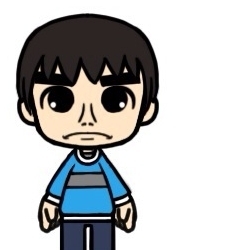その席上で盛り上がったのが「一体、自分は○発屋なのか」という検証だった。ダンディ坂野をちょうど1発としたら、小島よしおは2発はあるのではないか。じゃぁ俺は0.8発くらい? あいつは1.2発じゃない? そのとき、髭男爵の山田ルイ53世は、こんな都市伝説を想像したという。
「数字を全部足したら“8.6”になるんじゃ……」
山田ルイ53世『一発屋芸人列伝』(新潮社)は、世間から「消えた」と言われる一発屋芸人たちに、自らも「一発屋」を名乗る著者がインタビューしたノンフィクション。
「雑誌ジャーナリズム賞」を受賞した本作は、一発屋たちの「自虐エピソード集」や「瞬間最大風速エピソード集」ではない。徹底しているのは、彼らの面白さを解き明かす姿勢と、いまも芸に生きる姿を伝えること。帯に添えられた一文は「それでも、人生は続く」だ。

同業者による「舞台袖」からの目線
『一発屋芸人列伝』では、一発屋芸人たちが「一発を当てるまで」と「一発を終えてから」に焦点をあてる。ポッと出のように見える一発屋芸人にも、もちろん紆余曲折がある。そして売れたことには理由がある。
レイザーラモンHGが「ハードゲイ」キャラを思いつき、実際にブレイクするまでには実に5年の月日がかかった。
「ここまでして練り込まれたキャラクターは、重厚さ、つまり面白さの桁が違う」と山田ルイ53世は言う。舞台袖から見た「面白さ」「技術の高さ」の分析は、やはり説得力が違う。
たとえば、ジョイマンの脱力系ラップは「誰にでも真似できる代物ではない」と断言する。「ありがとう、オリゴ糖」「二三本、イビョンホン」など、脈略のない言葉を2つ並べ、韻を踏み、かつ笑いを取るのはとても難しい。2つの言葉に少しでも意味が生じれば、ただのダジャレになってしまうからだ。
また、コウメ太夫については「調律されていないピアノ」「全てが的外れ」と表現。ネタは浅いし、取材時のエピソードトークもグダグダ。ただ、裏を返せば「必ず的を“外せる”」ということ。「コウメ太夫で笑ったら即引退スペシャル」(TBS『テベ・コンヒーロ』2012年)では、その徹底した「できなさ」が爆笑を生み、イジられる存在へと変わった。
他にも、ハローケイスケの「アンケートネタ」のスマートさ、とにかく明るい安村の「全裸ポーズ」の構成の妙、キンタローのモノマネの精度など、各章に芸へのリスペクトがある。「消えた」ことが話題になる一発屋だが、彼らは現れるべくして「現れた」ことを教えてくれる。
大ブレイクという山の頂に一気に運ばれ……
「消えた」「死んだ」と揶揄される一発屋だが、もちろん実際に消滅などしていない。一発屋の「一発」は一夜の花火。夜が明け、日が昇り、人生は続く。
今では年間180本の営業をこなすというテツandトモ。地方のお祭りや企業パーティーに呼ばれると、必ず主催者に「あるあるネタ」の取材をするという。以前はネットで調べた情報でネタを用意したが、情報が古いこともあり、現地取材で裏を取るようになった。地産地消の「地元あるある」「職場あるある」は評判を呼び、リピート率も高い。
「右から左に受け流すの歌」がブレイクしたムーディ勝山は、ひょんなきっかけで中型免許を取り「ムーディがロケバスの運転手に!」とニュースになった。それを知った「エロ詩吟」の天津・木村は後を追い、業務運転に必要な二種免許を取得して、本当にロケバスの会社に就職してしまう。次のステップへの執念が生んだ「バスジャック事件」である。
未だくすぶり続けている者もいる。「ギター侍」波田陽区は、2016年に妻子を伴って活動の拠点を福岡に移した。しかし取材では言葉の端々にプロ意識の欠如が見られ、「東京には無い仕事が福岡にはある」と脇の甘さも目立つ。福岡を舐めるな! と反発されないか心配になるが、若手と一緒にライブに出ると客席投票で2ヶ月連続最下位に。いい感じで後輩に舐められるようになった。
まさに「残念」を体現する波田。もがき続けるが結果はついてこない。山田ルイ53世は波田を「大ブレイクという山の頂にヘリコプターで一気に運ばれ、未だに斜面をスベり続けるスキーヤー」と例える。その視点は優しい。
《しかし、裏を返せば、それは彼の到達した山が如何に高かったか……ということではないだろうか。10年以上立派に飯を食い、妻子を養っている。もはや“負け”は波田の生業……彼は勝ち組なのだ》
「一発屋」という永久ライセンス
本書によれば、近ごろ一発屋の定義は変わりつつあるという。
《「しぶどく生き残っている人達」「久しぶりに見たら面白いネタ特集」等々、一発屋に対するメディアの切り口、光の当て方も変わりつつある。売れっ子当時の最高月収を発表するだけでない、“生きた”一発屋の姿が、お茶の間に届く機会が増えた》
一発屋として生き続ける芸人が増え、一発屋自体の「層」が厚くなってきたのもあるかもしれない。もはや「一発屋」は不名誉な烙印ではなく、栄光と引き換えに手に入れた永久ライセンス。レースはまだまだ続く。手持ちのカードは多ければ多いほどいい。だがそのライセンスは、誰にでも配られるものではない。本書がそれを証明している。
今年も、うっかりそのライセンスを手にする者が出るかもしれない。そのたびに、一発会は「ルネッサ〜ンス」で乾杯するだろう。フランス語のルネッサンス(Renaissance)には「再生」「復活」という意味があるのだから。
(井上マサキ)