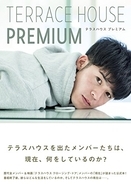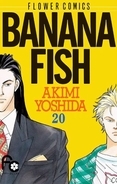プロレスを観つつ、無意識にロックの扉を開けている。思春期にプロレスを触れた男の子であれば、誰しも身に覚えのある経験だと思う。プロレスとロックは、ジャンルとして親和性の高い関係にある。
蝶野を”黒いカリスマ”へ変身させた新テーマ曲
「YOUNG GUITAR」7月号(シンコーミュージック・エンターテインメント)の表紙を見ていただきたい。三鷹の暴走族でありサッカー少年だった蝶野正洋が、フライングVを抱えポーズしている。

同誌が今回組んだ企画は、名付けて「プロレス・スーパーギター列伝」。端的に言えば、プロレステーマ曲特集だ。
テーマ曲のことはひとまず置き、蝶野のレスラー人生を振り返りたい。88年に有明コロシアムで初見参した闘魂三銃士。グレート・ムタの大ブレイクを経て凱旋帰国した武藤敬司、猪木イズムを体現する“強さ”を押し出す橋本真也に比べ、蝶野は遅れを取っていた。G-1クライマックスで3度の優勝を果たしても、名脇役のポジションを脱することができず。
ジレンマに陥った蝶野は、選手会長の役職を離れヒール転向を果たした。コスチュームは白から黒へチェンジ。
「ここで足踏みをしていてもしょうがないということで、一度は会社にダメ出しされたけど、フライングでイメージ・チェンジしたんですよ」
「ロイヤル・ハントのアルバムを聴いて、その中から俺が2曲くらい気に入ったものを見つけていて……、あの曲(「Martial Arts」)は3番手くらいだったかな。確かカミさんが『これがいい』って決めたはず(笑)。俺が決めていたら失敗していただろうな(笑)」(蝶野)
94年秋以降、Royal Huntの1st『Land of Broken Hearts』収録のインストゥルメンタル「Martial Arts」が蝶野の入場テーマ「CRASH~戦慄~」として定着した。

武闘派のイメージを具現化するこの曲はファンのハートを鼓舞し、蝶野正洋ブレイクの大きな要因となる。彼の新テーマ曲を初めて耳にした時、熱い胸さわぎがしたことを筆者ははっきりと覚えている。
長州のブレイクと共に名曲に変貌した「パワーホール」
音楽がブレイクの一助になるケースがあれば、本人のブレイクがテーマ曲に輝きを与える場合もある。その最たる例は、長州力の入場テーマ「パワーホール」だろう。

実はこの曲、82年10月の“噛ませ犬発言”以前から使用されていた。押しも押されぬ中堅選手・長州のテーマ曲がテレビの電波に乗ることは、当然ながら稀だった。しかし82年以降、状況は一変する。“革命戦士”として脚光を浴びた長州を後押しするパワーホールの旋律は、見事に革命のリズムを刻んでいたのだ。ちなみに作曲者にクレジットされる「異母犯抄」とは、P-MODEL平沢進のペンネームである。
のちに長州は新日本プロレスを離脱、ジャパンプロレスのリーダーとして全日本プロレスに参戦した。この時、異分子との邂逅で火が点いたのが天龍源一郎だ。彼のテーマ曲は、言わずとしれた「サンダー・ストーム」。ギタリスト・高中正義の2枚組アルバム『虹伝説 THE RAINBOW GOBLINS』に収録される一曲である。

サンダー・ストームが天龍のテーマ曲として初お目見えしたのは、1982年2月4日のミル・マスカラス戦。当時は“第3の男”としてジャンボ鶴田の後塵を拝す天龍だったが、全日の中心に立つにしたがい曲も輝きを増していく。決定打は、長州新日Uターン後の1987年。「全日マットを元のぬるま湯に戻すわけにはいかない!」と、天龍は阿修羅原と2人でレボリューションを始動する。同時に、サンダー・ストームは“風雲昇り龍”の反骨精神を象徴する名曲へと昇華した。
実は、天龍の入場テーマに関して一つ裏話がある。以下は、『1000のプロレスレコードを持つ男 清野茂樹のプロレス音楽館』(立東舎)掲載の情報だ。
『全日本プロレス中継』は天龍を売り出すため、視聴者からテーマ曲を募集する。
新日への敵意むきだしで用意された「サンライズ」
というわけで、ハンセンの入場テーマ「サンライズ」について。大前提として、日テレスタッフのセンスは図抜けている。音楽ファンとして、同局の選ぶ入場テーマに琴線がくすぐられるのだ。
ハンセンが新日から全日へ移籍したのは、81年より両団体の間で勃発した“引き抜き戦争”の最中。仕掛けたのはアブドーラ・ザ・ブッチャーに食指を伸ばした新日本プロレスだったが、全日がハンセンを抜き返したことで新日は大ダメージを負うことになる。
仕掛けてきた新日には日テレも怒りを抱えており、『全日本プロレス中継』ディレクター・梅垣進は「ハンセンについては新日本プロレスのイメージを絶対に変えてやろうと思った」とテーマ曲でも対抗意識を燃やしていたそうだ。
新日時代のハンセンのテーマ曲は、ガトー・バルビエリの「リベンジャー」やバッド・ボーイズの「ウエスタン・ラリアート」など名曲揃い。でも、負けるわけにはいかない。そこで日テレが編み出したのは、曲を混ぜ合わせる“マッシュアップ”という手法である。
カントリー歌手のケニー・ロジャースの「君に夢中」のウエスタン風のイントロと、日本のロックバンドであるスペクトラムの「サンライズ」を繋げ、繋ぎ部分にはスペクトラムの「モーション」を挿入。
全てがワクワクさせるエピソードなのだが、一方、今回の特集ではこんなガックリ話も紹介されている。
「ハンセン自身はテーマ曲に全く無頓着で、馬の鳴き声しか認識しておらず『馬が鳴いたら俺の出番だ』くらいにしか思っていなかったようである」

謎の多い全日版「移民の歌」
テーマ曲について語ると、筆者はどうしても全日寄りになってしまう。お許しいただきたい。続けて、ブルーザー・ブロディの入場テーマを取り上げたいのだ。彼は全日と新日の両団体へ上がった選手だが、私が論じたいのは全日時代の方である。
ブロディの入場テーマは、レッド・ツェッペリンの名曲「移民の歌」。新日時代は『LED ZEPPELIN III』収録のオリジナルバージョンが使われていた。

一方、全日はまたしても奇異なセンスを見せる。超獣といえば、多くのファンは全日版「移民の歌」をイメージするはず。ここからは『1000のプロレスレコードを持つ男』掲載の文章を引用しよう。
「アフリカの祭りを思わせるコンガ、ゾウの叫びのようなトロンボーンなど、全日本プロレス版の『移民の歌』は、“キングコング感”たっぷりで、まるでブロディのために作られたかと錯覚するほど似合っていた。
さて、このカバーバージョンだが、何の作品に収録されているのだろう。98年発売のムック『悶絶! プロレス秘宝館vol.2』(シンコー・ミュージック)に、その答えが記されていた。
「公式発表ではLPのロックメッセンジャーズ演奏によるものだということになっていた。だが、そういうバンドは存在しなかった。これは企画レコード制作にあたって適当につけた名前であり、実際には昭和46年発売のLPに収録されたものがオリジナル。これをきっかけに弱小レコード会社であったユニオンの様々なコンピレーション・アルバムにアーティスト名を変化させながら収録。実に9枚もの盤が出ているが、どの盤も入手は難しい」
「この曲のドラムは石松元というドラマーが担当。元々はジャズ系のスタジオ・ミュージシャンたちが集まって作られた企画物レコードであったようだ。この曲を発見したテーマ曲担当者には本当に心の底からリスペクトしたい」
三沢のテーマ曲が定着する前に使用された佐野元春
最後に取り上げたいのは、三沢光晴の入場テーマ「スパルタンX」である。

三沢がタイガーマスクの覆面を脱いだのは、90年5月14日。解説者を務めるグレート・カブキが「おい、何してんの。何してんの!?」と素のテンションで声を上げる中、被っていたマスクを客席へ投げた三沢。
この試合までは寺内タケシとブルージーンズの「タイガーマスクのテーマ」を使用していたが、素顔の三沢には新しい曲を用意しなければならない。暫定的に選ばれたのは、佐野元春の「約束の橋」。その後、紆余曲折があり、三沢本人が持ってきたのが「スパルタンX」だった。
識者はご存知だと思うが、この曲を使用したのは三沢が初めてではない。例えば、UWFとのイリミネーションマッチに際して、猪木が起用した“隠し玉”上田馬之助のテーマ曲はスパルタンXだった。というか、そもそもジャッキー・チェンの映画のサントラ盤に収録された曲である。それらの情報を踏まえたとしても、「スパルタンX」は三沢光晴のために生まれた曲としか思えない。筆者が特に印象深いのは、鶴田との抗争を繰り広げていた時期。“俺たちの時代”(鶴田、天龍、長州、藤波)を打破するニューウェーブへの期待値を高揚させるテーマとして、この曲は全てがハマっていた。
ちなみに、三沢が緑を基調にしたロングタイツを着用し始めたのは90年5月26日から。そして、彼のテーマ曲が「スパルタンX」に定着したのもこの日である。マスクを脱いで12日後、ようやく三沢光晴はスタイルを確立させたというわけだ。
最後に。筆者の思いを言わせていただくと、プロレステーマ曲のベスト中のベストは「サンダー・ストーム」。なぜなら、天龍のキャラクターとファイトスタイルを寸分違わずに表現しているからだ。加えて、「天龍! 天龍!」とファンに連呼させにくいニヒルなテンポ。会場との同化を拒否するリズムは、まさに天龍特有の“北向き”の性分である。
(寺西ジャジューカ)