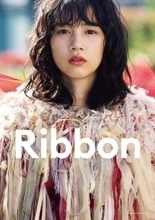そうなのだ。
方眼を埋めて、16進数になおし、データ入力してグラフィックを描いていたいのだよ、むかしは。
『ゲーム ドット絵の匠』が出た。
サブタイトルは「ピクセルアートのプロフェッショナルたち」。
インタビュアーは、とみさわ昭仁。
特殊古書店「マニタ書房」の店主であり、コレクターであり、ライター。
2009年までは株式会社ゲームフリークに所属し、『ポケットモンスター』シリーズの開発にも携わっていた。
彼が、ファミ熱!!プロジェクト編集部と協力して、7組のドット絵師にインタビューしたものをまとめたのが本書だ。

クリムトの「接吻」、ムンクの「叫び」
最初に登場するのは、『ギャラクシアン』『ギャラガ』『マッピー』などナムコの名作ゲームのドット絵を手がけた小野浩。
ゲーム内のドット絵だけでなく、製品のロゴデザインや、インストラクションカードのデザイン、アップライト筐体のパネルなど、なんでもデザインしていたと語る。そういう時代だったのだ。
ナムコの傑作ゲーム『マッピー』で、泥棒猫ニャームコが盗むモナリザの絵。
色数も限られた16×16ドットで、モナリザと判るように描かれていて、当時「すげーー」と少年たち(俺たち)は驚いたものだが、本書を読んで、また驚いた。
小野さんは、その後、個人的趣味で「絵画シリーズ」を作っていたのだ!
しかも、本書にはその絵画シリーズのドット絵が、カラー口絵でドサッと紹介されていている。
クリムトの「接吻」、ムンクの「叫び」などのドット絵名画の数々。
次に登場するのは、『ファイナルファンタジー』シリーズのドットデザインを手がけた渋谷員子。
アニメータ志望でゲームに興味がなかった彼女がスクウェアに入社したきっかけや、手探りでやってきた時代、14年のブランクの後にドット絵を打ったときのエピソードなどが語られる。
“自分の描いた絵がスマホの画面を通じて実際にユーザーに見てもらえるのは「もっと喜んでいいことなんだよ」と後輩たちに言いますね”
『メタルスレイダーグローリー』!
ファミコンでこんな緻密なグラフィックが描けたのか!と驚かされたゲームといえば『メタルスレイダーグローリー』だ。『メタルスレイダーグローリー』のグラフィックや企画、シナリオを手がけたのが、☆よしみる。
彼が、いかにファミコンの制約のなかであのグラフィックスを描き、ゲームに組み込んだのか。
度肝を抜く規格外の企画がいったいどういった環境の中で作られたのか。
手描きの「メタルスレイダーグローリー」システム仕様書も出てくる!
ドット絵といっても、懐かしのゲームだけではない。
いまも、ドット絵の新作ゲームを作り続ける人物がいる。
ユウラボだ。
子供時代にお父さんが作ってくれたゲーム(めちゃくちゃ楽しそう!)。
ゲームと出会って、作り手になるまで。
『ハイドライド』リスペクトの自主制作RPG『フェアルーン』が3DS版になるまで。
さまざまなエピソードや、レトロなだけじゃない今の技術のドット絵による表現が語られる。
インディーズゼロは、ゲーム『ゲームセンターCX 有野の挑戦状』を作った会社だ。
『ゲームセンターCX 有野の挑戦状』は、ニンテンドーDSの中で、1980年代のドット絵ゲームと、それを遊んでいた少年たちを再現したゲームだ。そのドット絵ゲームに対するこだわりと工夫。
“ファミコンだから、1スプライトは3色まで。でも、主人公だけは特別に1色、1スプライト多く持ってる。他のキャラクターはそれがないのでみんな3色で描かれている、みたいな設定。”
“そういうことの積み重ねが、時差氏のレトロゲームよりも、よりレトロっぽく見えるような仕上がりにつながっているんだと思います。”
ゲーム版トキワ荘
『ポケットモンスター』シリーズのアートディレクターを務める杉森健は、「ゲームフリーク」の初期作品「クインティ」「ジェリーボーイ」のドット絵を打った。
ゲームの同人集団「ゲームフリーク」に参加し、自分が借りた部屋が溜まり場になり、自分たちでゲームを作ろうという話が浮上するエピソードなどは、まさにゲーム版トキワ荘のイメージ。
最後のインタビューは、少年ジャンプゲーム編。
方眼用紙から画面に移すときに変わるタテヨコ比、すでにあるキャラクターをファミコンのドット絵に落としていく苦労、1ドットがすごく大きいという感覚などから、「ファミコンジャンプ」開発秘話、スクウェアに移籍してキャラの描き方がぜんぜん違って衝撃を受ける話など。
“いまの仕事に不満があるわけではないんですが、ドット絵を描いていた頃のことを思い出すと、やっぱり楽しかった”
いかに生きてきたか
語られるのは、ドット絵の技術的な奥義だけではない。
ドット絵を描いてきた人たちが、どういうふうに絵と出会い、ドット絵に関わり、ゲームに接してきたか。
いかに生きてきたか。
ただの懐かしさだけではないドット絵の世界が、7組のインタビューから浮かび上がる。(米光一成)
『ゲーム ドット絵の匠 ピクセルアートのプロフェッショナルたち』(とみさわ昭仁+ファミ熱!!プロジェクト 集英社)