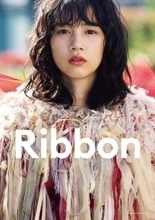先週放送された第7話の視聴率はわずかに上がって5.3%。1話完結で問題発生から解決まで描くと視聴者はスッキリ見やすいのだけれど、その分こぼれてしまう部分も多い。制作サイドが真面目につくろうとしている分、その苦悩が伝わってくる。

トム・クルーズもスピルバーグも悩んだ「識字障害」
第7話の主人公は、えみる(吉岡里帆)の同僚ケースワーカーの栗橋(川栄李奈)。頭脳明晰な栗橋は、意識も高く、仕事をバリバリとこなしていく優等生。しかし、人前で笑うことも、無駄話をすることも苦手だった。こういう人はどんな場所にも少なからずいる。
栗橋が担当している生活保護利用者の中林吉徳(池田鉄洋)は就労意欲をまったく見せない男だった。栗橋は彼の態度に苛立ち、ついに生活保護廃止の内容を示す指導指示書を発行する。
「働く意志を見せていただかないと、保護を受けることはできません」
これは規則に従った正論。話を聞いていたケースワーカーの向井(谷まりあ)は「単純に働きたくないってことかな」と口を挟むが、複雑な事情を抱える利用者に寄り添うケースワーカーが話を単純化しちゃダメでしょ。
しかし、栗橋が不在の間、役所を訪れた中林の応対をしていたえみるがあることに気づく。
「中林さん、字が読めないみたい……」
中林は識字障害(ディスレクシア)だった。
人口の3%ほどいると言われており、決して少なくはない。ドラマの中で名前が挙がったトム・クルーズやスティーブン・スピルバーグのほか、キアヌ・リーブス、キーラ・ナイトレイ、ジェニファー・アニストンらも識字障害であることを公表している。また、エジソン、ダ・ヴィンチ、アインシュタインらも識字障害だったそうだ(以上、だいたいウィキペディアより)。
真面目で優秀な人物が陥りがちな罠
中林は幼少の頃から親にも理解されず、就労先でも周囲に嘲笑されることがあった。これは辛い……。彼を唯一理解し、守ってくれた姉が亡くなり、中林は生活に困窮していた。
中林に識字障害があることを知らないまま生活保護を廃止しようとしていた栗橋は上司に叱責され、中林を傷つけてしまったことにショックを受けるが、翌日には立ち直り、中林の就労支援のため猛然と活動を始める。
ネチネチと中林に問いただす障害者職業支援センター職員や、いちいちため息を漏らすハローワークの担当者に苛立ちをぶつけ、正論を盾に突き進む栗橋。彼女のようなタイプはハリウッド映画なら小気味よく成功の道を突っ走ることができるだろうが、湿って濁った日本のローカルな行政機構の中では身動きが取れなくなる。そもそも中林に就労意欲がないままだった。
識字障害があっても肉体的には問題がないので働くことはできるはずだ。企業は法律で障害者を受け入れなければいけないことになっている。ケースワーカーである自分が努力すれば、障害に理解のある就職先は見つかるに違いない――。
栗橋の頭の中では淀みなくロジックが組み上がっているのだろう。だが、それは机上の空論だ。40年余り苦しんできた中林を理解したことにはならない。真面目で優秀な人物が陥りがちな罠だ。
「障害者、障害者ってやめてくれよ! 働け、働けって言うけど、そんなに簡単じゃないんだよ。あんたが思っている以上に、俺みたいな人、理解してくれないから、世間は」
「では、そこを理解してもらえるように頑張りましょう」
「無理なんだって! あんたみたいに普通に暮らしている人に俺の気持ち理解できないよ。あんたが一番わかってないよ、俺の気持ち!」
再び空回りする栗橋に、区役所の上司が追い打ちをかける。
「栗橋さん、君はこの数ヶ月、何を学んできましたか? 目の前の人との会話をどれだけ大切にしてきましたか? 今までもそんな態度だから、中林さんのことも何も気づかずに保護廃止しかかったんですよ!」
この叱責は理不尽なものではない。「目の前の人との会話を大切にする」ことは、半田が繰り返し言っていたことだ。
課長は栗橋を中林の担当から外し、後藤(小園凌央)を後任にする。第5話でも島岡の担当をえみるから引き継いでいたが、後藤って存在感ないわりに意外と優秀なの? 中林との面談の様子を見ていると、「識字障害」を「読み書きが苦手」とマイルドに言い換えるなど、オーソドックスな気配りができる男のようだ。
『ケンカツ』が示すクライマックス
栗橋の転機になったのは、えみるとの連帯だった。2人きりで自分のコンプレックスを吐露し、お互いの長所を言い合う。
「私は栗ちゃんがうらやましい。人の意見に流されないし、自分の考え貫き通す力があるし。まぁ、私みたいにブレないし。だから栗ちゃんがうらやましい」
栗橋が本当に優秀なのは、上司とえみるからの言葉を糧に、自分の考えを貫き通しながらも目の前の相手との会話を大切にするハイブリッド型に進化したことだ。ハローワークで偶然出会った中林は、そんな栗橋の姿を正義感の強かった姉にダブらせる。姉は彼の唯一の理解者だったが、姉が病魔に侵されたとき、彼はまったく姉を支援できずに死なせていた。
「だったら、しっかり生きなきゃ。
えみるだったら中林の話を聞いて一緒に泣いていただろう。それはそれでアリだと思う。だが、栗橋は自分なりに中林を叱咤激励してみせた。
「俺のために怒ってくれる人なんて、もう姉以外出会えないと思ってたから……」
ずっと栗橋の後をついて歩いてばかりだった中林が、今度は栗橋を先導して歩く。中林が主体的に「生きる」ことを選んだ瞬間だ。このドラマはエピソードごとに生活保護利用者が自分で「生きたい」と意志を示すところがクライマックスになっている。
彼が書店で手に取ったのは杉崎哲子・著『文字を書くのが苦手な子どものための「ひらがな・カタカナ」ラクラク支援ワーク』(明治図書)。識字障害を持つ子ども向けにつくられたワークブックだ。
先にも書いたとおり、識字障害の症状には個人差がある。漢字を見るとグチャグチャになって苦しくなる中林の症状は、けっして軽いものではないだろう。だが、自分の意志でワークブックをやってみようと手にしたことが大切なのだ。たとえ、うまくいかなくて挫けそうになったとしても、生きようという意志さえあれば次の手を考えることができる。
ただ、第7話ではちょっと結論を急いでしまったようで、中林の症状はかなり改善され、最後は就職先まで決まってしまう。明るい気持ちになる終わり方であると同時に、逆につらい気持ちになってしまった視聴者もいるのではないかと思ってしまう。難しい問題ではあるのだけれど。
今夜放送の第8話には、アルコール依存症の音尾琢真が登場! 江口のりこ、安達祐実、佐野岳、池田鉄洋、音尾琢真と非常に個性的なゲストたちが続々登場するのだが、彼ら全員が生活に困っているというのがすごい。今夜9時から。
(大山くまお)
「健康で文化的な最低限度の生活」(フジテレビ系列)
原作:柏木ハルコ(小学館刊)
脚本:矢島弘一、岸本鮎佳
演出:本橋圭太、小野浩司
音楽:fox capture plan
プロデュース - 米田孝(カンテレ)、遠田孝一、本郷達也、木曽貴美子(MMJ)
制作協力:MMJ
製作著作:カンテレ