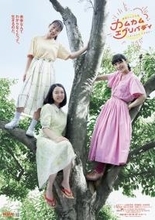長い階段が7つの宴会場をつなぐ建物で、かつては料亭として使われていた。
日本画や彫刻、螺鈿細工など、部屋ごとに個性が異なる豪華絢爛な装飾が特徴。「昭和の竜宮城」とも呼ばれたという。
その宴会場を「いけばな」でさらにきらびやかに飾ろうというのが、「いけばな×百段階段2018」だ。
全国各地から華道の流派、合計57団体が集まり、9週間にわたって開催されている。

個性豊かな「花と場の調和」
今回の展示の最大のポイントは、各流派のいけばなを部屋の空間ごと味わえること。
「普段いけばなの展示は、デパートの会場やギャラリーなど、無地の無機質な空間で行われることがほとんど。でも、百段階段というのはそれ自体がユニークな和の空間です。いけばなは床の間からはじまった文化なので、花本来の姿を見せて、流派ごとの個性が際立ちます。私たち華道家にとってもやりがいのある企画です」
そう話すのは、イベントの企画協力を行う「公益財団法人日本いけばな芸術協会」の海野俊彦さん。

10月5日〜10日時点での流派リストはこんな感じ。
ひとつの流派がひとつの部屋を丸ごと仕上げるという仕組み。
1週間ごとにいけこみ(花をいける)の日を設け、ローテーション制でその都度がらりと流派が変わる。

たとえば、階段をのぼってひと部屋め「十畝の間」を飾るのは、一葉式いけ花。
現代アートのような、独創性に富んだいけばなが特徴の流派だ。
「注目してほしいのが、“花留め”です。いける際に花が動かないようにさしてとめることで、実はこれは日本のいけばなだけが持つ技術です。一様式いけ花は、特に花留めの手法にオリジナリティがあります」と話す海野さん。

花留めには一般的に「剣山」を使うが、他にもツボにさしたり、水盤にさしたり、竹を利用したりとバラエティに富んでいる。
花を見るとき、この花はどうやってとまっているのかな?と探しながら見ると楽しい。

続いて階段をのぼると、ふた部屋めの「漁樵の間」。
部屋の装飾がとても特徴的だ。無地の壁がなく、室内は純金色。
極彩色の木彫りと日本画で埋め尽くされている。
「この部屋を飾るのは非常に難しいです。部屋の装飾に負けないようにと花をいけては絵に対して失礼で。いかにして花を場に共存させるかが腕の見せどころです」と、海野さん。

この日飾っていたのは郁生流。「花遊び」「花のある暮らし」をテーマとする優美な流派だ。
花材の色や高さなど、装飾を邪魔することなく調和を保てるよう、細かく調整しているという。

かと思えば、一見すると洋風?のいけばなもある。
きらら会は「花包のいけばな」をテーマとし、色とりどりの和紙でブーケのように花を包んでいる。
今回参加しているのは全部で57流派。流派とは、家元を中心とした組織だ。
いけばなの形式が確立されてから500年以上。そのあいだに派生し、現在は全国に300以上の流派が存在する。
それぞれの流派は「花型」と呼ばれる基本の型を持っており、いけ方も大きく異なるのだ。
「今は秋なので、いける花材はザクロや紅葉するツツジなど、どこもだいたい同じです。ところが、流派が変われば使い方も変わる。階段をのぼるたびに違った花の一面が見えてきますよ」
「いけばな×百段階段2018」
日程:2018年11月21日まで。11:00-17:00(木曜休館)
場所:ホテル雅叙園東京内 百段階段(東京都目黒区下目黒1-8-1)
入場料:当日券1,500円、期間中フリーパス2,300円
→詳細
(小村トリコ)