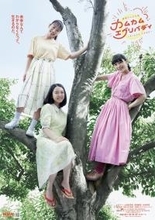おじさん、どっからでも飛んできてやるから」
渥美清主演、山田洋次監督による国民的人気シリーズ「男はつらいよ」の第1作が公開されてから50年、記念すべき50作目にあたる映画h「男はつらいよ お帰り寅さん」が2019年12月27日に公開された。
シリーズは主人公・車寅次郎を演じる渥美清の逝去によって1995年に途絶えていたが、今回はシリーズ49作を4Kデジタル修復した映像と新たに撮影された映像を組み合わせた新作となる。実質、主人公は寅さんの甥・満男(吉岡秀隆)だが、公式サイトのキャストのところにはちゃんと渥美清が最初に登場している。
今年は寅さんの少年時代を描いたドラマ「少年寅次郎」が放送されるなど、さながら「寅さんイヤー」だった。ちなみに年明け早々から山田洋次原作脚本によるドラマ「贋作男はつらいよ」が放送される。
当然、さまざまなサブテキストが出版されているのだが、なかでも「東京人」1月号「特集 寅さんと東京」が面白かったので紹介したい。

寅さんの「東京ロケ地案内」
巻頭記事は山田洋次と画家・藪野健による対談「不寛容な時代はこの厄介な男をどう迎えるか?」。金も社会的地位もないアウトローで、喜怒哀楽が激しく、場の空気も読まず、時には暴力沙汰も起こし、おまけに恋愛ばっかりしている寅次郎という男が、とても今の時代に受け入れられるとは思えない(SNSなどを見ていると特にそう思う)。
「満男は寅を通して、人間に対する寛容さや人を見る目を広げていったのだと思います」という山田洋次の言葉が印象的。余談だが、ドラマ「俺の話は長い」の満(生田斗真)と姪の春海(清原果耶)の関係は、寅次郎と満男の関係そのままである。
「東京ロケ地案内」では、50年の間に「男はつらいよ」の中で映し出されてきた東京のカットが並べられている。渋谷のスクランブル交差点にはまだ高層ビルは一つもなく、汐留にはバブル時代のイベント会場しかない。メインの舞台となる葛飾柴又の写真はもちろんのこと、もう一つの主な舞台となった「東京下町低地」――綾瀬、五反田、錦糸町、上野、根岸などの風景も興味深い。
川本三郎先生によるエッセイ「京成電車 生活文化券の物語」によると、葛飾柴又は明治末から戦後にかけて、東京の人間にとって気楽に行ける行楽地だったのだそう。
現代の寅さんはマドンナに出会えない?
美術・小道具・衣装スタッフ、キャストのほか、さまざまなジャンルの人間が語る「男はつらいよ」像も面白いのだが、強烈だったのが特集とは別に掲載されている独身研究家・荒川和久によるコラム「群れない街、東京」だった。思えば、ふられてばかりの寅さんは生涯独身を貫いたのだから、独身コラムがあるのは理にかなっている。
荒川によると現在の日本は「実は高齢者人口より独身者人口のほうが圧倒的に多い」国であり、将来的には「超ソロ社会」へ向かっているのだという。その先端を走っているのが東京で、生涯未婚率(五十歳時未婚率)は男が全国三位、女が全国一位という結果が出ている。
しかし、未婚単身男女がそれぞれどこに住んでいるかというと、男性は20~50代まで江戸川区が1位を独占し、65歳以上の高齢者を含めてベスト3がすべて江戸川区、足立区、葛飾区で占められているのに対し、女性は目黒区、中央区、港区の三区が上位を占めているという。つまり、東京の独身男女はまったく違うエリアに住んでいるのだ。それだけ両者に収入の差があるということであり、両者はもはや出会うことすら難しい。荒川は次のように結ぶ。
「最終的に失恋したとしても、マドンナと出会い、淡い恋心を抱くことのできた寅さんは、まだ幸せだったのかもしれない」
現代を生きる「寅さん」たちはマドンナに出会えない! 不寛容で格差が広がった現代の日本、現代の東京は、寅さんが居着くことができる場所なんてないのかもしれないなぁ、と思いつつ誌面を眺めた。せめて心の中に住まわせておいてあげたい、と思う人が「男はつらいよ お帰り寅さん」を劇場に観にいくのかもしれない。
(大山くまお)