この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも 無しと思へば一家三后(いっかさんごう)という前人未到の快挙を成し遂げた藤原道長(柄本佑)。摂政の位を嫡男の藤原頼通(渡邊圭祐)に譲り、自らの政権を盤石のものとしました。
【意訳】この世は私のものであると思う。望月(満月)のごとく何一つ欠けることなく、すべてが満たされたのだ。
大河ドラマ「光る君へ」公式サイトより
それを見守るまひろ(藤式部。吉高由里子)は道長の正室である源倫子(黒木華)から「殿の物語を書き残してほしい」と依頼され、困惑します。
満ちれば欠けるのが世の習い……NHK大河ドラマ「光る君へ」もそろそろ終盤に差しかかり、絶頂を極めた道長の、次第に欠けていく様子が描かれていくのでしょう。
第44回放送「望月の夜」今週も気になるトピックを振り返ってまいります。
■第44回放送「望月の夜」関連略年表
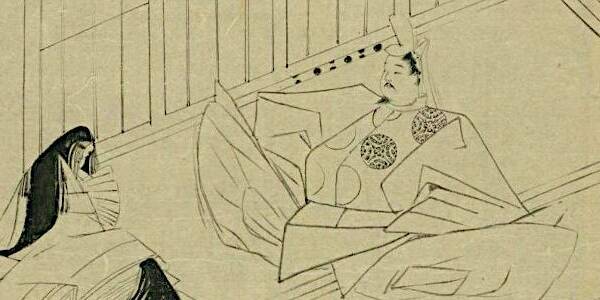
藤原道長。『紫式部物語絵巻』より
長和4年(1015年)まひろ46歳/道長50歳
- 9月~10月 道長・藤原公任・源俊賢が三条天皇に譲位を迫る。
- 10月15日 三条天皇が道長に禔子内親王の縁談を持ちかける。
- 10月27日 三条天皇が道長を準摂政に命じる。
- 12月12日 藤原頼通の病状が悪化する。
- 12月15日 三条天皇が道長に譲位の意向を伝える。
- 12月24日 三条天皇が譲位の条件として、敦明親王の立太子を要求する。
- 1月29日 道長が摂政となる。
- 2月7日 敦成親王(後一条天皇)が即位する。
- 4月29日 藤原為時が出家する。
- 12月7日 道長が左大臣を辞する。
- 3月16日 道長が摂政を辞し、従一位に昇る。
- 4月23日 寛仁に改元する。
- 5月9日 三条院が崩御される。
- 8月6日 敦明親王が東宮の地位を辞退する。
- 8月9日 敦良親王(のち後朱雀天皇)が立太子される。
- 3月7日 藤原威子が後一条天皇に入内する。
- 10月16日 藤原威子が中宮となり、道長の一家三后が達成される。
しかしその政治理念は次世代に受け継いでいけるのか……まひろの問いに対して、盃を巡らせる形で答えた?のでした。
みんなが「望月の歌」を合唱する中、茫然と?月を見上げる道長は、まひろとの「約束」を果たせた?達成感に満たされていたのでしょうか。
■頼通と破談になった禔子内親王
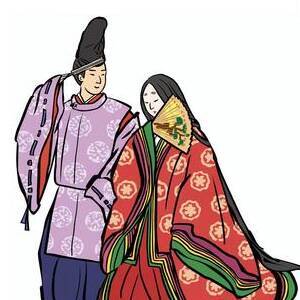
仲睦まじかった頼通と隆姫女王(イメージ)
道長との関係改善≒譲位を回避しようと図る三条天皇は、皇女の禔子内親王(ていし/ただこ/やすこ)を頼通の妻に勧めました。
古来、天皇陛下の方から積極的に内親王を降嫁させる例はなく、それだけ三条天皇が追い詰められていたのがわかります。
しかし頼通は正室の隆姫女王(田中日奈子)を愛していたため、この縁談に乗り気ではありませんでした。
また頼通が重病に臥した折、舅である具平親王(ともひら。村上天皇皇子)の霊が夢枕に立って、娘を捨てないよう涙ながらに訴えたと言います。
ちなみに『小右記』では亡き藤原伊周(三浦翔平)の怨霊とされており、本作ではこちらの説が採られました。
いずれにしても縁談は破談となってしまい、禔子内親王は後に藤原教通(姫子松柾)と結婚します。
ちなみに頼通はその後側室を迎え、後継者問題は解決されました。
「無理やり結婚を進めるなら、隆姫と二人で駆け落ちする(意訳)」
かつて道長がまひろとしようとしていたことを切り出し、因果を感じさせずにはいられません。
■藤原為時の出家

出家した為時(イメージ)
長和5年(1016年)4月29日に三井寺(園城寺)で出家した藤原為時(岸谷五朗)。その理由は単に老齢のためとも、藤式部(まひろ)が亡くなったためとも言われています。
為時は生没年不詳ですが、実子のまひろが天禄元年(970年)誕生説を採っているため、そこから20歳以上の年長であればもう古稀(70歳)が目前です。
当時の感覚とすれば、出家どころか亡くなっていてもおかしくないでしょう。
また為時の出家が藤式部らの菩提を弔うためと考え、彼女が長和5年(1016年)ごろに亡くなったとする説もあります。
いずれの理由にしても、為時は寛仁2年(1018年)に藤原頼通に詩を献じて以降、記録がありません。
恐らく次回くらいで最期を迎えることになるのでしょう。
世渡りこそ疎かったものの、為時の文才は数々の作品を通じて現代まで受け継がれています。
- 『本朝麗藻』漢詩13首
- 『後拾遺和歌集』和歌3首
- 『新古今和歌集』和歌1首
■東宮を辞退した敦明親王

敦明親王をボイコットする貴族たち(イメージ)
三条天皇が譲位する条件として、次期東宮(皇太子)となった敦明親王(阿佐辰美)。
そうした嫌がらせに耐え兼ね、また自分よりかなり年少な後一条天皇(敦成親王)の東宮でいても、自身が即位できる見込みは薄そうです。
仮に即位できたところで、周囲に味方がいない中で父帝が受けてきた仕打ち(譲位の圧力)を絶えず受け続けることになります。
前途に絶望した敦明親王は「自ら」東宮の座を辞退。かくして三条天皇との約束は実質的に反故とされたのでした。
次期東宮には敦良親王(彰子の第二子・後一条天皇の実弟。のち後朱雀天皇)が立てられ、兄弟で皇位二代を占めたのです。
東宮の座を退いた敦明親王は小一条院(こいちじょういん)という尊号を贈られ、上皇に準ずる破格の待遇を提供されました。
■欠けてゆく望月

満ちれば後は欠けるのみ(イメージ)
千年の歳月を越えて道長の悪名を高めた「望月の歌」。
しかしこれを詠んだ当時、道長自身は病(糖尿病か)に冒されてボロボロとなっており、また子供たちも一人また一人と喪われていきます。
昏倒を繰り返し、一時は三条天皇と同じく目がほとんど見えなくなっていた道長。
権力の絶頂を極める過程で蹴落としてきた相手は数しれず、思い当たる節は数え切れなかったことでしょう。
道長の死後、頼通が約半世紀にわたって権勢を誇ったものの皇子には恵まれず、時代は摂関政治から院政へと移ろい変わっていくのでした。
■第45回放送「はばたき」
まひろ(吉高由里子)の源氏物語はいよいよ終盤を迎えていた。ある日、まひろは娘・賢子(南沙良)から、宮仕えしたいと相談され、自分の代わりに太皇太后になった彰子(見上愛)に仕えることを提案。まひろは長年の夢だった旅に出る決意を固める。しかし道長(柄本佑)の反対にあい、ついにまひろは賢子にまつわる秘密を明かすことに。旅立つまひろを思わぬ再会が待ち受けていた。一方、道長は出家を決意する。病によって心身を冒され、ボロボロとなっていた道長。出家して完全引退かと思いきや、まだまだ頼通を罵と……もとい叱咤し続けます。
※NHK大河ドラマ「光る君へ」公式サイトより。
その頃まひろは内裏を去り、娘の藤原賢子(南沙良)がその跡を継ぎました。
またまひろは赤染衛門(凰稀かなめ)に物語を書くよう勧めていたようですが、これは『栄花物語(えいがものがたり)』の伏線となるのでしょう。
残り数回となった「光る君へ」最後まで見届けていきたいですね!
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan





























![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



