須原屋市兵衛令和7年(2025年)NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華之夢噺~」、皆さんも楽しみにしていますか?
すわらや・いちべえ
『解体新書』など先進的な本を出版した、時代を代表する書物問屋の店主
日本橋の中心地に店を構え、漢籍や学術書、辞典などを扱う大手本屋の商人でありながら、平賀源内や杉田玄白などが書いた“新しい本”を数多く出版する個性的で革新的な版元(出版人)。幕府の弾圧を逃れながらも『解体新書』や『三国通覧図説』など“世の中を変える本”を次々と出版する挑戦的な版元であった。
※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華之夢噺~」公式サイトより。
後世「江戸のメディア王」と称される主人公・蔦重(つたじゅう)こと蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう。横浜流星)の生涯がパワフルに描かれることでしょう。
江戸出版界の風雲児!2025年NHK大河ドラマ『べらぼう』の主人公・蔦屋重三郎は流行の仕掛人だった!
そんな蔦重の周りには、魅力的な個性を持つ人物が多数活躍していました。
今回はそんな一人・須原屋市兵衛(すはらや/すわらや いちべゑ)を紹介したいと思います。
■須原屋市兵衛・三代の足どり
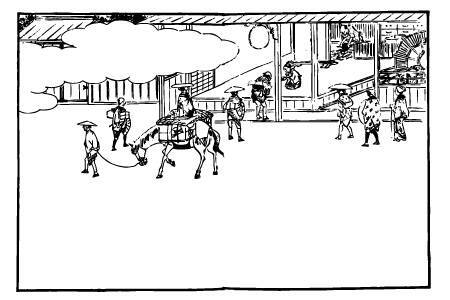
店先の様子(イメージ)
須原屋市兵衛は生年不詳、宝暦年間から文化年間にかけて活躍した版元(出版者)の一人で、須原屋茂兵衛(もへゑ)から暖簾分け(独立)しました。
三代にわたって襲名され、大河ドラマに登場するのはその初代かと思われます。
【歴代の須原屋市兵衛】
- 初代:生年不詳~安永8年(1779年)5月6日没
- 二代目:名は宗和生年不詳~文化8年(1811年)6月9日没
- 三代目:名は和文生年不詳~文政6年(1823年)8月9日没
しかし寛政4年(1792年)に重過料(罰金刑)を受け、また文化3年(1806年)の大火事(文化の大火)で打撃を被ったことで次第に経営が傾きました。
二代目が亡くなった後は共同出版のみとなり、三代目の死によって須原屋市兵衛の名(株)は休株(襲名する後継者が絶えた状態)となったのです。
墓所は浅草の善龍寺。江戸が東京となった現代も、人々の営みを見守っていることでしょう。
■須原屋市兵衛が世に送り出した主な書籍

多才で知られた平賀源内(画像:Wikipedia)
そんな須原屋市兵衛は多くの書籍を送り出しました。ここでは、主な書籍についてリストアップ。作者別に分類しておきます。
会田安明(あいだ やすあき。和算家)
- 『当世塵劫記』天明6・1786年
- 『西説内科撰要』寛政8・1796年
- 『寝惚先生文集』明和4・1767年
- 『売飴士平伝』明和6・1769年
- 『大疑録』明和4年・1767年
- 『宇比麻奈備』天明元・1781年
- 『絵本世都濃登起』安永3・1774年
- 『絵本世都の時』安永4・1775年
- 『略画式』寛政7年・1795年
- 『魚貝譜』享和2・1802年
- 『解体約図』安永元・1772年
- 『解体新書』安永3・1774年
- 『教訓いろは歌』安永4・1775年
- 『寒葉斎画譜』宝暦12・1762年
- 『民間備荒録』寛政8・1796年
- 『大清広輿図』天明5・1785年
- 『三国通覧図説』天明5・1785年
- 『物類品隲』宝暦13年・1763年
- 『火浣布略説』明和2年・1765年
- 『神霊矢口渡』明和7・1770年
- 『水の行方』明和元・1764年
- 『機巧図彙』寛政8・1796年
- 『古今名物類聚』寛政3・1791年
- 『紅毛雑話』天明7・1787年
- 『琉球談』寛政2・1790年
■終わりに
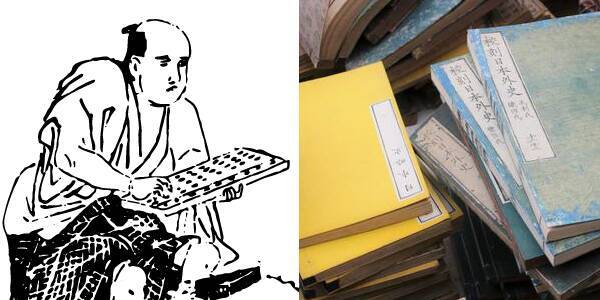
多くの書物を手がけた須原屋市兵衛(イメージ)
今回は江戸の版元・須原屋市兵衛について紹介してきました。
大河ドラマでは、保守的なお上への反骨精神を発揮して、数々の作品を世に送り出す気風が描かれることでしょう。
里見浩太朗の好演に期待しています!
2025年大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~」※参考文献:
- 今田洋三『江戸の本屋さん』NHKブックス、1977年10月
- 吉田漱 『浮世絵の基礎知識』 雄山閣、1987年7月
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan




























![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



