もちろん、フリーランスの方は自身でも積極的に情報収集している方も多いです。
そこで、本記事ではフリーランス保護新法について、クリエイティブ業界を意識した解説をしたいと思います。
目次
フリーランス保護新法とは?
▶フリーランス保護新法とはフリーランス保護新法とは、フリーランス(個人事業主)が安心して業務に従事できる環境を整えるために制定された法律で、2024年(令和6年)11月1日から施行される予定となっています。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、従来からある下請法(下請代金支払遅延等防止法)を参考に、フリーランスと発注企業間の取引における報酬の遅延、不透明な契約内容、ハラスメントなどの問題を解消することを目指して制定されました。
▶フリーランス保護新法が導入される背景
働き方やライフスタイルが多様化する中で、日本のフリーランス人口は年々増加しています。フリーランスは、場所や時間にとらわれない自由な働き方ができるというメリットもありますが、収入の不安定さや社会保障の面での課題など様々なデメリットも伴います。それにも関わらず人口が増え続けているのは、子育てや介護といったプライベートと仕事を両立させたい女性を中心にフリーランスを選択する傾向があるというのも一つの要因であると考えられます。
しばしば、「ママデザイナー」「ママライター」といった肩書で活動するフリランサーの増加がSNSで議論となっていますが、こうした現象はその顕著な例と言えるでしょう。これらの動向は、日本の労働市場における深刻な男女格差や、出産・育児、介護などに対する企業や行政の支援体制の不足、非正規雇用の問題と深く関連しており、ジェンダーギャップ解消の遅れが背景にあると考えられます。
※参考URL:女性フリーランスの仕事は?データを用いて実態も解説(コエテコキャリア)
加えて、フリーランスが増えている背景には、企業が人件費削減のためにフリーランスを活用しようという動向が存在します。時間拘束や出社義務があるなど、実質は「みなし社員」として雇用契約とほぼ同じ条件で働かされているフリーランスが増加していること、労働者として雇用されたと思っていたのに実際は業務委託契約や請負契約であったといったケースが目立つようになってきたことなどが社会的な問題となって、フリーランス保護新法が成立したということを、まず理解しておきましょう。
▶公的機関からの情報発信
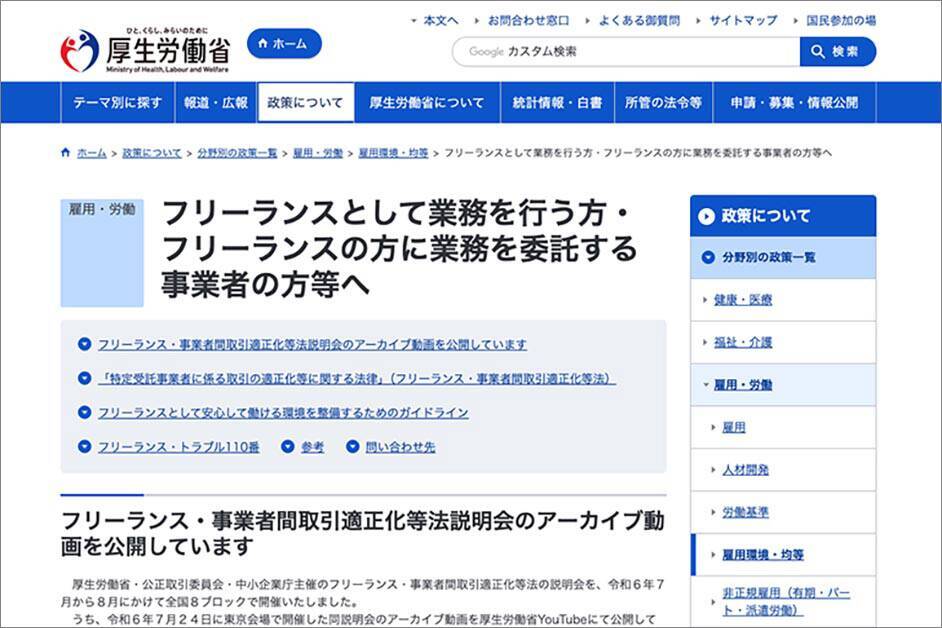

同様に、弁護士や公認会計士・税理士などの士業の方々が提供するYouTube動画なども、有益な情報源です。しかし、その考え方は立場によって様々で、フリーランス保護新法とインボイス制度はセットで推し進めていくものという視点で語られることも多いので、こちらも免税事業者を選択したフリーランサーにとってはモヤモヤしながら視聴しなければいけないかもしれません。
フリーランス保護新法で知っておきたいポイント
続いて、フリーランス側の立場に立ってフリーランス保護新法の内容を確認してきたいと思います。フリーランス保護新法のすべてを把握することは大変ですので、ここではクリエイターの方が知っておきたいチェックポイントをピックアップして紹介します。(筆者は法律の専門家ではありませんので、認識等が十分でない部分もあるかもしれません。条項の内容についてはご自身でも目を通して確認し、企業の方は法務部や顧問弁護士等にも確認してもらうようにしておきましょう。)
▶フリーランス保護新法に盛り込まれた義務項目
①書面などによる取引条件の明示
フリーランス保護新法では、業務を発注する際に「書面での契約内容の明示」「契約内容の明確化」「募集情報の的確な表示」などが義務付けられています。業務内容、報酬額、支払期日などの取引内容をメールや契約書などの書面に明確に記載して発注しなければいけなくなるので、電話や対面など口頭で発注するといった商習慣は改める必要があります。
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
フリーランス保護新法では、報酬の支払期日は納品日から数えて60日以内と定められています。また、発注の際に設定した支払い期日を守るという義務もあります。下請法では以前から同様の義務が設けられていましたが、資本金1,000万円以上の企業を対象としていました。これが、すべての発注者に適応されることになります。なにをもって納品完了とするかについては、業種によっても異なると思いますが、請求書で良く用いられるその月に発注した依頼分をまとめて「月末締め」「25日締め」のように締日を納品の起点と考える支払い方法は、注意が必要です。「納品締日の翌月末に入金」の場合は、現行のままでも60日以内に収まると思いますが、個々の納品日を明記するといったように発注書や請求書の表記に関して見直す必要が出てくるでしょう。また、個々の商品・サービスが納品された日付から数えて60日以内となりますので、「納品締日の翌々月末に入金」といった支払期日は、この規定に抵触する可能性が高いです。こちらは、支払期日の設定自体を見直す必要があります。
③7つの禁止行為
フリーランスに対して1ヵ月以上の業務を委託している場合は、以下の表にある7つの行為が禁止されています。また、1ヵ月以上という条件が設定されていますが、もちろんこれらの行為は1ヵ月未満の依頼でも推奨されるものではありません。1ヵ月未満の場合は罰則が発生しないだけですので注意しましょう。
禁止行為説明受領拒否注文した商品・サービスの受領を拒むこと報酬の減額発注の際に定めた報酬額を減額すること返品受け取った商品・サービスを報酬を支払わずに返品・返却すること買いたたき類似の商品・サービスなどと比較して、著しく低い報酬を設定すること購入・利用強制指定する商品・サービス、役務などを強制的に購入・利用させること不当な経済上の利益の提供要請金銭、労務の提供などをさせること不当な給付内容の変更・やり直し費用を負担せずに注文内容を変更すること・受領後にやり直しをさせること④募集情報の的確表示
フリーランスの募集・求人情報を発信する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはいけないという規定です。また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければいけません。
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
フリーランスに対して6ヵ月以上の業務を委託している場合は、フリーランス側からの申し出に応じて、業務受託者が出産・育児、介護などと業務を両立できるように配慮する必要があります。
⑥ハラスメント対策に関する体制整備
フリーランス保護新法には、フリーランスが業務においてハラスメントを受けないようにするための規定も盛り込まれています。フリーランスは立場も弱いので、実際には報告されている件数よりも多くハラスメントが発生していると推測されます。パワハラ、セクハラといったハラスメントはもちろんのこと、⑥と関連してマタハラ(妊娠・出産などに関するハラスメント)なども対象になります。
⑦中途解除等の事前予告・理由の開示
これは「中途解除する少なくとも30日前に通告する・フリーランスが解除の理由を請求した場合は開示する」といった内容で、労働契約と同等の措置となります。
▶対象となる範囲

条件によって異なる対応が必要な義務項目
従業員の有無と委託期間対応が必要な義務項目従業員がおらず1ヵ月以内の委託期間①従業員を使用しており1ヵ月以内の委託期間①②④⑥従業員を使用しており1ヵ月以上の委託期間①②③④⑥従業員を使用しており6ヵ月以上の委託期間①②③④⑤⑥⑦注意が必要なのは、①に関しては従業員を使用していないフリーランス・個人事業主が、他のクリエイターに発注する際も適用される点です。フリーランサーも委託される側としてだけでなく委託する側としての準備も必要になってくることは、しっかりと認識しておきましょう。
フリーランス保護新法チェックリスト
▶︎フリーランス保護新法に抵触する可能性が高い業界や案件
フリーランス保護新法の概要が確認できたところで、自分の仕事に関する状況も確認しておきましょう。以下のチェックリストは、現状の商習慣等で、新法に抵触する可能性が高い案件・業種などを確認できますので参考にしてみてください。注意が必要な案件・業種チェックリスト
契約内容が不明確な案件 口約束での仕事フリーランス保護新法施行以後は、フリーランスに口頭で発注することはできないので、そうした慣習となっている場合は是正が必要報酬体系が不明確な案件報酬体系が不明確な案件については注意。募集段階から条件を明示する・確認するようにする著作権に関する規定が不明確な案件著作権に関する規定が不明確な案件については注意。契約締結の際に必ず確認するようにするハラスメントが発生しやすい案件 クライアントとの直接的なやり取りが多い案件クライアントから直接依頼される案件は条件面で高待遇なことが多いが、一方でハラスメントは発生しやすいので注意。納期が厳しく、長時間労働が求められる案件納期が短い案件、長時間の作業が必要な案件などは注意。発注の段階で無理のないスケジュールを設定するよう心がける。支払い遅延のリスクが高い業界 ゲーム業界ゲーム開発では、開発期間が長期にわたるため、中間報酬の支払いが遅延したり、完成後のロイヤリティの支払いが大幅に遅れるケースもあるので注意映像業界映像制作では、制作費の支払いが分割されることが多く、最終的な支払いまで時間がかかることがあるので注意Web業界記事コンテンツ制作などは、出版と異なり締め切りが明確にないため、修正が繰り返され納品完了とならないケース、実際の納品日でなく公開日を起点に計算されるケースなどが多いので注意出版業界印税の支払いなどが数ヶ月後になることが一般的。また、特に書籍系は原稿料も、納品日ベースではなく、書籍発売後という慣例があるので注意その他 業務範囲が曖昧な案件業務範囲が曖昧な案件は注意。発注書を発行する段階で業務内容を明確にしておく。再委託が頻繁に行われる案件再委託が頻繁に行われる案件は注意。元請け、下請け、孫請け等、それぞれの段階で条件面をすり合わせておくことが必要。上記に挙げた他にも、フリーランスにとって不都合な条件となりやすい案件は多くあります。
クリエイターが取るべきアクション
▶フリーランス側がすべきことフリーランスがまずしなければいけないことは、フリーランス保護新法の内容をしっかりと把握しておくことです。その上で、信頼関係を築けているクライアントの委託案件で、問題がありそうなものがあれば、発注方法、支払期日、報酬体系、修正回数などについて見直しや条件のすり合わせを打診してみましょう。
また、雇用関係に近い業務となっていないか見直すことも重要です。時間拘束や出社義務など、時間や場所に拘束がかかる業務内容は、業務委託の条件に則していません。契約書では問題がなくても、担当者が理解していないケースもあります。メール・チャットのやり取りなどで、雇用関係に近い指示が出た場合などは丁寧に説明するのが最善の方法です。もし、現状言い出しにくい関係で仕事をしている場合は、トラブルが発生した際に備えて作業記録を取っておきましょう。
また、収入がそれなりに安定している場合は、クリエイター向けの団体・協会に所属することも、自分を守る上で役立ちます。年会費等が必要になりますが、法的なサポートや同業者とネットワークが作れることは、心強いでしょう。
▶発注・クライアント側がすべきこと
発注側・受託側の両方がフリーランス保護新法に合わせて、発注方法や支払期日などを見直す機会を設けられるのが理想的ではあります。しかし、フリーランス側から、契約条件の改善を積極的に要求することは、現実的に難しいケースも多くあると考えられます。まだ何も対策を打ち出していない企業の担当者は、法務部・人事部・経理部など関係部署と連携し、早急に11月以降の具体的な対応策・社内体制の整備を進めること強くお勧めします。
▶トラブルが起こってしまった場合
公正取引委員会の特設サイトでは、トラブルが発生した際の相談窓口は「フリーランス・トラブル110番」であると案内されています。

まとめ
フリーランス保護新法が施行されても「どうせ今までとそんなに変わらないでしょ」と思われる方もいるかもしれません。しかし、この法律には罰則規定が定められています。数の多さから考えて、すぐに摘発されることはないと思われますが、悪質な業者が見せしめ的に摘発されてから対応するのでは手遅れです。発注側の担当者は、フリーランス保護新法についてよくわからないといった上長の方などにも、本記事なども活用してもらって周知いただければと思います。また、フリーランスという働き方を選択した方々も、フリーランス保護新法の施行を機会に、しっかりと自分の立場を守れるような環境づくりを改めて模索していきましょう。フリーランスという働き方を利用して政府・行政・企業など雇用の流動性を高めていきたいといった思惑があった上での新法かもしれませんが、それを活かせるかどうかは、私たちフリーランスが主体的に新法を享受していこうとする姿勢にあるのかもしれません。










































![[USBで録画や再生可能]Tinguポータブルテレビ テレビ小型 14.1インチ 高齢者向け 病院使用可能 大画面 大音量 簡単操作 車中泊 車載用バッグ付き 良い画質 HDMI端子搭載 録画機能 YouTube視聴可能 モバイルバッテリーに対応 AC電源・車載電源に対応 スタンド/吊り下げ/車載の3種類設置 リモコン付き 遠距離操作可能 タイムシフト機能付き 底部ボタン 軽量 (14.1インチ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51-Yonm5vZL._SL500_.jpg)