そこで今回は、Google検索からAI検索へと人々の検索行動が変化する中で、クリエイターはどのような対策を取るべきかといった視点に立ち、次世代SEOとWeb最適化について詳しく解説します。また、そうした次世代SEOやWeb最適化に伴って、クリエイター自身は、どういう方向性を模索するのがベストなのかといった問題についても考察します。
※本記事は前後編の2回に分かれて掲載。〈前編〉から続く。
目次
情報提供と価値提供の2軸で考える次世代SEO
〈前編〉に続き、ここからは、次世代SEOで重要になる情報提供型コンテンツと価値提供型コンテンツの違いと、それぞれの特徴を深く掘り下げていきましょう(ここでは便宜上、テキストコンテンツを中心に解説しますが、動画コンテンツや音声コンテンツに置き換えても、同様の違いがあります)。▶生成AIの素材を提供する「情報提供型コンテンツ」
◎情報提供型コンテンツ(ニュース、用語集、広告、一般的なタイアップ記事など)
情報提供型コンテンツは、生成AIに代替されやすい領域の代表格です。そして、「ゼロクリック検索」でのAIによる回答や要約の素材として活用されるだけでなく、AIチャットボットやその他の生成AIモデルが情報を生成する際の基盤となるのも、この情報提供型コンテンツであることが多いです。これは、従来型のSEOライティングをはじめとした標準化されたフォーマット(型)を持ち、なおかつ大量の類似コンテンツがネット上に存在するジャンルからのデータ収集と再合成が生成AIの最も得意とする領域だからです。また、誰が書いても大きな違いが出にくいニュース、用語集、広告、一般的なタイアップ記事なども情報提供型コンテンツに該当します。こうした領域は、今後AIライティングの主戦場となるでしょう。

また、情報提供型コンテンツを引き続き提供していきたいと考えるWebメディアは、人間が直接制作に割くリソースを最小限に抑え、AIツール導入による自動化と効率化されたサイト運営を徹底していく必要があるでしょう。さらに、この領域ではコンテンツ制作費用の大幅な削減と、それに伴う人員のリストラ・配置転換が求められる可能性が高いと予測されます。加えて、SEOコンテンツの制作代理店はAIエージェントに代替される可能性が高く、これら制作代理店や代理店に登録しているクリエイターは、早急に事業の方向転換やキャリアシフトに向けて動き出す必要があると考えられます。
▶独自性や革新性を有した人間の手による「価値提供型コンテンツ」
独自性や革新性を有した「ユニコーン記事」としての人間の手による価値提供型コンテンツには、大きく分けてアプローチ力主導型コンテンツと表現・構成力主導型コンテンツの領域があると考えられます。以下にその2つの違いを説明します。
◎アプローチ力主導型コンテンツ(インタビュー、ルポルタージュなど)
アプローチ力主導型コンテンツとは、インタビューを中心とした取材記事や、現場での取材を中心としたルポルタージュ、ニッチな領域でのマニアックな調査活動を行うタレント性も兼ね備えた執筆者の手によるレビュー記事などが挙げられます。これらは、書き手のアプローチ力が問われる領域で、現場への深い潜入、独自の体験、人間的な関係性から生まれる一次情報がコンテンツの核となります。この領域で提供される価値は、AIには不可能な「発見」と「体験の言語化」です。
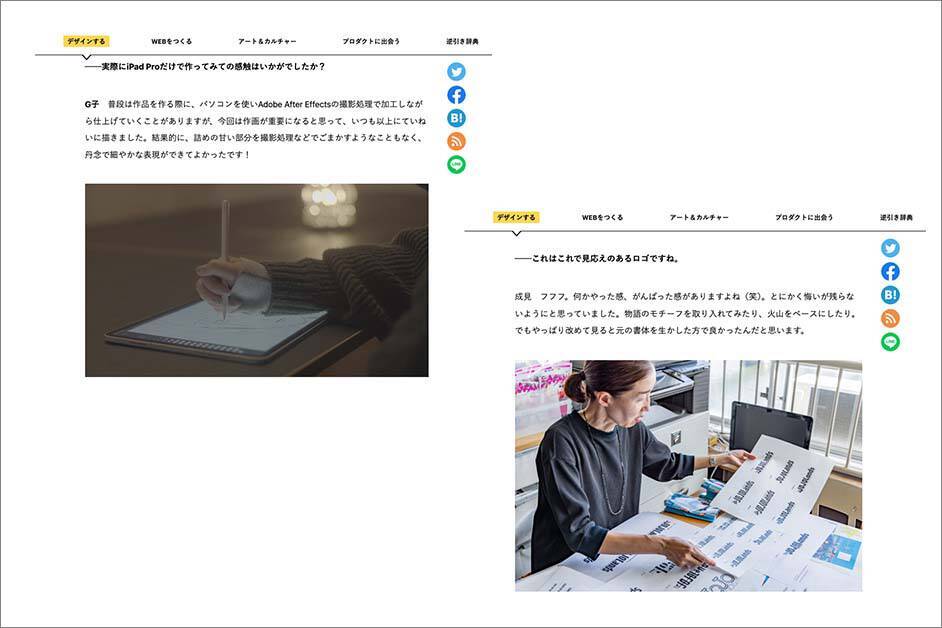
◎表現・構成力主導型コンテンツ(連載記事、コラム、エッセイ、批評など)
表現・構成力主導型コンテンツは、執筆者の独自の視点、哲学、感情を込めた言葉で読者の心を動かす「作品」を生み出す領域です。
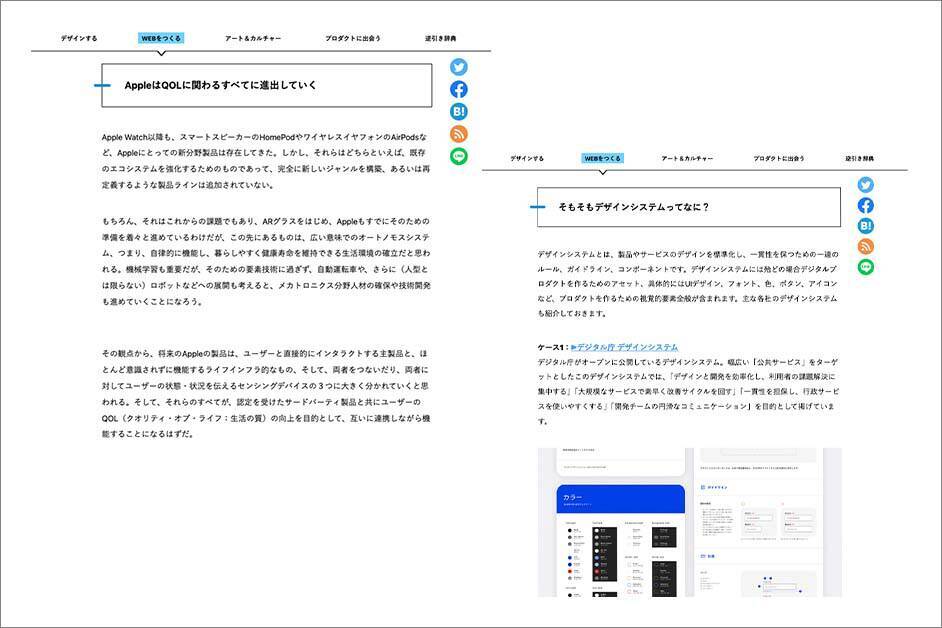
▶価値提供型コンテンツであることをAIに示すポイント
こうした価値提供型コンテンツは、E-E-A-Tを高めていくのにも貢献します。また、価値提供の中に有益な情報も含まれるため、AIOやLLMOにおいても高い評価を得やすい側面があります。こうした観点から、費用対効果という点においても価値提供型コンテンツは情報提供型コンテンツより優れていると言えます。
しかし、現状のAI検索や生成AIは、必ずしもコンテンツの「価値」や「独自性」を十分に汲み取り、適切に評価できているとは限りません。特に、生成AIによるコンテンツが大量に投入されつつある局面で、画一的な情報提供型コンテンツが多数を占める現状では、真に価値あるコンテンツが埋もれてしまう過渡期にあるとも言えるでしょう。ただ、GoogleをはじめとするAI開発企業は、ユーザーにとって真に価値ある情報を優先的に提示できるよう、現在も積極的なチューニングと進化を続けています。
次世代SEOの観点から重要なのは、そうした状況下でも、必ず署名を入れ誰が書いたものなのかを明示することです。この際「〇〇編集部」といった形で具体名を避けるより、著者の個人名による署名にしておくことで、より独自性の高い記事であることを示せます。近年、スーパーの野菜売り場でも生産者の写真やプロフィールが掲載されていることがあります。これは作り手を可視化させることで、信頼性を高めているのであり、署名記事の効果も同様です。また、情報ソースがわかるように参考文献・参考Webサイトなども明記することなどでも記事の信頼性を高めることができます。こうしたアカデミック・ライティング的な記述ができるかどうかも書き手の資質に左右されます。
加えて、次世代SEOでは、連載が持つ「シリーズとしての価値」も高まります。LLMは単一のキーワードだけでなく、記事間の関連性やシリーズ全体の文脈、E-E-A-Tにおける専門性と権威性の蓄積などを理解できるようになるため、連載を通じて特定のテーマや筆者(あるいはメディア)がエンティティとして確立されやすくなるからです。ページ単体の評価だけでなく、こうした著者のシリーズ作品全体の評価も意識することで、次世代SEOの攻略が上手くいくでしょう。
▶価値提供型のクリエイターを登用する意義
アプローチ力主導型、表現・構成力主導型のいずれにおいても、「外れ値」とも言える突出した才能を持つユニコーン人材を発掘・育成する必要があります。
また、単に才能を発掘するだけでなく、育成・保護する視点も不可欠です。加えて、クリエイターをアウトソーシング的な下請けとしてマイクロマネジメントするのではなく、魅力あるコンテンツを作成するパートナーとして個人の才能に委ねるといった姿勢も求められます。これはライティング分野以外の漫画家などのクリエイター登用にも共通する部分でしょう。そして、こうしたクリエイターの才能を最大限に引き出す優れた編集者(ディレクター)の存在もまた、非常に重要なポイントとなります。
確かに、こうした手間やコストといった側面があるとしても、価値提供型のコンテンツを生み出せるクリエイターは、メディアのブランドイメージを確立し、Webメディアそのものの価値向上に大きく貢献してくれる存在です。Webメディアは、生成AI検索へシフトする中で重要な岐路に立たされています。その分岐点で自社にとって正しい道を選択できるかどうかは、こうした本質的な人材登用の意義を深く理解し、新たな認識を確立できるかにかかっているのです。
▶まとめ:雑誌スタイルへの回帰が一つの解決策
「ユニコーン記事(コンテンツ)」の重要性を理解しつつも、時間やコストを考えるとすぐにすべての記事をその方向へ切り替えるのは難しいケースが大半でしょう。では、今後Webメディアのあり方はどのように変わっていけば良いのでしょうか。ここで重要なポイントになるのは、すべての記事をユニコーン記事にする必要はないということです。
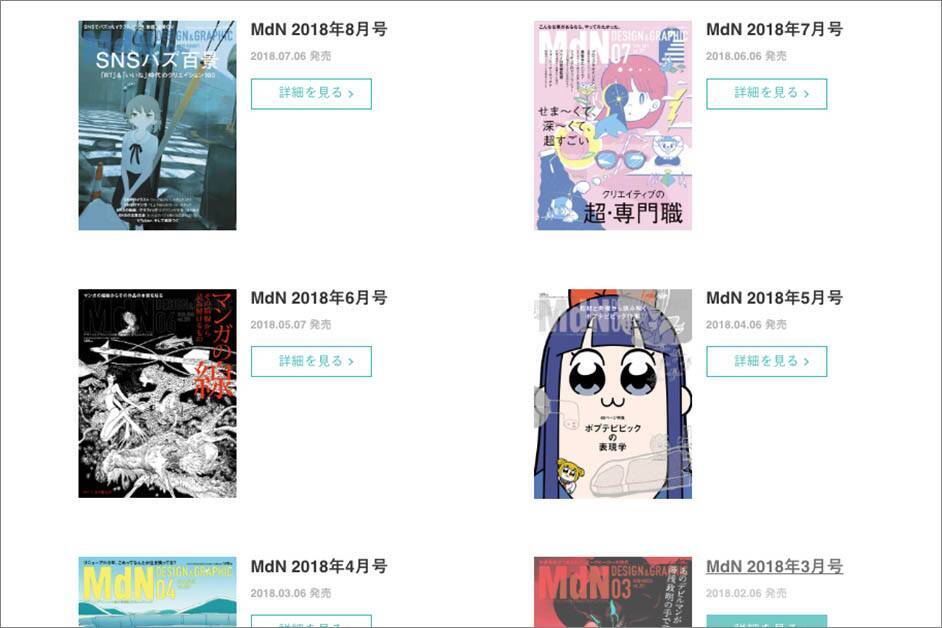
現在のメディア構成や既存の記事を次世代SEO向けに最適化するためには、まずニュース記事、タイアップ記事、記事広告、用語集といった情報提供型コンテンツを充実させ、既存記事のリライトなども含めて、生成AIの回答や要約の素材となるような改善策を講じるのが一つの重要な軸になります。その一方で、注目の高い人物へのインタビュー記事や惹きのある独自性の高い特集記事や連載など、Webサイトの特性に合致したテーマで勝負する価値提供型コンテンツを提供するといった方向も模索してみましょう。
このように、Webメディアの主流となっているブログ的な内容構成から、雑誌の誌面スタイルを参考にしたメディア構成へと調整していく取り組みは、次世代SEOにおいて有効な対策の一つとなるでしょう。
AIに代替されないクリエイター人材になるためのヒント
AIの進化は、クリエイターの未来に大きな問いを投げかけています。それは、AIに代替されない存在となるために、コモディティ人材(大量生産され、他者との差別化が難しいスキルを持つ人材)になるのか、それともユニコーン人材(唯一無二の価値や独自性を持ち、市場で希少な存在として輝く人材)を目指すのか、という選択です。▶コモディティ化されたジャンルの脆弱性を理解する
AIが得意とするのは、定型化された表現ジャンルです。これは、管理されたセントラルキッチンでマニュアル通りに作られるチェーン店の料理に例えられます。一方で、人間のクリエイターにしか実現できない独自性や革新性のある表現は、一流の料理人が提供するレストランの料理のようなものです。
生成AIに置き換わる可能性が高いジャンルの代表格であるSEO記事では、例えば「あなたは今、〇〇について悩んでいませんか?」から「今日からぜひ、〇〇を実践してください。」といった、均質化された展開パターンが確立されています。
こうしたコモディティ化が進んだ表現ジャンルは、生成AIが学習しやすく、代替されやすい領域なのです(ここでの言説は、生成AIの不正学習問題とは別の次元の視点における分析であることをご留意ください)。コモディティ化は、提供されるサービスやコンテンツの品質が一定水準にあっても、供給過多のレッドオーシャン市場では生成AIの問題とは関係なく必然的に発生する現象です。ただし、人気絵師のようにコモディティ化されたジャンルであっても、その頂点に立つ圧倒的なクオリティは、AIが模倣できない「外れ値」として、常に特別な価値を放ち続ける分野もあり得るということも補足しておきます。
▶型を破ることの重要性
SEOライティングをはじめとする情報提供型コンテンツは、フォーマットが確立され大量生産されているため、まさに生成AIが学習し再現しやすいコンテンツと言えます。したがって、AIに代替されないクリエイターを目指すなら、型に縛られた表現形式や意味内容からの脱却が求められます。
日本の伝統芸能である能楽には、世阿弥が説く「型破り」の精神があります。これは、型を極めた者がそれをあえて崩し、新たな表現を生むという考え方です。クリエイターが生成AI時代を生き抜く上でも、SEOの型を習得した上でクリエイティブに「破る」ことで、自身の表現を人々の心に響くコンテンツへと進化させていくことが重要です。また、それはSEOの型という「盛り付け」の部分だけに囚われず、自分にしか作れない本当に美味しい「料理」を提供することこそが大切だという意識を促すでしょう。さらに、美味しい「料理」を意識することで、生成AIによるコンテンツと優れた才能を持つ人間の手によるコンテンツに、「味」の部分で大きな差が存在することも見えてくるはずです。
もちろん、AIライティングなどでAIを最大限に活用し、AIに正確に情報を伝え効率的に届ける技術を磨く道も選択肢の一つです。しかし、それは他者やAIに代替されうるコモディティ人材の中でトップを争う、過当競争の中に身を置くことを意味します。この領域で習得できるスキルは『機動戦士ガンダム』で例えるなら、「ジム」や「ザク」といった量産型モビルスーツを操るための、普遍的で効率的なスキルに相当します。一方で、人間の手による独自性・革新性のある表現領域で得たスキルは「ガンダム」や「シャア専用ザク」といったパイロットの個性を最大限に引き出すパーソナライズされたモビルスーツを操るための、高度で専門的なスキルに相当するでしょう。こうした独自のモビルスーツ(スキル)を操るには、ガンダム作品で描かれる「ニュータイプ」のように既存の枠に収まらない「外れ値」の独自性や革新性を持ったクリエイターでなければなりません。
かつては、専門的な訓練や突出した才能がなければ「クリエイティブの世界」で生計を立てることは難しいとされていました。しかし、Webの普及やクラウドソーシングといったサービスの興隆と共に、誰もが情報を発信できる時代になり、多様なスキルレベルのクリエイターが活躍するようになりました。才能のある人間にとっては、むしろこれまでの均質化された市場こそがディストピアだったとも言えるのです。これから起こる生成AIによる変化は、クリエイター職がこの世から存在しなくなるという変化ではなく、実は量産型のクリエイターが淘汰され、本来の意味で創造性や専門性を持った「クリエイター」が活躍する世界への回帰なのです。
▶いま現実的にできる対応について
ただ、現実には、Webメディアの土壌がまだユニコーン的コンテンツを求めるほど成熟していない状況があるかもしれません。そのため、しばらくの間はコモディティ的コンテンツとユニコーン的コンテンツの両方を使い分ける「ハイブリッド型」のクリエイターとして活動するスタイルも有効でしょう。具体的に実践できることとしては、実績公開可能な案件(署名記事やポートフォリオ等に掲載可能な業務上の作品)を増やす、独自ドメインのポートフォリオを持つといった対策は、今後より大きな効果を持ちます。なぜなら、AI技術が組み込まれた次世代SEOにおいては、そうした実績やポートフォリオ、独自性を持つクリエイターのプロフィールなども、より発見されやすくなる傾向にあるからです。
また、「私が教える次世代SEOのノウハウこそ、これからのAI時代に通用する正解だ。それができないクリエイターは、もはや必要とされなくなる」といった形で不安を煽るIT系・Web制作系のインフルエンサーや情報商材提供者の言葉には、冷静に対処することが重要です。 そうした情報発信の意図には、彼らが考える「優れた情報提供」こそが「価値」だという誤解があるかもしれないからです。しかし、これまでの考察からご理解いただけたかと思いますが、フォーマット化された「優れた情報提供」こそ、生成AIが最も得意とする領域です。そして「これを実行しておけば大丈夫」といった次世代SEOの画一的なフォーマットや再現性の高い必勝法は存在しません。「価値」を提供できているクリエイターであれば、むしろ次世代SEOによって恩恵を受けることのほうが多いはずですので、不必要に不安を煽る情報には注意深く向き合いましょう。
加えて、資格や職能、大学・大学院で学んだ専門分野などを軸に「◯◯ライター」「◯◯系YouTuber」といったように専門的で質の高い情報提供の領域で活動する人なども、情報提供である限りAIによる情報提供に代替されやすい領域であることを念頭において、改めて自分は情報以外の価値を提供できているかを確認することが大切かもしれません。
そして重要なのは、生成AIに代替されないクリエイターになるために、コモディティコンテンツとユニコーン的コンテンツの違いを明確に理解し、自身のスキルを投資する領域を正しく見極めて実績や経験を積んでいくことなのです。
まとめ
本記事では、次世代SEOの解説から、AIに代替されないクリエイターになるためのヒントまで深く掘り下げてきました。読み進める中で「情報提供」は、AIが得意とする「データ処理」の世界であり、「価値提供」は、そのデータ処理の範疇を超えた領域なのだということがお分かりいただけたのではないでしょうか。また、この連載自体も単なる情報提供型から独自の視点提供を重視する価値提供型コンテンツへと少しずつ変化しています。これは本連載の中で、生成AIについて調査する中で得た独自の経験から導き出した一つの答えです。もちろん、次世代SEOで生成AIの回答に利用されるコンテンツを目指すことは重要です。しかし、執筆者の本望としては、自身の書いたコンテンツを最後まで楽しんで読んでもらいたい、という思いも強く持っています。だからこそ、逆説的ではありますが、次世代SEOを攻略するテクニカルな手法やアプローチについても深く理解する必要があるとも感じています。
そして、この執筆者としての本質的な追求は、特定の専門領域に深く携わる書き手が見過ごしがちな視点かもしれないのです。例えば、ジャーナリズムや学術論文といった「フォーマットのある文章」を主な情報伝達の手段とする方々は、読み物としての「価値提供」という視点を見過ごしがちな傾向にあるのかもしれません。また、エンジニアは自然言語による文章表現を情報処理するだけのコーディング・プログラミングと同じようなものとして捉えている節があります。もちろん、そうした分野にも読者の心を深く動かすクリエイティブな書き手は存在します。しかし、型にとらわれず、データとして処理できない読者の感情や思考に深く働きかける文章表現こそが、クリエイターとしての「物書き」が担う特異な領域の一つとも言えるのではないでしょうか。
Googleが最近発表したA2A (Agent2Agent) Protocolのように、AIエージェントがAIエージェントに対応して情報処理をしていく新技術は、あらゆる代理業やアウトソーシング的業務がAIエージェントに置き換わる未来を示唆しています。こうした生成AIの浸透は、インターネット上の情報提供やWebコンテンツそのものに大きな転機をもたらすでしょう。これからのクリエイターは、こうした技術的な進化を理解し、自身のクリエイティブに活かすことが極めて重要になってきます。そうした変化への理解を深めるために、この記事が、多くのクリエイターにとって有益な情報の一つになれば幸いです。
※〈前編はこちら〉












































![[USBで録画や再生可能]Tinguポータブルテレビ テレビ小型 14.1インチ 高齢者向け 病院使用可能 大画面 大音量 簡単操作 車中泊 車載用バッグ付き 良い画質 HDMI端子搭載 録画機能 YouTube視聴可能 モバイルバッテリーに対応 AC電源・車載電源に対応 スタンド/吊り下げ/車載の3種類設置 リモコン付き 遠距離操作可能 タイムシフト機能付き 底部ボタン 軽量 (14.1インチ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51-Yonm5vZL._SL500_.jpg)