ロシアとウクライナの戦争はいつ終わるのか。東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんは「領土問題が片付いたら休戦できるというのは誤解。
■国際情勢ネタは「大手メディア」も信用できない
【黒井】タブロイド紙に誤報が多いのは、ウクライナ侵攻に限らず、国際情勢ネタではよくあることですが、怪しい報道はタブロイドに限らない。米国の『ニューズウィーク』、『フォーブス』、『ブルームバーグ』などでも誤報はあります。それと、意外と誤報が多かったのが『ウォールストリート・ジャーナル』ですね。参考になる記事も多いのですが、国際紛争に関しては、未確認で裏取りがなくてもとにかく掲載、という方針っぽいです。
ニュースを追っていくうちに、それぞれのメディアのクセのようなものが経験則で見えてきて、そういう勘所みたいなものがないと、急なニュースの情報の扱いで間違う懸念があります。
【小泉】メディアのそういう性質みたいなものも、だんだんとわかってきますよね。やはり大事なのはこちらの情報の蓄積で、そうすることで相場観が見えてきます。
【黒井】メディアだけでなくて、シンクタンクのレポートでも、全部が全部、正しいわけではないことに留意が必要です。たとえば世界最高水準のイギリスの研究機関・RUSIでも、ウクライナ侵攻直後はロシア側の内部情報について間違った記述がありました。
そうした非公開の分野の内部情報は確認が難しいので、細かいミスはどこでも誰でも起こし得ます。
■記事の署名からわかること
【小泉】記者名も大事ですよね。ずっとニュースを追っていると、この分野はこの記者が強いということも見えてきます。
【黒井】アメリカの軍事マニア向けの新興サイト・ウォーゾーンが、ときどきウクライナ国防省情報総局のブダノウ長官の独占インタビューを掲載し、重要な情報を発信したりします。
ウォーゾーンには情報総局に強い記者がいるのですね。この人はもともとフロリダ州タンパの地方紙の新聞記者で、現地の米軍基地の担当で、フロリダ州の退役軍人会とか特殊作戦部隊OB人脈に太いパイプがある。そこから軍事記者をずっとやっていて、老舗軍事メディアの『ミリタリータイムズ』の上級編集者を経て、今はウォーゾーンの記者なのですが、一部の特殊部隊やそのOBにどうも強いコネがあるようです。
ウクライナの情報総局はおそらく米国の特殊部隊とコネがあるし、米軍OBがアドバイザーで入っていると思うのですよね。ウォーゾーンのブダノウ取材は、おそらく記者の個人的なコネだと思います。
【小泉】情報発信者の人名で情報を見ていく、という解像度は必要ですね。
■記者の想像で書かれたプーチンの病状
【黒井】メディアにも、そのときどきの内部の体制での方針というものがあります。未確認でも、飛ばしOKでどんどん載せちゃえというメディアもあります。
プーチン重病説は、英タブロイド各紙では、たとえば『デイリーメール』は「プーチンは血液ガン」「余命3年の宣告」、『デイリーミラー』は「プーチンは視力を失いつつある」と報じています。『ニューズウィーク』では「プーチンはすでに進行ガンで治療を受けている」として、治療歴をかなり具体的に書きました。
執筆者はベテランの軍事ジャーナリストで、米軍に関する著書を私も何冊か読んだことのある著名な人なのですが、ここのところ完全に飛ばしライターになっています。
『ニューズウィーク』はかつてはワシントンポスト系で、『タイム』誌と双璧の信頼性の高いニュース誌だったのですが、売却されて経営者が代わってから、どうも編集方針が変わったようです。
世界最古のイギリスの高級紙『ザ・タイムズ』も飛ばし記事が多かったですが、同紙もあのルパート・マードック(米国の世界的なメディア王)に買収されてから、編集方針が変わったのかもしれません。『ウォールストリート・ジャーナル』もマードック傘下です。
■ウクライナメディアはニュースを誇張しがち
――ウクライナ側の情報の読み方は?
【小泉】ウクライナも情報の出し方に癖があります。当然、戦時下ですから情報統制はしますし、プロパガンダも流しますが、全体的に、ロシアに比べると嘘は少ないですね。
【黒井】フェイク情報も含めて情報を操作しようという動機は、当然、より隠したいことが多い側に強くあります。事実を知られたら批判されることを“より多く”やっている側ということで、ロシアですね。
それに比べたら、ロシアが侵略行為をし、民間人もたくさん殺しているという客観的な事実を知られたほうがいいウクライナ側が、わざわざ嘘をついてまで情報操作をする動機があまりありません。
もっとも、ウクライナのメディアがロシアに不利な情報を盛ったりする傾向は当然ありますので、やはり情報のクロスチェックは重要です。また、ウクライナ側の情報で特に注意が必要なのは、国防省の情報総局の発信情報です。情報総局は自分たちが有利になるような情報工作が正規の任務なので、そこは慎重に読む必要があります。
■自分たちの非は絶対に認めない
【黒井】たとえば、プーチン重病説でも、ウクライナ国防省情報総局のブダノウ長官自身が頻繁にメディアに登場して「プーチンはガンを含む複数の病魔に侵されている」と発言していました。
彼はロシアへダメージを与える情報工作を任務として行っているので、こうした出方の情報はあくまでウクライナ側が発信する未確認情報という受け止め方が必要となります。ですが、そこをそのまま信用して報道するメディアは内外ともにありましたね。
【小泉】それに加えて、ウクライナ側の情報発信を見ていると、彼らはきわめて負けん気の強い人々だなという印象もあります。何かやらかしても、絶対に間違いは認めない。たとえば2022年にはウクライナの対空ミサイルが国境を越えてポーランドに落ちてしまい、死者が出る事件があったのですが、最後まで認めず、謝罪しませんでした。
「間違いを認めずに突っ張れる自分たちだからこそ、ロシアに負けずにいられるんだ」というような意識が垣間見える時があるように思います。ウクライナの主張だからと、全部は鵜呑みにできないのは大前提です。
さらに、偏向ということで注意したいのは、戦いが起きているのがウクライナ国土だということです。ほんの一部の例外を除けば、現地から上がってくる情報は、ウクライナの軍人や一般市民からの情報が多いので、現地からの情報といっても、ウクライナ寄りにバイアスがかかっている可能性があることは考慮しなければなりません。ロシア側の損失が強調されて伝えられる傾向があります。
■「陣取り合戦」という誤解
――この戦争の今後をどう見るか?
【小泉】この戦争が誤解されていると思うのは、この戦争の焦点が、土地をどこまで取るかと思われていることです。なので、どこに線を引くかということが論点になる。その線の引き方でもめていると思っている人が非常に多いのですね。
でも、現実はそうではありません。いかにウクライナの主権を制約するかということに、ロシアの関心が集中しています。
【黒井】プーチン自身がそう言っちゃっていますので。
【小泉】最近、そのプーチンが言ったウクライナとの和解の話も、ちゃんと元の発言をチェックしてみると「ロシアのウクライナ部分との和解」という言い方をしています。後に「ウクライナ全部が我々のものだ」とも言っている。
いちおう、「ウクライナの主権と独立は認めていますよ」とも言いますが、同時に「ウクライナは中立だというから独立できたんだぞ」ともつけ加えています。政治的手違いでソ連が崩壊しちゃったので条件付きで独立を認めたけれども、あくまでも条件付きなんだぞ、ということですね。
だから、ロシアの民族主義者はこの戦争を「内戦」と呼びます。本来はロシアの一部であるべき、少なくともロシアに逆らわないロシア寄りの中立であるべきウクライナが勝手なことをするから、ロシアの分裂を防ぐために戦っているというロジックがある。そもそも認知の中身がそこまで違うので、そこを擦り合わせて停戦するというのは難しいと私は思います。
おそらく最後までわかり合えることはなくて、どこかで物理的な戦争遂行能力が尽きて、自然休戦するというようなところに持っていくしか、現実には難しいでしょう。
■見え始めたロシアの限界
【黒井】プーチンは今さらやめるとは言えない。損得的な駆け引きでの一時的な休戦はあるかもしれないけれども。
プーチンもうまくいかないものだから、どんどん陰謀論を言い始めていて、「西側がロシアを攻めているので、祖国防衛戦だ」と意味不明なことを言っています。
【小泉】ただ、今の規模と烈度で戦争を続けることは、そんなに長くはもうできないはずです。戦争が4年目に入っていて、財政も苦しいですし、何より予備の武器がそろそろ枯渇するリミットが見え始めています。
結局、2014年以降、そうだったわけです。なので、これは突飛な予想ではなくて、過去10年間のパターンに戻るだけだろうということです。問題は、そこでほっとくとプーチンはおそらくドンバスで小さな戦争を続けながら軍事力を回復して、また攻めてきちゃうわけです。それだけは回避しなくてはいけない。国際的な仲介が難しいとはいえ、次の大規模化を抑制するための枠組みを頑張って作らなければならないのだと思うのです。そこは諦めずに支援し続けるべきです。
■ウクライナの理想的な「負け方」
【黒井】ロシアはプーチンが妥協しないので、自然な戦線の縮小に向かう可能性が高いでしょう。しかし、それも悲観的に可能性を考えると、米国の軍事支援がなくなって、さらに今は増額しようという姿勢の欧州からの支援が、実際には期待どおりにはいかず、たいして増えないとなってしまうと、ウクライナはきわめて苦しくなります。それが最も懸念される今後の可能性予測です。
【小泉】ウクライナが軍事力でロシア軍を追い出しにかかるのが難しいことは、2023年夏の反転攻勢失敗で明らかになりました。ウクライナ国民の多くも土地の割譲をやむを得ないと考えていることが世論調査からは読み取れますし、ゼレンシキーも「占領地域は外交的手段で取り返す」というふうにレトリックを変化させています。
だから土地はもはや問題ではない。問題となっているのは、土地に住んでいる人間の人権保障と国家の主権です。今、ウクライナが目指しているのは、戦場で劣勢に立たされながらも、国家主権を奪われるような負け方をしない=負けを戦術レベルにとどめて、戦略レベルの敗北をしないことなのだと思います。
逆に言えば、国家主権を維持してロシアの継戦能力が尽きるまで持ち堪(こた)えられれば、それはロシアが戦争目的を達成できなかったという意味でウクライナの判定勝ちだと言えるでしょう。
----------
小泉 悠(こいずみ・ゆう)
東京大学先端科学技術研究センター准教授
1982年、千葉県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所客員研究員、未来工学研究所客員研究員などを経て、2022年1月より現職。ロシアの軍事・安全保障政策が専門。著書に『「帝国」ロシアの地政学』(東京堂出版、サントリー文芸賞)、『現代ロシアの軍事戦略』(ちくま新書)、『ロシア点描』(PHP研究所)などがある。
----------
----------
黒井 文太郎(くろい・ぶんたろう)
軍事ジャーナリスト
1963年生まれ。横浜市立大学卒業。週刊誌編集者、フォトジャーナリスト(紛争地域専門)、『軍事研究』特約記者、『ワールド・インテリジェンス』編集長などを経て、軍事ジャーナリスト。専門は各国情報機関の最新動向、国際テロ(特にイスラム過激派)、日本の防衛・安全保障、中東情勢、北朝鮮情勢、その他の国際紛争、旧軍特務機関など。著書に『イスラム国の正体』(KKベストセラーズ)、『イスラムのテロリスト』『日本の情報機関』(以上、講談社)、『インテリジェンスの極意!』(宝島社)、『本当はすごかった大日本帝国の諜報機関』(扶桑社)他多数。近著に『プーチンの正体』(宝島社新書)がある。
----------
(東京大学先端科学技術研究センター准教授 小泉 悠、軍事ジャーナリスト 黒井 文太郎)
現実には、どちらかが弓折れ矢尽きるまで戦闘が続く」という。『国際情勢を読み解く技術』(宝島社)より、軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんとの対談を紹介する――。(第2回)
■国際情勢ネタは「大手メディア」も信用できない
【黒井】タブロイド紙に誤報が多いのは、ウクライナ侵攻に限らず、国際情勢ネタではよくあることですが、怪しい報道はタブロイドに限らない。米国の『ニューズウィーク』、『フォーブス』、『ブルームバーグ』などでも誤報はあります。それと、意外と誤報が多かったのが『ウォールストリート・ジャーナル』ですね。参考になる記事も多いのですが、国際紛争に関しては、未確認で裏取りがなくてもとにかく掲載、という方針っぽいです。
ニュースを追っていくうちに、それぞれのメディアのクセのようなものが経験則で見えてきて、そういう勘所みたいなものがないと、急なニュースの情報の扱いで間違う懸念があります。
【小泉】メディアのそういう性質みたいなものも、だんだんとわかってきますよね。やはり大事なのはこちらの情報の蓄積で、そうすることで相場観が見えてきます。
【黒井】メディアだけでなくて、シンクタンクのレポートでも、全部が全部、正しいわけではないことに留意が必要です。たとえば世界最高水準のイギリスの研究機関・RUSIでも、ウクライナ侵攻直後はロシア側の内部情報について間違った記述がありました。
そうした非公開の分野の内部情報は確認が難しいので、細かいミスはどこでも誰でも起こし得ます。
日々のニュースの背景を知るためには、世界中のメディアやシンクタンクを参考にすべきですが、報道・報告される情報が絶対ではないことを、常に自覚する必要があります。そして、大事なのは複数の情報源で裏取りをする、クロスチェックの作業です。また、情報が更新されたら更新を躊躇(ちゅうちょ)しないことも大事です。
■記事の署名からわかること
【小泉】記者名も大事ですよね。ずっとニュースを追っていると、この分野はこの記者が強いということも見えてきます。
【黒井】アメリカの軍事マニア向けの新興サイト・ウォーゾーンが、ときどきウクライナ国防省情報総局のブダノウ長官の独占インタビューを掲載し、重要な情報を発信したりします。
ウォーゾーンには情報総局に強い記者がいるのですね。この人はもともとフロリダ州タンパの地方紙の新聞記者で、現地の米軍基地の担当で、フロリダ州の退役軍人会とか特殊作戦部隊OB人脈に太いパイプがある。そこから軍事記者をずっとやっていて、老舗軍事メディアの『ミリタリータイムズ』の上級編集者を経て、今はウォーゾーンの記者なのですが、一部の特殊部隊やそのOBにどうも強いコネがあるようです。
ウクライナの情報総局はおそらく米国の特殊部隊とコネがあるし、米軍OBがアドバイザーで入っていると思うのですよね。ウォーゾーンのブダノウ取材は、おそらく記者の個人的なコネだと思います。
【小泉】情報発信者の人名で情報を見ていく、という解像度は必要ですね。
■記者の想像で書かれたプーチンの病状
【黒井】メディアにも、そのときどきの内部の体制での方針というものがあります。未確認でも、飛ばしOKでどんどん載せちゃえというメディアもあります。
プーチン重病説は、英タブロイド各紙では、たとえば『デイリーメール』は「プーチンは血液ガン」「余命3年の宣告」、『デイリーミラー』は「プーチンは視力を失いつつある」と報じています。『ニューズウィーク』では「プーチンはすでに進行ガンで治療を受けている」として、治療歴をかなり具体的に書きました。
執筆者はベテランの軍事ジャーナリストで、米軍に関する著書を私も何冊か読んだことのある著名な人なのですが、ここのところ完全に飛ばしライターになっています。
『ニューズウィーク』はかつてはワシントンポスト系で、『タイム』誌と双璧の信頼性の高いニュース誌だったのですが、売却されて経営者が代わってから、どうも編集方針が変わったようです。
世界最古のイギリスの高級紙『ザ・タイムズ』も飛ばし記事が多かったですが、同紙もあのルパート・マードック(米国の世界的なメディア王)に買収されてから、編集方針が変わったのかもしれません。『ウォールストリート・ジャーナル』もマードック傘下です。
■ウクライナメディアはニュースを誇張しがち
――ウクライナ側の情報の読み方は?
【小泉】ウクライナも情報の出し方に癖があります。当然、戦時下ですから情報統制はしますし、プロパガンダも流しますが、全体的に、ロシアに比べると嘘は少ないですね。
【黒井】フェイク情報も含めて情報を操作しようという動機は、当然、より隠したいことが多い側に強くあります。事実を知られたら批判されることを“より多く”やっている側ということで、ロシアですね。
それに比べたら、ロシアが侵略行為をし、民間人もたくさん殺しているという客観的な事実を知られたほうがいいウクライナ側が、わざわざ嘘をついてまで情報操作をする動機があまりありません。
もっとも、ウクライナのメディアがロシアに不利な情報を盛ったりする傾向は当然ありますので、やはり情報のクロスチェックは重要です。また、ウクライナ側の情報で特に注意が必要なのは、国防省の情報総局の発信情報です。情報総局は自分たちが有利になるような情報工作が正規の任務なので、そこは慎重に読む必要があります。
■自分たちの非は絶対に認めない
【黒井】たとえば、プーチン重病説でも、ウクライナ国防省情報総局のブダノウ長官自身が頻繁にメディアに登場して「プーチンはガンを含む複数の病魔に侵されている」と発言していました。
彼はロシアへダメージを与える情報工作を任務として行っているので、こうした出方の情報はあくまでウクライナ側が発信する未確認情報という受け止め方が必要となります。ですが、そこをそのまま信用して報道するメディアは内外ともにありましたね。
【小泉】それに加えて、ウクライナ側の情報発信を見ていると、彼らはきわめて負けん気の強い人々だなという印象もあります。何かやらかしても、絶対に間違いは認めない。たとえば2022年にはウクライナの対空ミサイルが国境を越えてポーランドに落ちてしまい、死者が出る事件があったのですが、最後まで認めず、謝罪しませんでした。
「間違いを認めずに突っ張れる自分たちだからこそ、ロシアに負けずにいられるんだ」というような意識が垣間見える時があるように思います。ウクライナの主張だからと、全部は鵜呑みにできないのは大前提です。
それと「ロシアの侵略が悪である」という話は全く別に考える必要があります。
さらに、偏向ということで注意したいのは、戦いが起きているのがウクライナ国土だということです。ほんの一部の例外を除けば、現地から上がってくる情報は、ウクライナの軍人や一般市民からの情報が多いので、現地からの情報といっても、ウクライナ寄りにバイアスがかかっている可能性があることは考慮しなければなりません。ロシア側の損失が強調されて伝えられる傾向があります。
■「陣取り合戦」という誤解
――この戦争の今後をどう見るか?
【小泉】この戦争が誤解されていると思うのは、この戦争の焦点が、土地をどこまで取るかと思われていることです。なので、どこに線を引くかということが論点になる。その線の引き方でもめていると思っている人が非常に多いのですね。
でも、現実はそうではありません。いかにウクライナの主権を制約するかということに、ロシアの関心が集中しています。
【黒井】プーチン自身がそう言っちゃっていますので。
【小泉】最近、そのプーチンが言ったウクライナとの和解の話も、ちゃんと元の発言をチェックしてみると「ロシアのウクライナ部分との和解」という言い方をしています。後に「ウクライナ全部が我々のものだ」とも言っている。
彼の頭の中では、ウクライナは国ではなく、ロシアの一部なんです。
いちおう、「ウクライナの主権と独立は認めていますよ」とも言いますが、同時に「ウクライナは中立だというから独立できたんだぞ」ともつけ加えています。政治的手違いでソ連が崩壊しちゃったので条件付きで独立を認めたけれども、あくまでも条件付きなんだぞ、ということですね。
だから、ロシアの民族主義者はこの戦争を「内戦」と呼びます。本来はロシアの一部であるべき、少なくともロシアに逆らわないロシア寄りの中立であるべきウクライナが勝手なことをするから、ロシアの分裂を防ぐために戦っているというロジックがある。そもそも認知の中身がそこまで違うので、そこを擦り合わせて停戦するというのは難しいと私は思います。
おそらく最後までわかり合えることはなくて、どこかで物理的な戦争遂行能力が尽きて、自然休戦するというようなところに持っていくしか、現実には難しいでしょう。
■見え始めたロシアの限界
【黒井】プーチンは今さらやめるとは言えない。損得的な駆け引きでの一時的な休戦はあるかもしれないけれども。
プーチンもうまくいかないものだから、どんどん陰謀論を言い始めていて、「西側がロシアを攻めているので、祖国防衛戦だ」と意味不明なことを言っています。
【小泉】ただ、今の規模と烈度で戦争を続けることは、そんなに長くはもうできないはずです。戦争が4年目に入っていて、財政も苦しいですし、何より予備の武器がそろそろ枯渇するリミットが見え始めています。
どこかで戦争の規模は縮小せざるを得なくなると思います。それでも東部のドンバスなどでは小規模な戦闘が続いていくでしょう。
結局、2014年以降、そうだったわけです。なので、これは突飛な予想ではなくて、過去10年間のパターンに戻るだけだろうということです。問題は、そこでほっとくとプーチンはおそらくドンバスで小さな戦争を続けながら軍事力を回復して、また攻めてきちゃうわけです。それだけは回避しなくてはいけない。国際的な仲介が難しいとはいえ、次の大規模化を抑制するための枠組みを頑張って作らなければならないのだと思うのです。そこは諦めずに支援し続けるべきです。
■ウクライナの理想的な「負け方」
【黒井】ロシアはプーチンが妥協しないので、自然な戦線の縮小に向かう可能性が高いでしょう。しかし、それも悲観的に可能性を考えると、米国の軍事支援がなくなって、さらに今は増額しようという姿勢の欧州からの支援が、実際には期待どおりにはいかず、たいして増えないとなってしまうと、ウクライナはきわめて苦しくなります。それが最も懸念される今後の可能性予測です。
【小泉】ウクライナが軍事力でロシア軍を追い出しにかかるのが難しいことは、2023年夏の反転攻勢失敗で明らかになりました。ウクライナ国民の多くも土地の割譲をやむを得ないと考えていることが世論調査からは読み取れますし、ゼレンシキーも「占領地域は外交的手段で取り返す」というふうにレトリックを変化させています。
だから土地はもはや問題ではない。問題となっているのは、土地に住んでいる人間の人権保障と国家の主権です。今、ウクライナが目指しているのは、戦場で劣勢に立たされながらも、国家主権を奪われるような負け方をしない=負けを戦術レベルにとどめて、戦略レベルの敗北をしないことなのだと思います。
逆に言えば、国家主権を維持してロシアの継戦能力が尽きるまで持ち堪(こた)えられれば、それはロシアが戦争目的を達成できなかったという意味でウクライナの判定勝ちだと言えるでしょう。
----------
小泉 悠(こいずみ・ゆう)
東京大学先端科学技術研究センター准教授
1982年、千葉県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所客員研究員、未来工学研究所客員研究員などを経て、2022年1月より現職。ロシアの軍事・安全保障政策が専門。著書に『「帝国」ロシアの地政学』(東京堂出版、サントリー文芸賞)、『現代ロシアの軍事戦略』(ちくま新書)、『ロシア点描』(PHP研究所)などがある。
----------
----------
黒井 文太郎(くろい・ぶんたろう)
軍事ジャーナリスト
1963年生まれ。横浜市立大学卒業。週刊誌編集者、フォトジャーナリスト(紛争地域専門)、『軍事研究』特約記者、『ワールド・インテリジェンス』編集長などを経て、軍事ジャーナリスト。専門は各国情報機関の最新動向、国際テロ(特にイスラム過激派)、日本の防衛・安全保障、中東情勢、北朝鮮情勢、その他の国際紛争、旧軍特務機関など。著書に『イスラム国の正体』(KKベストセラーズ)、『イスラムのテロリスト』『日本の情報機関』(以上、講談社)、『インテリジェンスの極意!』(宝島社)、『本当はすごかった大日本帝国の諜報機関』(扶桑社)他多数。近著に『プーチンの正体』(宝島社新書)がある。
----------
(東京大学先端科学技術研究センター准教授 小泉 悠、軍事ジャーナリスト 黒井 文太郎)
編集部おすすめ











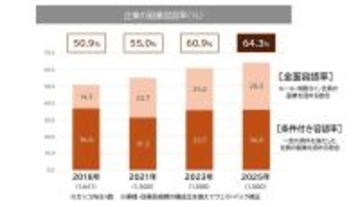

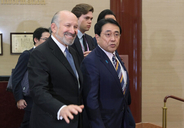


![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
