■なぜ今さらJRが? 羽田アクセス線“参戦”の真意
JR東日本が2031年の開業を目指して羽田空港への「アクセス新線」建設に乗り出した。このニュースに対して、思わず「なぜ今になって?」と感じた読者も少なくないだろう。羽田空港へのアクセスは、これまで京急と東京モノレールの2系統で長らく運用されてきた。JRはなぜ、今さら3番手として乗り込むのか?
1:最終的に目指されるのは、羽田空港から各方面へのアクセス
現在、工事が進められているのは、田町付近から既存の大汐線(現在は休止中)を再活用し、東京貨物ターミナルを経て、最大深度約50mにおよぶシールドトンネルで羽田空港に至るもの。これにより、宇都宮線・高崎線・常磐線など首都圏北部の広域エリアから羽田空港への直通アクセスが可能となり、東京駅からは乗り換えなしで最短約18分という所要時間が実現する。
JR東日本にとっても、自社の広域ネットワークと羽田を結ぶことで新たな収益源の確保を狙う、長期戦略の中核をなす事業とされている。湾岸部の再開発や沿線不動産の資産価値向上など、空港アクセス改善を契機とした都市構造の変革も期待されており、このプロジェクトは単なる「空港への鉄道新線」を超え、首都圏の交通・経済の再編を促すトリガーとなる可能性を秘めているとされる。
■訪日6000万人時代へ…羽田空港の需要はもう限界
2:羽田空港のアクセス路線は足りない
羽田空港アクセス線の整備が本格化する背景には、羽田空港の利用者数が年々増加し、既存のアクセス路線では将来的な需要を捌ききれなくなるという切実な事情がある。
羽田空港は、コロナ禍前からすでに年間8000万人規模の旅客を受け入れており、日本国内で最も利用者数の多い空港である。2020年以降の感染拡大によって一時的に旅客数は落ち込んだものの、その後の需要回復は著しく、2024年には約8590万人に到達。
そしてこの需要は、まだ「回復の途中段階」に過ぎない。政府は2030年に訪日外国人旅行者数6000万人を目指すという明確な目標を掲げており、それに応じて首都圏空港、特に羽田空港には今後もさらなる国際線の就航や増便が求められる。国際航空運送協会(IATA)も、世界的な航空旅客数は年率約3%のペースで成長を続けると予測しており、日本の空港も例外ではない。
実際、羽田空港が将来的に捌くことになると想定される国際旅客は、年間4300万人(乗降客換算で8600万人)規模に達するとされており、現在の国際線発着枠(年12.9万回)では明らかに対応が困難である。試算によれば、これらを処理するには年間45.5万回の発着枠が必要とされるが、羽田単独では今後も約13万回程度にとどまる見通しだ。
つまり、羽田空港は早晩「容量不足」に直面する。仮に訪日外国人6000万人時代が現実になれば、羽田には再拡張=E滑走路新設などの追加整備すら検討が必要になるとする見方も、国の報告書や専門家から出始めている。
■新線に見る“都市インフラ戦略”
そのような中で、羽田空港への新たな地上アクセスを確保する「羽田空港アクセス線」は、単なる利便性の向上策ではない。空港の受け入れ能力と都市全体の輸送キャパシティの底上げを同時に担う戦略的インフラとして位置づけられる。
つまり、インバウンド需要は今後さらに増大していくことが確実であり、羽田空港の利用者数はこの先も伸び続ける。航空機の発着枠やターミナル機能の強化だけでなく、空港へ向かう“地上交通”そのものの強化が急務となっているのだ。
現在のアクセス手段である、京急線と東京モノレールは、一定の輸送力と利便性を担ってきたが、将来の需要拡大に対応するには明らかに限界がある。特に、埼玉・茨城・北関東方面など、羽田から距離のあるエリアからのアクセスには乗り換えが複数回必要となるケースが多く、時間的・物理的なハードルが高い。
現在のアクセス手段である京急線と東京モノレールは、長年にわたり羽田空港と都心を結ぶ役割を果たしてきたが、将来の利用者増に十分対応できる体制とは言いがたい。
実際、国土交通省の調査報告では、羽田空港が東京湾臨海部に位置していることから、「大部分の地域からの旅客が羽田空港まで60分以上のアクセス所要時間を要し、乗換回数も多い」と指摘されている。また、欧米の主要空港と比較して、アクセスの所要時間や乗換回数といったサービスレベルが低いと評価されており、抜本的な改善が求められている。
■北関東からのアクセスに立ちはだかる「乗換の壁」
さらに、特に不便とされている地域として、「東京都西南部・多摩地区・埼玉県方面・千葉県臨海部」が挙げられており、これらの地域は都市人口も多く、羽田空港までのアクセス改善は急務であるとされている。報告書では、「これらの地域からは90分以内で羽田空港に到達できるようにすることが望ましい」として、アクセス改善の方向性を明確に提示している。
また、乗換回数の多さも大きなハードルである。航空旅客は都市鉄道利用者と比べて「乗換に対する心理的・物理的抵抗が大きい」とされており、羽田空港の広大な後背圏からのアクセスにおいて、「乗換回数が数回以上必要である地域が多い」ことは国際競争力の観点からもマイナス要素となっている。
つまり、現在の空港アクセス網は、「都心南部」には強いが、北関東や首都圏郊外からのアクセスに関しては、乗り換えや所要時間の面で構造的な制約を抱えており、羽田空港が“首都圏全体の空の玄関口”として機能するためには、新たなアクセスルートの構築が不可欠なのだ。
だからこそ、こうした構造的な課題を解消し、羽田空港を真に“首都圏全体の国際玄関口”として機能させるには、都心や北関東方面からのダイレクトアクセスを実現できる、新たなルートの整備が不可欠となる。そこで登場するのが、JR東日本による「羽田空港アクセス線」だ。
■JRが羽田を取る理由
JRはすでに、東北本線(宇都宮線)・高崎線・常磐線・中央線・東海道線など、首都圏広域を結ぶ強力なネットワークを保有しており、それらを羽田空港と直結させることで、これまで乗り換えが必須だったエリアからのアクセスをシームレスに変えることができる。さらに、都市鉄道利用者と空港アクセス旅客の動線を分けつつ、輸送サービスの質も高められるという点で、既存路線の負荷分散にもつながる。
新線整備は、単なる利便性向上ではなく、首都圏の交通インフラの再編成であり、羽田空港の“真のポテンシャル”を引き出す鍵ともいえる。
羽田空港アクセス線が数ある構想の中で最も現実味を帯び、実際に着工まで至った理由はシンプルだ。他の構想と比べて、圧倒的に「安く」「早く」実現できる計画だったからである。
このプロジェクトの最大の特徴は、休止中の東海道貨物支線(旧・大汐線)のインフラを活用する点にある。既存の橋りょうや高架橋、用地を最大限再利用することで、フルスペックの新線建設と比べて用地取得のコストと期間を大幅に圧縮している。総工費は約2800億円。3つのルート(東山手・西山手・臨海部)が構想されている中で、まず着手されたのは、最も実現性が高く、効果も即効性がある東山手ルートである。
比較対象としてよく挙げられるのが、蒲蒲線(東急・京急直通構想)や地下深くを通す都営地下鉄延伸案などだが、これらはいずれも用地取得・シールド工法・複雑な交差構造などから建設費が膨らみ、事業採算性も不透明なままだ。
■JR案の決め手は“既存インフラ活用”
さらに、開業目標は2031年度とされており、これは空港アクセス関連の他構想と比べても圧倒的に早い。JR東日本は2023年に国から工事施行認可を受け、同年には本格的な着工に踏み切っている。
また、アクセス新線の終点となる「羽田空港新駅(仮称)」は、第1・第2ターミナルの中間地点に地下駅として整備される予定で、空港施設との接続性にも優れている。旅客導線や乗り換え距離、バリアフリー対応など、インフラ整備における実務面でもJRの構想が最も合理的である。
さらにJR東日本は、単に鉄道を通すだけでなく、駅周辺や沿線の再開発を含めた総合戦略を描ける“都市開発プレイヤー”でもある。東京貨物ターミナル周辺ではすでに施設整備に着手しており、空港アクセス線の整備にあわせて、新たなビジネスエリアや商業開発が動き出す見通しだ。これは、鉄道単体で収支を合わせるのが難しい空港アクセス事業において、周辺不動産と組み合わせた“面的利益”を創出できるJRならではの強みといえる。
■一向に進まない東急・京急直通構想
こうした事業スキームの広さとスピード感、実現力を見れば、JR東日本に軍配が上がるのは当然の流れだった。つまり、羽田空港への新たなアクセス路線において、JR東日本は「限られた時間と予算の中で、最も合理的に、最大の効果をもたらすことができる唯一のプレイヤー」ということができるだろう。
東急・京急直通構想はどうだろう。2022年10月に大田区と東急電鉄が、整備主体となる第三セクター・羽田エアポートライン株式会社の設置にはこぎつけたものの、京急空港線への乗り入れは構想止まりとなった。こうした迷走ぶりを見れば、JR東日本の羽田空港アクセス線が「唯一の現実的選択肢」として浮上したのも頷ける。
しかし、果たしてこれは巨額を投じるだけの価値がある事業だろうか。実のところ、東京駅から羽田空港までのアクセス時間は現状モノレールや京急線で30~35分ほど。これが、新線では18分となる。たしかに、短縮はされるが正直微妙な時間だ。
しかも、この「18分」という数字もかなり怪しい。JR東日本の発表では「東京駅から最短約18分」となっているが、これは恐らく各駅停車ではなく、途中駅を通過する快速的な運行を前提としているはずだ。つまり、途中駅の利用者はさらに時間がかかることになる。
それより何より、この新線の最大の問題は「誰が得をするのか」がまったく見えてこないことだ。JR東日本は「埼玉・群馬・栃木方面から羽田空港へのダイレクトアクセス」を売りにしているが、これは上野東京ラインと全く同じ謳い文句である。
■誰のために新線なのか
上野東京ラインの開業時には、宇都宮線・高崎線から東京駅・品川駅間が乗り換えなしで便利に利用できることが盛んに喧伝されていた。結果はどうなったか。以前は上野駅や、東京駅で始発電車に座れていた利用者が、立ちっぱなしで利用する羽目になった。
そして今度は、この混雑した車内に、スーツケースを抱えた外国人観光客まで乗り込んでくることになるだろう。朝の通勤ラッシュの車内で、巨大なキャリーケースが転がる光景を想像してみてほしい。これが「利便性の向上」なのだろうか。
JR東日本にとっては確かに「合理的」な判断かもしれない。既存路線を活用することで建設費を抑え、新たな収益源を確保できる。競合他社である京急や東京モノレールから乗客を奪うこともできる。だが、それは本当に利用者のためになるのだろうか。結局のところ、この2800億円の巨大プロジェクトで一番得をするのは、JR東日本の株主だけになるだろう。
----------
昼間 たかし(ひるま・たかし)
ルポライター
1975年岡山県生まれ。岡山県立金川高等学校・立正大学文学部史学科卒業。東京大学大学院情報学環教育部修了。知られざる文化や市井の人々の姿を描くため各地を旅しながら取材を続けている。著書に『コミックばかり読まないで』(イースト・プレス)『おもしろ県民論 岡山はすごいんじゃ!』(マイクロマガジン社)などがある。
----------
(ルポライター 昼間 たかし)





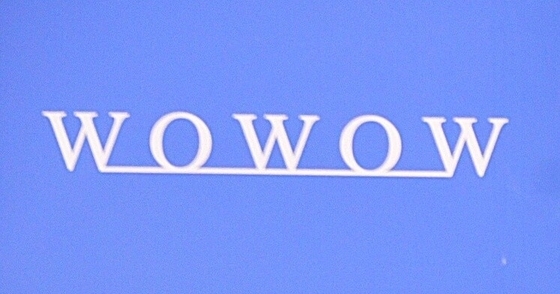









![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
