※この記事は現在発売中の「Rolling Stone Japan vol.05」に掲載されたものです。
アルバム『重力と呼吸』で起きた衝撃的な変化
2018年10月3日に発売されたMr.Childrenの19枚目のアルバム『重力と呼吸』は、衝撃作だった。
前作『REFLECTION {Naked} 』(2015年発売)は全23曲の内容で、Mr.Childrenがプロデューサー・小林武史から離れても様々なサウンドメイクの手札を持っていることを示すものだったし、翌年から始まった約22年ぶりのホールツアーは、チャラン・ポ・ランタンの小春(アコーディオン)と管楽器を連れた8人編成で、「ポップス」「ロック」以外の音楽的要素を色濃く鳴らしながら、繊細に音を積み重ねることで生まれるサウンドスケープをオーディエンスに見せるような公演だった。それから一変、というか、もう「180度真逆のアプローチ」と言っても過言ではないだろう。『重力と呼吸』ではロックサウンドの楽曲が多く並んでいて、ホールツアーで見せた「繊細さ」に加えて「力強さ」を際立たせながら、桜井和寿の歌とギター、田原健一のギター、中川敬輔のベース、鈴木英哉のドラムによるバンドサウンドが鳴らされているのだ。
さらに衝撃だったのは、Mr.Childrenがデビューから26年、ずっと自らの強力な武器としてきた「歌詞」においても大きな変化があったこと。これまでソングライターの桜井は、現実世界のそこらじゅうに落ちている悲しみ、苦しみ、絶望を拾い上げて、それらを凝視しながら、その奥にある希望を見つけ出し、物事の見方を変えることや前に一歩踏み出すためのガソリンとなる言葉を日本中のリスナーへ届けてきた。だからこそMr.Childrenは、90年代から今に至るまで、大勢の人の日常、人生のなかに溶け込み、彩ったり支えたりするバンドとして語られ続けている。しかし『重力と呼吸』では、歌詞がとてもシンプルに綴られており、これまでのように強いメッセージや主張がほとんど含まれていないと感じたのだ。
歌詞の変化に対する驚きにさらなる衝撃を与えたのが、アルバム発売日にネットで公開された桜井のインタビュー内の発言だった。「今はたいがいのものがネットを通じて音と視覚で入ってくる。自分自身が、言葉だけを見て、何かを想像したりイメージしたりする力が落ちてきてるなって感じています。
そういえば、本誌の表紙を飾ってくれていて、Mr.Childrenと対バン経験がありBank Bandとして楽曲をカバーしているRADWIMPSも、ソングライターの野田洋次郎が近いことを語っている。時代の流れを敏感に汲み取る感性を持つ表現者たちは、今の世の中をそう感じ取っているのか……それは、今の社会やカルチャーのあり方として、とても悲しいものではないかと、私も思っていたし同業者の間でそんな話題が上がったりもした。
しかし、そんな時代に対する諦めにも似た気持ちを吹っ飛ばしてくれたのが、11月28日に目撃した『Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸』の横浜アリーナ公演。
Mr.Childrenはなにひとつとして絶望やネガティヴなマインドを持って自分たちの作品の作り方やスタンスを選んでいないし、受け手を突き放そうとも思っていないし、シンプルを突き詰めてこそMr.Childrenにしか示すことができない究極のものがあるのだと、はっきりと証明する公演内容だった。
サポートメンバーに、お馴染みのキーボーディスト・SUNNYと、今ツアーから参加している世武裕子(Key&Cho)を迎えて、「SINGLES」から幕を開けた。アルバムはドラムとベースが重たく鳴るような音作りがされていたが、ライブでも、JENこと鈴木のドラムに自然と目を奪われる。フロアタムを強く叩く音がずしりとアリーナ全体に響き渡り、桜井は、まるでアスリートのような肉体と体力で、一挙手一投足を大きく動かして全身で表現する。1曲を終えた後に湧き上がったオーディエンスの声は、「待ってました!」という声援や、桜井に向けられた黄色い声援以上に、人間の凄みが伝わるようなパフォーマンスや快楽的な演奏を目の当たりにしたときに思わず声が出てしまうような、そういった類の声色だった。

Photo by Shin Watanabe
CD音源ではアコギのダウンストロークと歌だけで始まる「NOT FOUND」が、この日は、桜井に「Mr.Childrenの骨格を鳴らしてる男の音です」という言葉を添えられたJENの激しいドラムからスタート。ロックバージョンにリアレンジされた「NOT FOUND」に登場する「僕」は、これまで何度も聴いてきたこの曲の「僕」とは別の人格、また違う顔を見せてくるようだった。
そんなロックモードのMr.Childrenを引き立たせていたのが、映像と照明の演出だった。

Photo by Shin Watanabe
10曲目「Dance Dance Dance」では、青、緑、赤、黄色、紫など、カラフルなレイザービームが放たれ、次の曲「ハル」では会場全体が鮮やかなピンク色に染まる。ステージ上だけでなくフロア全体の所々に照明が吊るされていて、会場全体を彩るような照明演出が施されていたこともユニークな点だ。
最新技術の映像・照明システムを取り入れながらも、それらが何かを多く語ったり目立ったりするわけではなく、さりげなく、シンプルに、演奏を際立たせるようなものとなっていた。「こんなMr.Childrenのライブ、観たことない」。そんなシンプルな驚きが、このツアーの衝撃的な印象のひとつだった。
本編最後に演奏されたのは「皮膚呼吸」。その演奏前、桜井は次のように語った。
「まだまだ僕ら、やりたいことがあって、理想があって、憧れがあって、夢があって。今からでも遅くない。一歩ずつでもいい、少しずつでもいいから、そこに近づきたい。そんなふうに思って新しいアルバムの制作に入りました。見ればわかる通り、この会場の多くの人がティーンエイジャーではないことを僕は知っています(笑)。でも、ティーンエイジャーじゃなくても、僕らと同じように、まだ夢を持っても、憧れを持っても、理想を掲げてもいいと思ってます。まだまだみなさんにも僕らにも伸び代があるんだと、そう信じています」

Photo by Shin Watanabe

Photo by Shin Watanabe

Photo by Shin Watanabe

Photo by Shin Watanabe
私は、この3日前に、同じ会場でSuchmosのライブを観た。Suchmosのライブ演出も至ってシンプルだったが、彼らの空間は「ライブハウスの延長線」に横浜アリーナがあったのに対して、Mr.Childrenが作り上げていたのは、「ドームやスタジアム公演などを何度も経てきた上でのシンプルな演出空間」だった。どちらにも魅力があるが、それらふたつは、似て非なるものだ。Mr.Childrenの演出と、『重力と呼吸』における歌詞とサウンドのシンプルさは、様々な経験を経てきて、いろいろな思考を巡り巡った結果たどり着いたもので、そこには一流以外は成し得ない深みが帯びている。料理でたとえるなら、熟練の料理人が作った味噌汁には上品な深い味わいがあるように。
本公演の最後に演奏された「Your Song」は、白色の照明で彩られたが、白はこれほどまでに美しくて清らかで神聖な色だったのかと思わされた。
『重力と呼吸』の歌詞には、強いメッセージは含まれていない。しかし、これだけの成功をおさめているバンドの、今も変化と挑戦を止めようとしない貪欲さや好奇心、そして人としての成長が止まることへの恐れを持っているその生き様自体が、Mr.Childrenにしか説得力を持って表現できない強固なメッセージであるように思う。歌詞がシンプルになったと言えど、これまで数多くの名曲を綴ってきた詩人・桜井が書く「シンプル」には、わかりやすい言葉であっても奥行きがあって、そこにはどうしたって彼らの生き様から生まれる生命力が零れ落ちているし、聴いた人が受け取ることのできる道標がある。
そしてMr.Childrenが今回「ロック」に寄ったのは、ホールツアーで音楽的な複雑さや芸術性を追求した上で自分たちが勝負できるのはそこではないことを自覚し、やはりエモーショナルな表現こそがMr.Childrenの魅力でありやりたいことであると気づけたからだという。人は誰しもが、自分の人生や生き方における「正解」を明確には見つけ出せずに歳を重ねていくが、これほどまでに成功をおさめてきたように見えるMr.Childrenさえも自分たちの答えをまだ探し続けているというその姿勢も、強固なメッセージになっていると言えるだろう。
さらに言えば、何事もいつかできなくなるときが来るかもしれないからこそ、今やれることをやりきろうというメッセージも、今のMr.Childrenの表現からは感じ取れる。年齢を重ねていくなかで、この日みたいなアスリート並の体の動かし方、叫び方を、10年後20年後もやり続けられるとは限らない。だからこそ、今、バンドとして表現できる肉体性を存分に発揮しようという想いが見えたのだ。
2月には台湾公演が決定していて、これはMr.Childrenにとって初の海外単独公演となる。ロックバンドとしての強い演奏力と、26年間あらゆることを乗り越えてきた4人の強靭なチームワークと、ずっと極め続けている桜井の歌と、全身の肉体を駆使したパフォーマンス、そしてそれらに滲み出るバンドの生き様は、言語の壁を超えて人から人へと伝わる感動と音楽の醍醐味を生むだろう。















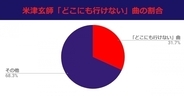




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








