「君にとっての正解は何か? 君は何を信じるか?」ーーRADWIMPSは、今、そう問いかける。
正解のある問いに対しては、自分の親指だけを動かしてネットで検索すればすぐにわかる。しかし、その一方で、正解のない問いに対しては、多様な選択肢が存在し、自分の思う正解を他者にも強要させようとする風潮さえもある。そんな世の中だからこそ、時代が提示する正解だとか、上の世代が言う正解などには惑わされず、自分の目と体と心を使って、自分にとっての「正解」を見つけてそれを信じればいい。RADWIMPSは、人間が持つエネルギーや可能性の尊さを知っているからこそ、そう歌うことができる。
RADWIMPS、結成から17年。結成当時の話、曲の作り方の変化、ドラムの山口智史の無期限休養発表、『君の名は。』の大ヒット、NHK『18祭』などの出来事をたどりながら、山口を含めた4人のメンバーの関係性の変化や、「人と何かを一緒にやる」ということの価値と難しさを、野田洋次郎(Vo, Gt, Piano)、桑原彰(Gt)、武田祐介(Ba)に聞いた。『ANTI ANTI GENERATION』には、ひとりの人間や機械からは生み出すことができない、複数の人間が合わさることで生み出せるエネルギーと肯定感が宿っている。
※この記事は2018年12月25日に発売されたRolling Stone Japan vol.05に掲載されたものです。
いまだにロックバンドが一番かっこいい
ー『ANTI ANTI GENERATION』を聴かせていただいて、いまRADWIMPSの3人の結束力がすごくいい状態にあるのだろうなと感じました。なので今回は「バンドとは?」というテーマをRADWIMPSに投げかけてみたいなと思っていて。
野田:幼稚園の年長から4年半くらいアメリカにいて、小学校5年で日本に帰ってきたんですけど、そのとき(1995年)に日本のバンドの代名詞的なものとしていたのがMr.Childrenやスピッツで。まず日本のことを知っていきたいと思っていたから、「これが日本の音楽なんだ」と思いながらCDを買ったり、ドラマも「これが月9なんだ」とか思いながら観てその延長で音楽を聴いたりしていましたね。

Photo by OGATA for Rolling Stone Japan
ーそこで自分も音楽をやりたいと思ったときに、なぜ「バンド」に憧れたのだと思いますか? たとえば今の10代って、バンドを組むよりもひとりで家でラップトップミュージックを作ってネットに上げることを選ぶ子のほうが多かったりしますよね。
野田:中学生のときは、ギターを覚えてずっと弾き語りをやっていて。バスケ部だったんですけど、部活が終わって家に帰ると、ひたすらギターを弾いて歌ってる、みたいな。もしそのとき身近にラップトップとかGarage Bandがあれば、そういうのを使って自分で全部作っていたんだろうなという感覚はありますね。でも、それがなかったので。あってもせいぜいレコーダーくらい。ちゃんと録音するにはスタジオに行かなきゃいけなくてね。
桑原:そうだったね。
野田:高校に入ってから、くわ(桑原)たちと出会ってバンドを始めて。音楽をちゃんとやるとなると、バンドが一番近道だったんだと思うんです。
武田:あったね。
野田:一番後ろにメンバー募集があってね。
武田:懐かしい。
10代の頃の衝動と憧れ
ー武田さんはなぜ、10代の頃「バンド」に憧れたんだと思いますか?
武田:僕が楽器を始めた経緯としては、小学校の頃の友達がギターを弾いていて、その友達の家へ遊びに行ったときからギターに興味を持って。それでギターを始めたんですけど、そのあと中学校では吹奏楽部に入ったんです。そこでパートの楽器としてコントラバスを渡されて。部活ではクラシックとかジャズをやってたので、いろんなものを聴くようになって、そこからどんどん音楽に興味を持ち始めていった感じです。それで、その部活の先輩たちから「バンドやろうぜ」って言われてやったのが、THE BLUE HEARTSとX JAPANのコピーバンドで。なので最初の憧れのバンドというと、その2組だったのかな。
ーその2組のどういうところに、それほど惹かれたんだと思いますか? その頃の衝動とか憧れが、自分もプロのバンドマンになると決めるところにまで続いていくということですよね。
武田:入口としては、スタジオに入って音を鳴らす、爆音の中にいるというのが、とにかく未知の体験だったし、それがすごく刺激的でしたね。

Photo by Takeshi Yao
ー桑原さんはいかがですか?
桑原:ギターを始めたきっかけは、いとこがギターを持っていてGLAYのフレーズを弾いているのを見てかっこいいなと思って。それで親にギターを買ってもらいました。バンドはその延長で、中学生の頃、みんなでHi-STANDARDのコピーをしたりして。高校になって(野田)洋次郎にバンドに入ってもらって、最初はHi-STANDARDとかグリーン・デイとかをコピーしていたんですけど、すでに洋次郎がオリジナル曲を持っていて。まあ、あのときはオリジナルを作ってるというよりもコピーの延長ってくらいだったかもしれないですけど(笑)、青春時代の早い段階から、コピーとオリジナルが混ざっていたんですよね。
野田:バンドに誘われたときには、すでにライブが決まっていて、ヴォーカルとして出てって言われて。僕は当時のHi-STANDARDとかそんなには聴いていなくて、どちらかというとバンドよりもシンガーとか、親の系譜でフォークやユーミンさんが大好きで、ひとりで弾き語れることをやっていたんですけど。そこからいきなりHi-STANDARDとかのコピーをやるっていう(笑)。あと、そのとき1曲、なぜかオアシスの弾き語りやったんだよね。
桑原:やったね。それが一番よかったってライブハウスの人に言われてた(笑)。
学校とはちょっと違う空間にいる楽しさ
ー野田さんが歌うHi-STANDARD、想像つかないですね。聴いてみたいです。
野田:いわゆる普通のコピーでしたけどね。まあ、やっぱり単純に、バンドをやっているというのが、あの当時は一番かっこいいものだったんだと思うんですよね。
桑原:うん、そうだね。
野田:学校終わりにスタジオへ行ったりとか、制服でスタジオに行って音を鳴らしてる感じとか、それだけでも楽しかったし。部活を自分たちでやってるみたいな感じ。ライブハウスにもちょっと不思議な香りがあるし。大人の世界というか。対バンすれば不思議な先輩方がいっぱいいるし。

Photo by Takeshi Yao
ーそこで桑原さんはバンドに熱中して、17歳のときに高校を辞める決断までするわけですよね。そんなに熱中させたのはなんだったんでしょう?
桑原:洋次郎の作る楽曲がすごくよかったので。それを大会みたいなのに送って出場したら優勝しちゃったんですよ。それで「あ、これで大丈夫かな。人生いけるかな」と思って辞めたんですけど。でも、本当に真似はしないでほしいです(笑)。たまたま僕がラッキーってだけで。あの……本当に、(洋次郎の曲が)すごかったんですよ。今もすごいんですけど、当時聴いたときはもう、びっくりして。「同い歳の人がこんなの作れるんだ」「どうなってるんだろう?」とかいろいろ思いながら、人生を賭けてみようと思ったんですよね。
野田:まあ、思い込みは激しかったよね、くわはね。
桑原:そうですね。視野が狭かったので(笑)、頭の中に選択肢がなかったんですよ。
野田:ギターの音も本当によくなくて。「ペラッペラだよ」とか言っても、それしかないので「めちゃめちゃいいじゃん」とか言っていて。
武田:ずっとリバーブかかってたりとかね(笑)。
桑原:ふふふ(笑)。
野田:くわは、いまだに人生そうやって生きている感じがあるんですけど。当時の延長で物事を決めていってるというか、その時々の正解が正解、っていう。
ーでも、ときには思い込みって大事ですよね。大人になってくると、「Aの選択肢もいいけど、Bの選択肢にもよさがあって、でもCにはこういうメリットがあるよな」って考えがちになっちゃいますけど。
野田:ああ、でも俺は知った上で選びたいですね。くわみたいにはなりたくない(笑)。

Photo by OGATA for Rolling Stone Japan
ー(笑)。では、10代の頃に憧れていたバンド像と今の自分たちには、ギャップがあるか、それとも近づけているかでいうと、どちらの感覚が強いですか?
野田:まったく違うものだよなぁ。10代の頃に描いていたバンド像よりも遥かにかっこいいと思っていますね。あのときに知ってたバンドは、あのときにかっこよかったバンドだし、バンドのあり方も音楽のあり方も変わってきているなかで、それを目指しても勝てるわけがない。だから、あのときに憧れていたバンドよりも全然かっこいいなとは思いますね。
桑原:予想外というか、自分の思い描いていたものよりも遥か上をいく展開ですね。
武田:僕はそんなに「バンド像」を持ってなかったかなと思いますね。どういうふうになっていくのかなって、正直わからなかった。でもやっぱり、自分が18歳のときにあったバンドの形態とは変わってきているなと思います。いわゆる「ギター、ベース、ドラム、ヴォーカル」というバンドサウンドの垣根からどんどん広がっていると思うし、それはすごく面白いことだなって。現に今うちはドラマーが休養しちゃって不在のままだけど、それでもバンドとしてやっているし。
「洋次郎の中で描いている世界をどうやって具現化するか」
ーまさに今作『ANTI ANTI GENERATION』は、「ギター、ベース、ドラム、ヴォーカル」のロックサウンドと、ヒップホップの手法やビートミュージックのサウンドの融合が、かなり新鮮かつ刺激的な内容となっていて。そうやって音の作り方が変わってきたなかでも、RADWIMPSとしては「ロックバンド」という名称で呼ばれることに対してこだわりや美学があると言えますか?
野田:あると思いますね。やっぱり自分は「ロックバンドなんだ」っていう。いろんな音楽が多様化していて、トラックベースの音楽――ビートミュージック、いわゆるクラブミュージックやヒップホップがものすごく身近なところきていて、もしかしたらバンドが一番身近じゃないのかもなって思うくらいですけど。バンドって、一番フットワークが重いんですよ。たとえばイベントがあったときに、「とりあえずDJがいればできる」とか「飛び入りで参加できる」ということではないので。でも、だからこそ、バンドはわざわざ観に行く価値があるものだなっていうふうにしたいし。僕はいまだにロックバンドがかっこいいと正直思っているので、一番かっこいいところに居続けるために、どういう音楽を鳴らそうかなという意識がありますね。
ービートミュージックを取り入れようとしたときに、もっとクールな、エモーショナルや体温をあまり入れない音作りを選ぶこともできたと思うんですね。でも今回のアルバムは、まったくそうはなっていなくて。
野田:そうですね。やっぱり有機的な肉体感がバンドの持ち味だと思うし。同じようにステージに乗ったときに負ける気がしないというか。ヒップホップだったり、DJでターンテーブルを回してたりというのも、それぞれのよさはもちろんあるんですけど、エネルギーの量としてはまだまだ負ける気がしないし、プライドもあるんだろうなと思います。うちらは十何年かけて一つの音を作り続けてきていて、ひとりじゃなく4人で今までずっと作ってきたから。今は5人で音を鳴らしていて、後ろを向いたらドラマーが2人(森瑞希、刄田綴色)いて、横を向いたらこの2人がいるなかで、音を出したときの無敵感みたいなものは、ステージに乗って同列に比べられたとしても負ける気がしないんですよね。
武田:やっぱりライブをやっているときって、すごく特別な時間で。レコーディング・スタジオで弾いているときとは全然違う。5人がガッと向かっているあの空気感が、やっぱりバンドなんだなって。そのフィジカル感と熱量は、今のところバンドが一番なんじゃないかなって思うんですよね。
ー3人のバンド感や有機的な肉体感を音源にも詰め込むために、レコーディングはどうだったのかも聞かせてください。具体的に曲作りはどうやって進めていったんですか?
野田:大きく2パターンにわかれていて。データ上で2人にアレンジしてもらって、俺がそれを聴いて手直しして渡すというやりとりで最後まで構築していった曲もあれば、アレンジを途中までデータでやりとりして、「この方向でいけるね」と決まった段階でスタジオに入ってせーのでレコーディングするというやり方と。後半に録っていた曲は、後者のやり方ですね。「そっけない」「泣き出しそうだよ feat.あいみょん」「TIE TONGUE feat.Miyachi, Tabu Zombie」「tazuna」「HOCUSPOCUS」……あ、半分くらいはそうか。
ー最初に野田さんがデモを渡すときって、どこまで形になっているんですか?
野田:このアルバムでは、歌詞とフル尺の曲ができていることが多かったかな。

Photo by OGATA for Rolling Stone Japan
ーある程度打ち込みもされた状態で、ということですか?
野田:そうですね。してるところも結構あります。ほぼできてる曲とかもあります。
武田:あるね。
野田:「あと、ここを足してよ」って言うときもあるし。でも、弾き語りの状態で渡すときもある。本当に様々ですね。
ーそれを2人に渡して、アレンジが戻ってきたときに、「うわ、こんなふうに戻ってきたのか」という驚きがあった曲って、何かありますか?
野田:また最近作っている曲ではそういうのがあったんですけど、このアルバムではほとんどヴィジョンが見えた状態で渡しているので。どちらかというと要望をしてるよね。
武田:そうだね。洋次郎の中で描いている世界をどうやって具現化するかということが多かったですね。
ーその具現化方法がわからない、ってことはないんですか?
武田:いやいっぱいありますよ(笑)。
桑原:しょっちゅうだね。
野田:大概「違う」って、1回目はなる。
武田:それを受けて、桑原と「うーん……」って(笑)。
野田:昔はスタジオの中でそれを行っていたので、本当にギスギスしてきたりしていて。目の前で「考えて」みたいな瞬発力を俺は欲していたので、一向にできなかったりすると、ただ待つだけの何時間とかがあって。みんなが本当に閉鎖的で窮屈な気持ちになっていくことがよくあったんですよね。それもあって、ある程度までデータでやりとりしようってなって。「いざ鳴らすぞ」という状態になってからレコーディングをするのは、精神衛生上、ものすごくいいんですよ。これは培ってきた業だよね。
武田:そうだね。
桑原:うん、なんとかかんとか続けてきたなかでね。
野田洋次郎がたどり着いた「バンド像」
ー野田さんが作ったものとか、野田さんが「YES」と言ったものに対して、2人は「これはちょっとダサいんじゃない?」みたいになることってないんですか?
野田:たしかに、それ聞きたい。周りの人からもたまに聞かれるんだよね。
武田:それはないなぁ。
野田:ないの? ダメ出しとか、歌詞こうしようよとか。
桑原:「聖域」みたいな感じになっているのかもしれない。そこはもう完全に、100パーセント信用していますね。
野田:たしかに、ある日突然くわに言われたらびっくりするかも。「じゃあなんて書いたらいいの?」って、逆に聞きたくなる(笑)。
桑原:漢字の間違いくらいしか言えない(笑)。
ー桑原さんの野田さんが作るものに対する絶対的な信頼は、結成から今までの17年間、ずっと揺るぎなくあるんですね。
桑原:それは武田も含め、そうですね。
野田:ありがたいですね。俺はずっと、ちょっと違うバンド像を目指していたんです。「全員が無敵」みたいな。最強の布陣で最強のバンドを目指していたけど、それを目指していたら精神的に破綻して。みんなが、それぞれ1回ずつぐらい、「洋次郎、本当にごめん。もう俺、このバンドの足を引っ張るから辞めるね」ってなって、それで考え方を変えたんです。そこからより引き受けるようにしたし、今まで目指していたバンドを1回諦めて、捨てて、この4人だからできるバンド像を目指そうと思って。そういうことを経て今の仕組みにたどり着いたし、当時気付けなかった部分も含めてなるべくいいところを抽出するようにしたし。できてないところを見過ぎないようにしよう、できるところのなかで最大の効果を発揮する何かをやろうって。昔は、大前提として曲作りの段階から一緒にやりたいという気持ちがあったんですけど、曲は圧倒的に自分が責任を持って作る、という切り替えをして。
ーそうやって切り替えられたのって、いつ頃ですか?
野田:『絶体絶命』(2011年3月リリース)あたりからじゃないですかね。だから6、7年前に、バンドを続けることを選んだんです。
ーそれは逆に言うと、RADWIMPSを終了させるという選択肢が、なきにしもあらずだったということですよね?
野田:そうそう。もともとのバンド像を追いかけ続けていれば、違うバンドをやっていたのか、終わっていたんだろうなって思いますよ。
ーそのとき、そちらの選択肢を選ばず、RADWIMPSを続けることを選んだ理由は?
野田:なんですかねえ……もうみんな結婚してたからじゃないですか?(笑)
武田・桑原:(笑)。
ーえ、そんな現実的な答えでいいんですか?(笑) まあもちろん、生活も大事ですけど。
野田:(笑)。一緒にやり続けたいなって、単純に思ったんだと思いますね。一緒にいることを第一に選んだのだと思う。

Photo by OGATA for Rolling Stone Japan
ーたとえばillionで他のプレイヤーと一緒にやったりして、それを経てまたRADWIMPSに帰ってくると、武田さんと桑原さんの個性が見えてくるところもあったりします?
野田:めちゃめちゃありますよ。他をやってると余計にめっちゃ気付きますね。やっぱり2人が入らないとRADWIMPSにはならない、それは間違いないです。最近は2人に預ける部分も増えてきたし、俺が他もやっているぶん、アレンジの部分で絶対的に2人の要素が入らないとRADWIMPSとしての意味がないと思っていて。2人が入ると、「なるほどRADWIMPSっぽいな」って思ったりしますしね。でも桑原が同じことをやり続けると、「いやそれもういい加減飽きたわ」ってなるときもある(笑)。「しかもそれ、俺の真似して始めたやつだろ?」って(笑)。
桑原:このなかでパクリ合いしてます。あ、パクリ「合い」じゃないか、パクってる(笑)。
ー(笑)。バンドとしてのRADWIMPSを語る上で山口(智史)さん(Dr/2015年9月より無期限休養中)のことは避けて通れないと思うんですけど。『ANTI ANTI GENERATION』にも、音としては入っているんですよね?
武田:4曲目「IKIJIBIKI feat.Taka」と、6曲目「洗脳」ですね。「洗脳」は、サンプリングという形ですけど。
ー今あらためて振り返ってみると、山口さんが休養に入ることになって『君の名は。』の劇伴制作やツアーを3人で乗り越えてきたことが、3人の結束力を一段と強めたと思いませんか?
武田:めちゃくちゃあると思いますね。
野田:細かいことを言っていられなくなったよね。家族にピンチが訪れるとケンカしてる場合じゃなくなるじゃないですか。外に向かって達成しなきゃいけないものがあると、どうしたってそうなりますよね。
武田:当時は智史のことですぐに動かなくちゃいけなかったし、メンバーの3人がそれぞれバンドのために何ができるかを自分で考えて進めていた感覚があって。そのなかで結びついたものがあったと思いますね。それまで、あんまり桑原としゃべってなかったかもしれないもんね。
桑原:そうだね(笑)。
野田:武田と智史がやりとりしてたもんね。あとはもう、とにかくサポートの2人がいなかったらすべて始まってなかったから大感謝だし、本当に奇跡的に綱渡りで続けてこられたなと思っています。
武田:うん、本当に奇跡だった。
大ヒットしても「真ん中の端っこにいる」
ーその奇跡を持ってピンチな期間を充実なものへと変えて、その後生み出された前作『人間開花』は、肯定とか光の輝きが宿っていた作品だったと思うんです。今回のアルバムも、色でいうと「黒」みたいな雰囲気の曲も一部あるけれど、全体としては前作に続いて肯定感や前に連れていってくれる感じがとても強くて、何かを一方的に否定することはないアルバムだなと思ったんですよね。それはきっと、バンドの今の精神状態や空気感が表れているものでもあるだろうし、さきほど話してくれた曲作りの仕方が内にこもっていた感じから解かれたからでもあるだろうし。
野田:そう、内にこもっている感はないですね。『人間開花』を作り終えた後、やり切ったという感じはなくて。あのときからアイデアとしてあった曲もあるし、もうすぐに作りたいとも思って、その時点で完全に次に向かっていたので。『人間開花』のおかげで生まれた、バンドの開かれた空気とマインドでさらに突き進みたいし、それを持って違う景色が見たいと思ってやり始めましたね。『人間開花』の後、結構すぐにやってたよね?
武田:うん、本当にすぐだったね。
ー『人間開花』の続編とまでは言わないけど、地続きになっている作品なんですね。
野田:間違いなくそうですね。あそこでリセットして「さあ、次何しよう?」ってことではなかったです。そのなかで、RADWIMPSが次に向かうべき方向としては、こっちだなっていうことで。バンドの肉体的なサウンドと、ビートが強調されたものを、いま俺らなりに融合して面白いものを作るとしたらこうだっていう道筋が見えたんだと思います。「洗脳」は『人間開花』の直後に作っていたんですけど、「カタルシスト」もそうだし、「NEVER EVER ENDER」のアイデアも実は2017年ぐらいには出来上がっていたので。
ー2016年には「社会現象」とまで言われた『君の名は。』があって、『紅白歌合戦』にも出場して、RADWIMPSというバンドが大衆音楽の真ん中に立ったと思うんですけど、それ以降の楽曲、つまりこのアルバムの曲を作る上で、そのことが何か3人の意識や楽曲の作り方に変化を与えた部分ってありますか?
野田:まったくないですね。
桑原:曲を見たら……(笑)。
武田:まったくないよね。
野田:大衆歌がないですからね(笑)。

Photo by Takeshi Yao
ーえ、そんなことはないでしょ。
野田:俺らは真ん中の端っこにいたいっていうのがずっとあって。真ん中の役割のバンドはもっとたくさん適任がいるから、僕らではない。俺らが目指すロックバンド像は真ん中ではないんです。
ーあれだけのヒット曲を出しても、その意識は昔からずっと変わらないんですね。
野田:昔から変わってないですね。……俺らじゃないよね?(笑)
武田:違うよね(笑)。
ー2016年以降、確実にリスナーの数は増えているし、それら大勢のリスナーをちゃんと引き連れながら肯定感を持って前に進もうという姿勢が今作では強いなと思ったんですよね。
野田:それはすごくあります、今のバンドのモードはそうですし。ただ僕の意識としては、アルバムごとに離れていってしまうお客さんもいるけれど、ずっとコアで僕らを支えてくれている人がバンドとともにある気がして。そこを見失うと終わっちゃう気がするんですよね。まず、『君の名は。』は、僕らは音楽をやっているだけだし、付属品でしかないので、あの現象で知ってくれたりあの曲で来てくれたりした方は、バンドにとってご褒美とかボーナスみたいなものだと思っていて。あの曲で好きになってくれた人が、必ずしもRADWIMPSの他の曲を聴いて好きになってくれるとは到底思えないので、そこがコアになることはないというか。なので、そういう意味でも、僕らが今真ん中にいるということはないのかなと思っています。やっぱり自分たちは、アルバムタイトルじゃないですけど、真ん中に対してアンチテーゼを持ったスタンスでいたいっていう気持ちがどこかありますね。
ーRADWIMPSとillionって、サウンドメイクでいうと今ははっきり境界線があるものではなくなってきているのかなと思っていて。でも、歌詞の書き方や使われている言葉は、明確に違いますよね。そこは、やっぱりRADWIMPSが背負ってるものがあるからこそ、言葉を選んでいるんじゃないのかなと思ったんですけど。
野田:ああ、そうですね。あっち(illion)は「抽象画」という以上に抽象というか。自分の中から出てきた言葉をそのまま言っているだけで。RADWIMPSっていうのは、一つの命題みたいなものに対して僕なりの答えを導き出そうとする感覚が強いなとは思います。意味あることを言うのが疲れるとillionで書く。風呂入ってるか服着てるかって感じかな。……うん、そうですね、歌詞は全然違います。
アンチテーゼを掲げるだけではもうダメ
ー『ANTI ANTI GENERATION』は、最後「正解(18FES ver.)」で締めくくられていて。これはNHK『18祭』のために書き下ろした楽曲であり、実際あの場で1000人の18歳の人たちと歌ったものがそのまま収録されています。『18祭』は、RADWIMPSにとってどういう経験だったと言えますか?
武田:すごかったですね。普通に過ごしていたら18歳の子たちと出会うことって、そんなにないので。
野田:いかがわしいことがない限り? くわ、大丈夫だよね?
桑原:うんうん(笑)。

Photo by Takeshi Yao
ーやばいやばい、パパラッチが来ちゃう(笑)(9曲目「PAPARAZZI~*この物語はフィクションです~」ではパパラッチのことを歌っている)。
武田:しかも18歳の子たちが1000人も集まって、同じ楽曲を作り上げるというのは、すごく大きな体験で。あそこにあった熱量は、本当にあの場でしか体験できないものだったし、あの場にいれたことを今後も誇りに思えると思います。しかもそれがアルバムに入るところまで来るっていうのは、すごいなって。
桑原:一生に1回の体験だったし、本当にやってよかったなと思いましたね。もう1回やるってなっても、あの感動は生まれないなと思っていて。
野田:でも打ち上げで、「もう1回やってくださいね」って言われたよね。
桑原:言われたね。
野田:「同じ曲でいいですか?」って俺言ったもん。「この感じはもうできないですよ」って(笑)。
ーあの経験を通して、下の世代に対する意識が強まった部分もありますか?
野田:うーん……。正直、15歳からバンドをやっていて、このメンバーとは18歳からやっていて、バンドをやってるとそんなに景色が変わらないなとは思っていたんですけど。
武田:まあそうだね。
野田:スタジオで曲作って、とか。あまり変わらないと思っていたんですけど、意外と歳取ったんだなとは思って。生で18歳を見ると(笑)。
桑原:ああ、18歳は質感が違うからね(笑)。
野田:質感って(笑)。でも、変わった部分にも、変わらない部分にも気付かされました。18歳って、迷いのなかにいる年齢だと思うんですよ。ゾッとするくらい人生って恐ろしく長くて怖いなとか、自分って何もないんじゃないかと思って絶望する感じとか、世界にとって自分なんてなんでもない存在なんだなと思って自分の小ささに怯える感じとか。三十何年生きているのとはわけが違って。でも、ビクビクしながらも、「何かしたい」っていうあのエネルギーは、すごいなと思いましたね。
ーそういった10代とか下の世代に対して、何かしてあげようという気持ちが増えた部分もありますか?
野田:いや、「してあげよう」って感じではなかったですね。一緒に何かを歌いたい、表現したいと思って歌うんだったら、彼らと俺らの共通項となる言葉を歌いたいと思ったし。自分たちと一緒だなと思える最大公約数として「万歳千唱」と「正解」の歌があって。結局、生きてる年数は十何年しか変わらないので、まだまだ僕らも迷いのなかにいるし、だからこそ僕から言える言葉を歌いたいなと思っていました。
ー「正解」で歌われている、自分にとっての正解を探すことって、若いときだけの悩みじゃなく、30歳を過ぎても続いてしまいますよね。
野田:そう。あの番組を見て、上の世代の人や同世代の人も反応してくれたのがすごくうれしかったです。
ー今回のアルバム・タイトル『ANTI ANTI GENERATION』という言葉の奥にある想いを聞かせてもらってもいいですか?
野田:アンチテーゼを掲げる世代って、どの時代にもあった気がしていて。いろんなアンチテーゼが常にあって、音楽が担ってきた役割もいっぱいあると思うんですけど。でも、アンチテーゼを掲げるだけじゃもうダメなんだなって思ったというか。それで何がよくなったんだろう、社会の仕組みの何が変わったんだろうと思って。いろんな軋轢をいまだに感じるし。アンチテーゼを掲げるだけじゃ芸がないというか、変える仕組みにはならないんだなと思っているんですよね。なので俺なりのスタンスとして、「ANTI GENERATION」に対するアンチっていう。俺は、ただアンチテーゼを言うだけの思想とか音楽からは離れようと思っているし、自分なりの新しい仕組みとかスタンスを作っていきたいと思ってこのタイトルにしました。
ーアンチテーゼを掲げているだけでは何も変わらないと思ったのは、野田さんの年齢が上がって感じるようになったことなのか、それとも時代のあり方から感じ取ったのか、どちらですか?
野田:なんとなく、僕らのこの時代の空気って、それがある気がしていて。もう今の若者は気付いているんじゃないかな。学生運動なんてほぼ起こり得ないし。諦めも含まれているのかもしれないですけど、クレバーに冷静に見ているなと思うし。でも、若い人たちにエネルギーは間違いなくあり続けているから、それが上手いこと発揮できる思想か何かが必要なんだなと思っていますね。
ー今回のアルバムって、時代や上の世代が提示する「正解」ではなく、「君にとっての正解は何か」「君は何を信じるか」を問いかけているし、「自分で自分に問い続けろ」というメッセージが全体に流れていますよね。
野田:正解がいっぱい提示されている世の中だと思っていて。なんでもググればいいわけだから。昔だったら5年ぐらいかけて「こういうことだったんだ」ってわかったことが、今は2秒でわかる時代で。つまり失敗しない参考書はめちゃくちゃあるんですけど、それって失敗していないだけで、一生自分の正解にはたどり着かないじゃんって。だから今の10代とかは余計に大変だなって思うんですよね。高校の宿題とかも、今は全部ネットに載ってるじゃん? 俺らは一応頑張って考えたりしていたけど。宿題出すほうも、どうしてるんだろうと思って。
武田:たしかに出題するほうも難しいよね。今、ネットのオークションでも売ってるもんね。ゴーストライターが書いた論文をそのまま出すみたいな。
野田:それもう、知識は必要なのか?みたいな話になってくるじゃん。
武田:知恵さえあればいいんだもんね。
野田:そう、「知恵」と「知識」の差がどんどん開いてきているなと思います。
バンド史上最大規模の海外ツアーを経て
ーアジアツアーについても聞かせてください。前作からの2年の間に、アジアツアーを2回まわられていて、2018年はバンド史上最大規模の海外ツアーとなりましたね。この経験はRADWIMPSにとってどういうものでした?
武田:アジアに初めてライブで行ったのが2014年で。そのときも「RADWIMPSを待ってくれている人が、海外にこんなにいるんだ」っていうのを強く認識できて。それからコンスタントに行くようになり、そのたびに待ってくれている人がどんどん増えている気がしています。直接届けに行けるというのは、僕らとしても刺激になるし、喜んでもらえることをやれるのは僕たちとしても喜ばしいし。
野田:それにしてもアジア贔屓だよね、俺ら。
武田:沖縄とかよりも行ってるよね(笑)。
桑原:四国より行ってるね(笑)。
武田:中国のメインランドは去年初めて行ってきたんです。ずっと前からメインランドでもやりたいって話していたんですけど、なかなか実現しなくて。ようやく上海で、しかもアリーナでやらせてもらえることができて。そのアリーナでやったすぐあとに、2018年もちゃんとまわろうということで、今年も大規模なツアーをやらせてもらって。
野田 面白いんだよね。
桑原:うん、面白い。
野田:まだいろんな意味で仕組みができあがってなくて、今一緒になって何かを作っている感じがあって。中国の政府の仕組みとか難しいところもあるのかもしれないですけど、若者たちの音楽を求めるエネルギーとか一緒に何かを作り上げている感じはすごく楽しい。一緒に今の時代を作ってる感じが、僕は好きですね。
桑原:来てくれる人たちがどんどん増えていて、もっともっとこの先可能性があるなってツアーをやっていて思ったし、これからも挑戦していきたいなと思いますね。
武田:本当、刺激になるよね。
ーアジアのオーディエンスって、RADWIMPSのどういう部分を楽しんでくれていると思いますか?
桑原:歌詞は日本より覚えてくれているんじゃないかってくらい。Aメロまで一字一句ね。だから歌詞を間違えられないなって(笑)。
野田:本当、そうだよね。
武田:楽しみ方は国それぞれじゃない?
野田:うん、タイと韓国でも全然違うし。
武田:シンガポールは民族の多い国だから、一つの会場でも民族同士で楽しみ方が違うんですよ。

Photo by OGATA for Rolling Stone Japan
ーそれこそONE OK ROCKのTakaさんとかと、海外活動について話したりします?
野田:いや、まったく。話す?
桑原:たまに。TakaとかToruから、アメリカでの活動の話を聞いたりしますね。
ー今回Takaさんと歌った「IKIJIBIKI feat.Taka」って、それこそ海外に通ずるグローバルスタンダードな曲を一緒に作ることもできたと思うんですけど、結構オリエンタルな感じで、日本のロックキッズたちに向けて歌っているところがある感じの曲だなと思ったんです。
野田:これは、最初Takaに3曲送ったら、「どれもいいじゃん! どれでもいいよ!」って言われて(笑)。
武田・桑原:(笑)。
野田:1曲は丸々英語で、もう1曲は英語と日本語半々くらいでバラードみたいな感じだったんですけど。結局「俺が決めなきゃいけないのか」と思って、すごく迷いましたね。これは、もともと曲自体はあって、誰か一緒に歌ってくれないかなとずっと思っていたんですけど、このタイミングが一番いいんじゃないかなと思って。あんまり考えなくていい曲いうか、とにかく突き抜けて、一緒にやれた喜びが爆発できるといいなって。
武田:うん、爆発してたね。
3人が憧れているロックバンド像
ーRADWIMPSを海外でもっと広げていこうとする意識から、曲作りに何か変化があったりなどしますか?
野田:あんまりないよね。
武田:ないね。
野田:多少英語の曲が増えたのは、間違いなくそういう意識からではあるけど。すでに何回かアジアをまわっていて感じるのは、僕らが日本という場所で、日本語でメッセージを伝えていることが、これだけ他の国にも伝わっていて、そうであるのならこのスタンスはあまり崩すべきではないなということで。今のところそういう意識ですね。
武田:海外から聴いてくれている人は、いま僕らが日本で活動しているものを受け取って評価してくれているから。それをわざわざ変えて寄せる必要もないのかなと思っていますね。
ー最後の質問です。今の3人が憧れているロックバンド像とは、どういうものですか?
野田:もうひとりくらい、背の高い人がいないとバランスが悪いなと思っていて。毎回写真を撮るたびに、ちょっと不格好だなって……ほら、ひとりだけ背高ノッポがいてさ。
桑原:申し訳ない(笑)。
武田:いやあ、もっと伸びたかったねー。
桑原:幼稚感漂うというか(笑)。
野田:もうひとり、パートはなんでもいいから背が高い人が来てくれるとバランスがいいんだよなぁ。……っていうのが悩みですかね(笑)。
ーそんな締めでいいんですか?(笑)
野田:僕にとっての切実な願いはこれで(笑)。
ー武田さん、桑原さんは、いかがでしょう?
武田:10年後、20年後がどうなっているかわからないけど、今のところ僕らは形態も音楽の作り方も変化し続けてこられたから、今まで通り、自分たちのやりたいことに合わせて自分たちを変えていけるような活動ができたらいいなと思います。
桑原:身長は欲しいですけど……(笑)。歳は取ってしまうけど、ライブをやるときは、いつまでも気持ちは若いときのままでありたいなと思いますね。
【衣装クレジット】
野田:ジャケット ¥180,000 ベスト、¥80,000 オーバーオール、¥146,000 シューズ 参考商品(すべてヨウジヤマモト/ヨウジヤマモト プレスルーム TEL:03-5463-1500) 中に着たタンクトップ/スタイリスト私物
桑原:ニット ¥37,000(イロコイ/イロコイ ヘッドショップ TEL:03-3791-5033) 中に着たタンクトップ ¥7,800(ラウンダバウト/ラウンダバウト http://www.roundabout-route.com/) パンツ ¥23,000(ノンネイティブ/ベンダー TEL:03-6452-3072) ブーツ/スタイリスト私物
武田:ポンチョ ¥49,000(タクタク/スタジオ ファブワーク TEL:03-6438-9575) カットソー ¥17,000円、パンツ ¥29,000(ともにヤントル/ヤントル info@yantor.jp) シューズ 参考商品/スズキタカユキ
※すべて税抜価格となります。

Rolling Stone Japan vol.06 掲載
RADWIMPS
野田洋次郎(Vo, Gt, Piano)、桑原彰(Gt)、武田祐介(Ba)。山口智史(Dr)は持病の悪化のため活動休止中。2001年結成、2005年にメジャーデビュー。既存のスタイルに捉われない音楽性、恋愛から死生観までを哲学的に、ロマンティックに描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に大きな支持を受けている。2016年夏公開の、アニメ映画『君の名は。』の音楽全般を担当し、バンドサウンドのみならず劇伴音楽でも多彩な作曲性を発揮し、高い評価を得た(同作にて2017年日本アカデミー賞最優秀音楽賞を授賞)。同年11月23日、最新アルバム『人間開花』をリリース。2017年は全国ツアー「Human Bloom Tour 2017」(全国12カ所21公演)を敢行、その後6月から7月にかけて6都市(シンガポール、ソウル、香港、バンコク、台北、上海)、8公演のアジアツアーを実施し大成功をおさめる。夏にはフジロック・フェスティバルをはじめとする数々のフェスへ出演し、各地を沸かせた。2018年2月に劇場公開されたチェン・カイコー監督作品・日中共同製作映画『空海-KU-KAI-美しき王妃の謎』の主題歌・日本公開版挿入歌を書き下ろした。2018年6月には最新シングル「カタルシスト」をリリース。同月にはアリーナ会場6カ所11公演をめぐるツアーを敢行、7月からは約1年ぶりとなるアジアツアー『RADWIMPS Asia Live Tour 2018』がスタート。前回の6都市に加え、初めて北京と成都でも公演を行い、8都市で延べ4万人を動員する、バンド史上最大規模の海外ツアーとなった。12月12日に待望のニューアルバム『ANTI ANTI GENERATION』をリリース、同日には今年実施されたツアーの模様を収録したLIVE Blu-ray&DVDも発売された。
<INFORMATION>
映画『天気の子』
7月19日(金)全国東宝系全国ロードショー
原作・脚本・監督:新海誠
音楽:RADWIMPS
声の出演:醍醐虎汰朗 森七菜
キャラクターデザイン:田中将賀
作画監督:田村篤
美術監督:滝口比呂志
製作:「天気の子」製作委員会
制作プロデュース:STORY inc.
制作:コミックス・ウェーブ・フィルム
配給:東宝
©️2019「天気の子」製作委員会
https://www.tenkinoko.com/
「ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019」
6月8日(土)長野ビッグハット
6月9日(日) 長野ビッグハット
6月14日(金)アスティとくしま
6月22日(土)千葉 ZOZOマリンスタジアム
6月23日(日)千葉 ZOZOマリンスタジアム
6月29日(土)沖縄コンベンションセンター展示棟
6月30日(日)沖縄コンベンションセンター展示棟
7月5日(金)和歌山ビッグホエール
7月9日(火)大阪城ホール
7月10日(水)大阪城ホール
7月20日(土)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
7月27日(土)宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)
7月28日(日)宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)
8月2日(金)CONVEX岡山
8月3日(土)CONVEX岡山
8月13日(火)マリンメッセ福岡
8月14日(水)マリンメッセ福岡
https://radwimps-ticket.jp/



















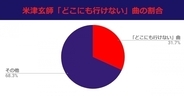


![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








