「俺たちのレガシーはファンが決めればいい、本当に」と、アイアン・メイデンのベーシスト、スティーヴ・ハリスは平然と言ってのける。
アメリカ国内で彼らが獲得した記念の盾はゴールドとプラチナを合わせて7つで、最新アルバム2作品は両方ともアルバムチャートで4位まで上り詰めた。2011年には、アルバム『ファイナル・フロンティア』収録の「エル・ドラド」でグラミー賞を受賞している。そんな数々の功績をあげているアイアン・メイデンの屋台骨はずっとハリスだ。1975年にハリスが中心となってアイアン・メイデンが結成され、それ以来ずっと中心的ソングライターとしてバンドを引っ張ってきたのだ。
それにもかかわらず、ハリスは常に謙虚な姿勢を保ち、バンドの歴史やヒット曲にまつわる裏話を聞いても多くを語らない。「誰かに『死んだあとにどんなふうに記憶されたいか?』ときかれたら、俺たちがかなり良いライブ・バンドだったってことだな、と答えるね」とハリス。「一番興味があるのはそれだから」と。
―アイアン・メイデンがEP『The Soundhouse Tapes(原題)』でデビューして今年で40周年です。当時のことで覚えていることがあれば教えてください。
雪が降っていたのを覚えている(リリース日は1979年11月9日だがレコーディングは1978年12月30~31日)。
―あのEPの1曲目が「Iron Maiden(原題)」でした。これは現在もライブで演奏していますが、この曲を作ったときの思い出はなにかありますか?
あの曲のタイトルが(アレクサンドル・デュマ・ペール原作の)「The Man in the Iron Mask(原題)」の中に登場する拷問器具だってことは周知の事実だよね。(オリジナルは1939年の白黒映画、1998年版はリメイク作品)
―ええ、でも、この曲の歌詞は拷問器具について歌っていません。バンドがどうやってみんなを虜にするのかを歌っています。
うん、それが当時の俺たちの姿勢だったのさ。みんなの前に出て、みんなを虜にするつもりだった。基本的になりふり構わずに突進するってね。俺たち、全員が若造だったし、ハングリーだったし、アドレナリン全開だった。人の前に出て音楽をプレイしようとしていた。
―パンクの影響はどうですか?
ないね。パンクっぽい曲があるから誤解した人もいるようだが、俺たち、実はパンクはまったく好きじゃなかった。後期のパンクスと違って、当時のパンクスは楽器がまったく弾けなかったんだよ。
速弾きを目指した理由
―速弾きを目指した理由は何ですか?
俺たち全員、生粋の速弾きアーティストだと思う。みんなで「じゃあ、これから速く弾こうぜ」なんて話し合って決めたわけじゃない。最初にアドレナリンありきさ。それをステージに持って行くと、レコーディングしたときよりも演奏の速度が上がってしまう。速くなりすぎて手に余ることもあるけど、ライブでのエネルギーというのは本当に素晴らしいんだよ。
―『The Soundhouse Tapes』から3年経たないうちに、バンドがブレークするきっかけとなったシングル曲「誇り高き戦い」を作りました。ご自身もアメリカ西部との特別な結びつきを感じますか?
俺たちはいつも西部劇の映画や本の世界に憧れていたんだ。俺はいろんなことに興味を持っていたけど、あの曲を作った時点でまだアメリカという国に足を踏み入れたことがなかった。でも昔ルイス・ラムール(西部劇の作家)が書いた本をたくさん読んでいて、彼の小説にインスパイアされたんだ。とくに、あの曲の最初の数行の歌詞は、明らかに西部劇の本を読んだからこそ生まれたものだ。あの頃は映画で見て知ることが多かったけど、あとで気づいたのは、俺があの頃思い描いていたアメリカはアリゾナだったってこと。サボテンと乾燥した大地に生きる人々みたいな(笑)。
―あの曲にはアイアン・メイデンの十八番と言える速いリズムが入っています。あれは、西部劇に登場する馬みたいなイメージで作ったのですか?
ああ、そうだと思う。自分では意識していないにしてもね。何らかのイメージを創造しようとするとき、創っているのは感情であり、雰囲気なんだよ。
―では「明日なき戦い」のインスピレーションは何ですか?
(1854年のクリミア戦争中の)軽騎兵の突撃さ。命令を受けて戦地に向かって戦う人物というイメージだ。あの戦争があった時代は戦うことを誰も疑っていなかった。疑うことが許されなかったからね。どんなばかげた戦いでも、馬に乗って戦場に行かなければならなかった。そして、自分に火を吹く大砲に向かって突撃しなきゃいけなかったのさ。戦争中というのは、平常時では思いもつかない狂った命令を出す連中がいたし、俺たちの曲ではそれをテーマにしたものがけっこうあるよ。
―長年戦争に魅了され続けている理由、また戦争をテーマにした楽曲が多い理由は何だと思いますか?
子供の頃から歴史が大好きだったんだ。得意な学科も歴史だったから、そういうところからインスピレーションを受けていることが多い。あとは、人間が同じ人間に対してできる酷い所業や、普通の一般人が平常時なら絶対に陥らない状況に陥った時の状況に強い興味を抱いていることもあるね。
―今回のツアーでは「魔力の刻印」も演奏するようですが、この曲の悪魔的なイメージのせいで、80年代にはアメリカの極左勢力と一悶着ありましたよね。あの曲はどうやって出来たのですか?
映画『オーメン』もインスピレーションの一つだけど、大きかったのは(ロバート・バーンズの)『タム・オー・シャンター』という詩だ。とにかく、昔から読書とホラー映画が大好きなんだよ。
「フィア・オブ・ザ・ダーク」作曲の舞台裏
―セットリストにはあなたが作ったダークな曲がもう一つあって、それが「フィア・オブ・ザ・ダーク」です。あれは実体験に基づいたものなのですか?
いいや、違う。あれを作ったのは、俺がイギリスにある中世のめちゃくちゃ古い家に何年も住んだことがあるからさ。厳密には中世の家じゃなくて、15世紀に建てられた家だ。家がちょっと怖いと言って子供たちが俺に泣きついたものだよ。でも俺は「見てみろ、この家で一番怖いのはパパだぜ」と答えた。そんなふうに怖さをジョークにしていたんだ。
でも、この家は木造で、あちこちにひび割れがあった。
―あなたの楽曲には宗教やキリスト教信仰がテーマのものも多いですよね。例えば「フォー・ザ・グレイター・グッド・オブ・ゴッド~神名に捧ぐ」は今回のツアーでも披露する曲です。最近は宗教についてどんなお考えですか?
あらゆる宗教も、宗教に対するあらゆる考えも尊敬し尊重するよ。みんな、自分の人生を思い通りに生きられるべきだと思う。好きじゃないのは、自分の考えを他人に押し付ける連中だ。「フォー・ザ・グレイター・グッド・オブ・ゴッド」では、「神の名における大義とは異なることをしている人が多い」ということを歌っているんだよ。
―この曲は2006年のアルバム『ア・マター・オブ・ライフ・アンド・デス~戦記』収録で、このアルバムがリリースされたときに、アルバム全曲をライブで演奏しました。あの経験から学んだことは何ですか?
たぶん、俺たちのファンにはアルバム全曲を聴くだけの忍耐力があることと、彼らは全曲通しで聴いても飽きなかったことかな。まあ、飽きた人が一人か二人はいたと思うよ。でも、あれはかなり大胆な試みだと思う。あの頃の俺たちはあのアルバムを心底信じていたんだ。そして、あのライブで演奏する曲を決めながら、俺たちは「どの曲を外そうか? いや、どの曲も外すのをやめよう。全曲演奏して、少しひねりを加えよう」と考えたんだ。とはいえ、あのライブはリスナーにとってはちょっと大変だったと思う、うん。でも、驚くほど上手く行った。俺も楽しんだよ。俺、挑戦が好きだからね。
「メイデンの音楽を聴く多くのファンの第一言語が英語ではない点を、俺は昔から真剣に考えている」
―曲作りをするとき、最初に浮かぶのは曲ですか? 歌詞ですか?
9割が曲だ。一番大変なのが、実際のメロディに歌詞をはめ込む作業だよ。それというものも、俺が作るメロディはきっちり決められているから。ジャズみたいにちょっと曲げるってことができない。だから、メロディにきっちり合うシラブル(音節)の単語に変えないとダメなことも多々ある。メイデンの音楽を聴く多くのファンの第一言語が英語ではない点を、俺は昔から真剣に考えているんだよ。でも、たとえ英語が母語じゃないとしても、最初に耳を奪うのはメロディだ。歌詞を覚える前にね。だから俺は、意味のない言葉遊びじゃなくて、ちゃんとした意味のある良い歌詞にしようと決めているんだよ。
―今回のセットリストで驚いた曲が「イカルスの飛翔」です。これはリード・ヴォーカルのブルース・ディッキンソンとギタリストのエイドリアン・スミスが作った曲で、ディッキンソンは本(シンコーミュージック刊『ブルース・ディッキンソン自伝』)の中で、スタジオ内でこの曲のテンポであなたと意見が対立したせいで、それから30年間ライブでプレイされることがなかったと述べています。これは本当ですか?
それはね、長い歳月リタイアしたままの楽曲がたくさんあるし、俺たちはときどき引っ張り出して演奏するわけだ。「イカルスの飛翔」の場合、あのとき、俺はテンポが少し遅いと思った。だから、今ライブでやっているバージョンはあれよりも数段良い……と俺は思う。最初にレコーデイングしたときにこのテンポでやるべきだったよ。今ではこの曲をプレイするのが楽しい。ちょっと毛色の違う曲だし、ライブではそういう曲をやると楽しいんだよ。
「ウエイステッド・イヤーズ」も同じだった。ある意味、俺たちらしくない曲だったのさ。エイドリアンは俺にも聴かせないで、この曲をテープの終わりの方に隠していたんだ。そして「これは合わないと思う」と言うものだから、俺は「いい曲ならどんな曲でも合う」と言い返した(笑)。あの曲は判断がちょっと難しいと思うが。
―メイデンのアルバムであまり好きではない作品はありますか? 『ノー・プレイヤー・フォー・ザ・ダイイング』はほとんどプレイしていないようですが。
俺たちが特定のアルバムの曲をプレイしないからって、それを深読みするのはよくないね。あのアルバムにはかなり強力な曲がいくつか入っていると思う。それに、他のアルバムに収録された楽曲よりも弱いと思われている楽曲も当然あるわけだ。『ノー・プレイヤー~』の曲なら、俺はそのほとんどを喜んでプレイするよ。あれはかなり強力なアルバムだと思うもの。
―最後にレガシーについてですが、アイアン・メイデンは2004年以来ずっとロックの殿堂入りする資格を持っているのに、未だに殿堂入りを果たしていません。それをどう解釈していますか?
殿堂入りしていなくてもべつに気にならないし、そういうことを考えることもない。誰かから賞をもらったり称賛されたりするととても嬉しいけど、そういうことを求めてこの仕事を始めたわけじゃないから。一つも賞をもらえなくても心配で眠れなくなるなんてことは絶対にない。ロックの殿堂だけじゃなくて他のどんな賞でも同じだよ。「この賞が自分に相応しい」とか思うこともない。俺たちが作ったものが評価されたら、それはそれでいいし、評価されなくてもべつにいいってことだよ。



















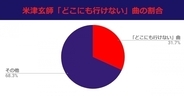


![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








