一「第七作品集」、むっちゃ良かったです。
青木ロビン:良かったですか、ありがとうございます。頑張りました。手応えはありますし、(前作を)超えられるな、みたいな感じを得られたので、レコーディングに入ったみたいな感覚もあったので。
一前作から今作に至るまで、メンバーのことも含めて大きな変化がありました。いつごろからアルバムの構想が?
ロビン:2年前かな。(青木)裕さんの病気が発覚して、余命1年って言われて。元気なうちにアルバムを作ろうっていうのが一応最初のきっかけです。で、今回シングルを出した「砂上、燃ユ。
ーなるほど。
ロビン:メンバーが代わって「前よりも良くなくなった」っていうのは絶対しちゃいけない。裕さんもそれを気にしていたし。だから、超えなきゃいけない。それはすごく意識して作りました。
一裕さんとしては、すでにある程度覚悟していたということですか。
ロビン:本人はもちろん死ぬつもりなんてなくて「治すから大丈夫」って言ってたんです。なんなら「調子がいい」って言ってたんですよ、数日前まで。ほんとに急に「お腹痛い」ってなって、急にバタバタと入院してという感じで。
一裕さんがご存命のときに作ろうとしていた作品のコンセプトは、今回も活かされているんですか。
ロビン:活かされてます。レコーディングする人間が違うんで、いろいろ変わってはしまいますけど、「こういうことがやりたい」っていうコンセプトみたいなのは自分の中でわりと決まってた感じですかね。もっといわゆるプログレっていうのが強くあったんです。ギターの音作りも詰めて話してたんですよね。今までは音がギターっぽくないところにいたんですけど、もっと、ノイズだけでもいいから、周波数がこのへんにあるやつ、立体感のあるやつを録りたいっていうのはずっと話していて。
一なぜそう思ったんですか。
ロビン:僕の子供たちが、普通に(英国プログレ・バンドの)イエスを聴くんですよ。アニメ『JOJOの奇妙な冒険』の影響もあるんですけど。今はパソコンでみんな何でも手に入るじゃないですか。僕らが何したって、気づく人は気づく、捕まえてくれる子は捕まえてくれるし。いつの音楽とか関係ないんじゃないか、単純に自分が一番好きな時代の音をもう一回突き詰めてみようかと思って。(キング・)クリムゾンとかイエスみたいなプログレッシブなバンド像を。もちろんdownyのループ感とかは残しつつ、そっちのエッセンスをもうちょっと入れたいなと。そこで(聴く人が)引っかかってくれればいいし、引っかかんないなら別に、僕らが古い音楽をやっているでいいし。
一これが今の人に通じるかどうかとか、どう聴いてもらえるかを気にしなくなった?
ロビン:そうですね。音作りは絶対に、今ここ(スマホ)で聴こえるようにしなきゃいけないし、マスタリングでも、Spotifyはレベルが小さいからとか、いろいろ気にしなきゃいけないことはもちろんある。でも魂の部分では「気にしないでいいんじゃないの?」と。あとは裕さんの(余命)1年で作んなきゃいけなかったんで、本来は。もしかしたら1年保たないかもしれない、駆け足で作んなきゃいけないときに、ゴチャゴチャ考えずに好きなもんだけバーンと作っちゃおうかな、みたいな。でもまさかこんなに(亡くなるのが)早いとは思わなかったです。
亡くなった青木裕と、新メンバーSUNNOVAの貢献
一予期せぬ急逝によって、アルバムの構想にどういう影響が出ました?
ロビン:単純にギターがいなくなったので、自分の役割が非常にでかくなってしまって。そもそもあんなに上手く弾けないし、練習する時間も必要で。その間もライブはやっていて、バックアップしてくれたサポートのSUNNOVAくんがすごく前向きにやってくれてたんです。彼は中高生の頃にdownyを聴いてた人で、理解力がすごくある。サンプリングで裕さんの音を出すっていうライブ・スタイルだけじゃなくて、もっと新曲をやっていこうって流れの中で、ぜひ彼を正式メンバーにしたいという話をもともとしていて。
一新しいギターを入れようという考え方はなかったんですか。
ロビン:最初にメンバーと話して決めたのは、「ギタリストは入れないでおこう」っていう。彼より上手いギタリストがいたとしても、そこは僕らのこだわりで「ギターじゃない人を入れよう」と。単純に裕さんへの敬意というか。僕らの表せる愛情の一個かなっていう感覚ですかね。極端に言えば、入れるのはピアノでもヴァイオリンでも良かったかもしれないけど。結局僕のところでわりと作り込んじゃうので、彼の音をどう活かすのか、ライブでフィルターをどう使うか、見た目格好いいのかとかも含めてやりとりをずっとしていて。そういうのもすべて含めてメンバーとして一緒にやっていけるなという感じですね。
ーなるほど。
ロビン:ただ彼(SUNNOVA)が、制作の途中、去年の末に倒れちゃって。

downy。左から柘榴(VJ)、秋山タカヒコ(Dr)、青木ロビン(Vo,Gt)、仲俣和宏(Ba)、SUNNOVA(Sampler, Synth)
一SUNNOVAさんが入ることによって、裕さんがいた頃と、サウンドやバンドのあり方って何か変わりました?
ロビン:僕は年下とバンドをやったことがなかったんです。昔のバンドからずっと自分が一番年下で、周りが年上っていう環境だった。その方がラクというか、文句言いやすいじゃないですか。「これやれ、あれやれ」って下の奴が一番うるせぇ、みたいなやり方、それに慣れてたんですけど。今回初めて年下が入って、ええカッコしいじゃないですけど、カッコいいオッサンに見せたいなっていうのはどっかにあるんで。すごい気を使ってますね。うん、もともと彼はdowny好きだし、「がっかりさせんとこう」みたいな。
一裕さんのギターはこのアルバムでもあちこちで使われているわけですか。
ロビン:はい。「砂上~」は完全に彼がツルッと録ってるギターなんで。それを僕が一小節伸ばしたくらいで。「角砂糖」っていう曲のノイズも裕さんのギター。あとは本人の承諾を得てないんで具体的には言わないですけど、何曲かエッセンスとして入ってますね。裕さんの録りためてたノイズみたいなのがちょっと入ってたり。
一アルバム全体としては彼の追悼というか、そういうニュアンスはあったりするわけですか。
ロビン:いや、そこはそんなに。追悼というよりも、僕らバンド自体が一歩前に出るためのアルバムっていう位置づけですかね。裕さんに……聴いてもらいたいって気持ちはもちろんありますけど、それも叶うのか叶わないのかわからないし。僕らがもう一回、メンバーも変えて、止まってた時間をもう一回進めるというきっかけのアルバムっていう感じじゃないですかね。
コンセプトは「現代のプログレ」
一前のものを超えないと意味がないって最初におっしゃいましたけど、超えるために何が一番必要だったんでしょうか。
ロビン:何ですかね? まぁいつも過去の自分たちのアルバムを超えようと思って、毎回毎回そのつもりでやってるんですけど。20年一緒にいたバンドのメンバーがいなくなるのは大きいですよね。あと、亡くなる前の本人に冗談で「僕がいないときに一番カッコいいアルバム作んないでね」って言われてたんで(笑)。「いや絶対作るから」って笑いながら返してましたけど、それをちゃんと明確に作品にできたらいいなっていうのが一番。んー、なんでしょうね、これをやったから前を超えた、っていうのは何ともわかんないですけど。でもさっきも言った立体感のある音像で「いわゆる現代のプログレバンドみたいなことがやりたいな」って、明確なキーワードを初めて僕がメンバーに(伝えて)。今まではそういうのはなかったんです。「僕らがカッコいいのを作るとdownyになる」ぐらいのニュアンスでいたものを、もうちょっと明確に「現代のプログレッシブ・ロックみたいなことをやりたい」って伝えきれたのかなって感じはありますかね。
一「プログレッシヴ・ロック」って、ロビンさんにとってどういうものなんです?
ロビン:もう、イエスなんですけど(笑)。イエスとか、もっと古いクリムゾンとか、ああいう、あの時代にあれがちゃんとポップスとして成り立ってた、みたいな感じのが作りたいなって。ポップスなんですよあの曲が、あの時代は。凄いことですよね。
一「ミュージック・ライフ」の人気投票でELP(エマーソン、レイク&パーマー)が1位だったりしたこともあったわけで(1975年)。
ロビン:そうそうそう。僕も母が普通に聴いてたんで、僕の中ではけっこう普通のことだったんです。でも周りは誰も聴いてなくて、中高生のとき。「なんで? わりと歌えるよ」みたいな。そういう感覚を持った洋楽っていう印象が僕の中にあったんですけど。そういうシンプルなモチーフですかね。
イエスのライブ映像作品『Yessongs』より、1972年のパフォーマンス
一音楽的に非常に凝ったことをやりながらも、ポップに聴かせる、くらいの意味合いで。
ロビン:そうですね。あとループにちょっとこだわりすぎてたんで、今まで。展開の幅がどうしても(狭くなる)。もちろんそこがカッコいいと思ってやってたんですけど、今回はループ、ダンス・ミュージックっていうところから離れて、もうちょっとプログレッシブな展開を。
一あのループ感がdownyの現代性に繋がってたと思うんですけど、そこから離れようと思った?
ロビン:んー、上手く使おうって感じですかね。離れすぎず。結果、けっこうループしてますけど、そこは展開力とかコード進行でもうちょっと持っていけないかなっていうのが。それこそSUNNOVAくんがいることによる、ギターとかでは補えない周波数帯ですね。そういうのの持っていき方とか。そこはSUNNOVAくん、やっぱトラックメーカーなので、バッと周波数見て「ここ足りないんで、ここ僕作ってきまーす」みたいな。バーンと持ってきてくれたりするんで。
一そういう発想は今までなかった?
ロビン:いや、意識してやってましたけど、パソコンできっちり「ここがない」とかいうのはなかったですね。図で出してくれるんで。「ここが今ちょっとないんで、ここに歌入れてみていいですか」とか。「あぁ入れてみよう、入れてみよう」みたいな。
一特定の周波数帯が足りないっていうのは、アレンジした結果気付くものなんですか。なんとなく物足りないな、とか。
ロビン:そうですね。あるいは、わざと空けておく。展開のために。イントロがあって、Aと言われる部分を敢えて抜いてこれを足す、みたいなのはもちろんやる。単純に「低音がないな」と感じることもある。それを楽器で埋めちゃいたくないんですよ。足し算をしたくないんで。単純に「そこにないからプラス」っていうのは、downyの手法としてはカッコ悪いって感覚なんで。そこを補うための同じ一個の楽器の振り幅は、やっぱりPCなんでやりやすい。そういうのは(SUNNOVAが)すごい理解力を持ってくれるんで。今まで逆にいうと、ギターだと「これを出してるとこれは出せないよ」とか「(音が)団子になっちゃうよ」とか「僕のギターと被ってるよ」とか。そこをさらに避けたりできるっていう面白さが今回はあって。そこに立体感が足せる、球体のような音楽が作れるようになったんじゃないかなって思います。
一立体感というのは、具体的にどうやって出していったんですか。
ロビン:んー、レイヤーの重ね方ですかね。やっぱりギター2人だけだと、どんだけ音を重ねてもレイヤーの層ってエフェクティブに聴こえちゃうじゃないですか。それがシンプルにダサいというか。そこを他の楽器で補う。キックとかも今回エンジニアさんがこだわってくれて、マイクの打点だけちょっとズラしたりして。立体感というか、音の作り方とか、アレンジの状態で最初からここに来るようにしようっていう。スタジオではできない、こうやっては作れない感覚というか。
「個々の音を作り込んだ」レコーディング
一レコーディングは具体的にどうやって進めていったんですか。
ロビン:今回は、ざっと(自分が)作ってきて、そのあと具体的にプレイをどうするか考える。さっきも言ったように「ここは(周波数帯の)こういうのが足りないからこうしましょう」っていうやりとりをしたあと、今度は秋山くん(秋山タカヒコ、Dr)のレコーディングをやる。今回は全部ドラムをセパレートで録ったんです。ハットのプレイだけとかキックのプレイだけを加工してデザインされた音作りをしたいと思った。一緒に録ると、どうしても音のカブリが出るから。そういう録り方にして、もっとマスクされた音作りを一個一個やっていこうっていうのがテーマで。そうやってこまごまと録っていった感じですかね。ベースの音だけでも10パターンぐらい。
一ライブバンド的な、ノリ一発みたいなのではないもの。
ロビン:そうですね。今回は一曲も「せーの」がない。3枚目(2003年)とかに近いのかな、録り方の空気としては。ただそれを生バンドでやることに意味がある。最終的にライブでやれる環境に持っていく。ライブで実際に叩けなかったら意味がないから。そしたら打ち込みにしちゃえっていう話にもなるんで。そこはプレイヤーであることが必要だし、ハットだけでもやっぱり人間のやることなんで訛るところがある。それが残せてるから、独特なリズムになってるというか。マッチョ(仲俣和宏)のベースもライブとは違う音作りで何度もやりとりした結果、シンセベースのまま録音して、ライブでベースでやるとこうなるというのを確認しながら作り込んで行きました。
一バンド全体のノリとか勢いを重視するよりも、個々の音を作り込んで音を立体的に配置していくほうが、今回のアルバムには合っていた。
ロビン:そうですね。ライブで一回やってる曲が多いんで、その時にノリというか「ここはもうちょっとベースを突っ込んで弾いたほうが回る感じがするんじゃないか」とかもやりきってるんで。そこは見えてたっていうのはあるかもしれないですね。見えてるから全部バラ録りする淡泊さは、うまく隠せてるんじゃないかなぁという気がします。
一いつもライブで先にやるんですか?
ロビン:いや、珍しいです。ライブで先にやってるっていうのはけっこう珍しいパターン。
一それは裕さんの件があるから、ライブで先行して作っていったということですか。
ロビン:そう。なのと、2年間くらいブランクが空いちゃってるんで、何かやっとかないとさすがにバンドとしても飽きちゃうんで。「次のライブは2曲新曲をやるぞ」みたいなモチベーションが必要だった。あとは作んなくなっちゃうんですよ、どっかで誰かが忙しいと。先に進めるためにも、やっぱライブで一回やっとこうって。
一そうすることで楽曲のイメージは掴みやすくなる?
ロビン:そうですね。僕らみたいに距離が離れた環境でバンドやってると、みんなが同じ方向向いてないと進まなくなっちゃうんですよ。たとえば「今週はずっとこの曲を作ろう」ってやらないと、誰かが海外行っちゃった、誰かがツアー入っちゃったって、2週間経っちゃうともう感覚が(薄れる)。「えっとどこまで進んだっけ?」みたいな感じになっちゃうんで。そこを避けるためにも、ピンポイントでライブに向けて一回ちゃっと作って、ライブでやったけどこうだったからこうしよう、じゃあ次のライブではこうしてみよう、とか。極端にいうと「コントラポスト」っていう曲とか、実は最初にライブでやったときは最後のアルペジオをギターでやってたんですよ。僕がギター弾いてたんですけど、ピアノ弾いてギター弾いて、立ったり座ったり自体も格好悪いし、だったらもうこのままシンセにしようかなぁとか。

Photo by Hana Yamamoto
一実際にメンバー全員が顔を突き合わせてレコーディングする場面はあったんですか。
ロビン:ないです。必ず誰かがいない。僕とSUNNOVAくんは基本メールマターなんで。あと秋山くんも……あー、一回だけあったかな、最初のドラム録りだけ全員いましたね。みんなでああでもないこうでもない、「いいねぇ」とかやってました。レコーディングは基本メールのやりとりなんですけど、特にドラムは、秋山くんが打ち込みでやってくるわけじゃないんで、ちゃんとスタジオにいる時に録らきゃいけない。たとえば秋山くんがスタジオにいて、僕はその時間(沖縄の)家にいるんですよ。で、電話とかで生で叩いたのをそのままもらって聴いて、「ここ、キックはこっちがいい」とか。あとこっちで打ち込み直して「これはどうですか?」「ここ、どうしても2発目は弱くなっちゃうから、ロビンが言ってるグルーヴ出ないよ?」とか。
downyを20年続けてこられた理由
一それにしても、3年半、裕さん亡くなってから2年ぐらいですか。時間はやっぱりかかりましたね。
ロビン:そうですね。やっと。ドラム録りが始まったのが去年の9月くらいかな。それまでほんとに、レコーディングをやるのかっていうところも含めて、悶々と悩みました。「うーん、やるのかなぁ、俺らは」みたいな空気もありつつ。
一それはレコードを作るということのモチベーション?
青木:そうですね。バンドとしてもう一回駒を進める気なのか、っていうのも含めて。
一バンドを続けるか否か、ということですか。
ロビン:どうなんでしょう。誰も言わなかったんで。「休もうか」ってことは結果的には誰も言わなかったんですけど、空気はちょっとありました。「どうするの?」みたいな。まぁ僕がバンマスなんでほんとは僕が言わなきゃいけないんですけど、どっかでまだ僕も「今構想してるこのアルバムがはたしてほんとにできあがるのか?」みたいなのもあったんで。「どう進めるの? SUNNOVAくん入れるの?」とか。メンバーほんとに固めんのか、とか、じゃあ新曲作るのか、とか。ライブだけやってるぶんにはいいんですけど、一緒に制作ができるのかどうか、そもそも制作し始めないとわかんなかったから。それで初めて「大丈夫だ。SUNNOVAくんいいね!」ってなって。それでレコーディングを進めようってなって、3月19日が裕さんの命日なんですけど、3月18日にとにかく間に合わせようっていうのが決まったんですね。「とにかく3月18日発売にしましょう、そこまでに必ず終わらせるために、みんなでもっかい一枚板になってやろうね」っていうところでSUNNOVAくんが倒れちゃったりして大変だったんですけど、まぁそれでもちゃんと最後まで漕ぎ着けてやれたんで。

Photo by Hana Yamamoto
ー今回はこれまで所属していたfelicityではなく、downyの自主レーベルからのリリースですね。
ロビン:今回は自分たちでやろうと。別にfelicityと喧嘩したわけじゃない(笑)。むしろ感謝しかないんで。今もずっとサポートしてくれてるし。そういうのがあって、条件がやっと自分の中で整ったんで、よし行こうみたいな流れでした。
一なるほど。かれこれ20年くらいdownyをやってきてるわけですが、今のバンドの状況をご自分ではどう捉えてます?
青木:単純にメンバーが今すごいポジティブなんです。コロナウイルスの影響で海外のツアーが流れちゃったりもあって、組み立ててたものが一回バラけちゃったので、またいろいろやんなきゃいけないんですけど。今年20周年なんで。せっかくだしいろいろ楽しんでやっていけたらいいなと思っていて。
一20年続くと思ってました?
ロビン:思ってませんでしたねぇ。まったく。まぁ途中で10年休んでますけど、僕らの場合は(笑)。でもどうなんすかね? 実質11年の活動で7枚のアルバムはなかなか頑張ってると思うけど。
一downyみたいな音楽だと、かなり多いほうですね。お手軽にできるインスタントな音楽じゃないのに。
ロビン:多いですよね。今、ちょうどゲネプロ中なんですけど、作った曲をもう一回リハーサルやってる最中で、すごい楽しいですね。合わせていくのもまた楽しいですし。「ライブはちょっとアレンジ変えようか」みたいなアイディアもメンバーから出ますし。
一途中お休みがあったとはいえ、それだけ長いこと続けていられた理由って何だったんですか。
ロビン:オリジナリティがあるから。このオリジナリティだけに固執してたんで、ポンと(シーンの中で)浮いてくれてるんじゃないですかね。浮いてるから、downyってバンドを知る人は、特にミュージシャンなんかは「呼びたいな」とか「一緒にやりたいな」みたいな、声かけやすかったんじゃないかな。やっぱり僕らも声かけられなかったら続けてく意味がわかんなくなる可能性があるんで。どっかで「好き」って言ってくれる人がいて、ライブ誘われたりどこか行くきっかけがあって。Afterhours(downy、MONO、envyが主催している音楽フェス)とかもそうですけど、最近だと僕は「FRIENDSHIP.」っていうサービスのキュレーターをやっていて、若い子たちの音楽を聴いて配信するサイトを手伝ってるんですけど、そういうきっかけ作りがあるのはdownyがあるからだと思いますし。うん、じゃないと、ただの音楽が好きなオッサンになっちゃうんで。僕がいきなり若いバンド呼んでライブ、フェスをすることはできなかったでしょうし。
一自分が音楽をやりたい、演奏をしたい気持ちはもちろんあったと思うんですけど、それ以上に自分が求められてる、必要とされてるという実感は、続ける際にはとても大事なものなんですか。
ロビン:……うーん、少なくとも「カッコいい」って言ってもらえないと厳しいかもしれないですね。誰かに「カッコいいっすね」って言ってもらえないと「俺何やってるんだろう?」って気持ちになるかもしれない。幸いなことに、見向きもされなかったことがなかったんで。
一あるハードコア・バンドのメンバーがね、アルバムを作ったときに、これだけの作品を作って俺はもう満足だ、これが誰にも聴かれなかったとしても全然構わない、みたいな意味のことを言ってたんです。自分が納得のいく作品を作ることが何より大事で、それが他人に届かなくても、評価されなくてもいいと。その気持ちってわかりますか。
ロビン:わかります。わかるんですけど、誰にもカッコいいって言われなかったら、多分すげぇ寂しいでしょうね。僕が曲作るときは「これはカッコいいって言われるぞ」と思っては作ってはいない。あくまで作りたいものを作って自分でカッコいいと思ってるだけ。でも、その自分の感覚はそんなにおかしくないと思ってる。カッコいいの作っていれば、きっと誰かがカッコいいって言ってくれると思ってます。ゼロじゃないというか、誰かが、絶対に。それは信じている。
一自分の感覚がズレてないかどうか。
ロビン:そうですそうです。別に誰にも聴かれなくてもオレはこれを作った、っていう気持ちはめちゃくちゃわかります。僕らも全然そうだと思うし。でも絶対誰かに届いているはずだ、とも思う。
青木ロビン、43歳を迎えた現在の心境
一そうやってご自分でバンドを続けることによって、得られてるものは?
青木:何ですかね……でもいつからだろう、18歳くらいから音楽がやりたくて、一応音楽を始めるわけですよね。で、オリジナルを作り始めて、downyで言うと7枚もアルバムを出せて。それだけ言えばずいぶん幸せというか。出すきっかけがある、発表するきっかけがあるというのは。んー、何を得ましたかね? なんですかね?
一ものすごく孤高なイメージが昔からあるじゃないですか。どことも関係してない、どこにも所属してない、誰ともツルんでない感じ。それは意識的にそうなったわけじゃなくて?
ロビン:そうですね。ほんとに今でこそまだマシですよ。フェスやったりするんで(『Afterhours』)まだマシなんですけど、ほんとに誰もいなかったんで。
一最近お友達ができてきた(笑)。
青木:最近友達ができ始めたんで(笑)。うん、ものすごい突っぱねてるわけでもないんですけどね。でもホームがないというか。どこの人なのかがわからない、僕が。

Photo by Hana Yamamoto
一downyの音楽は、表面的には変わりつつ全体のイメージは変わらない。にも関わらずだんだん広がってきてるのは、周りが変わってきてるんですかね。
ロビン:うーん……どうなんですかね? 僕らが単純に社交的になったっていうシンプルな話になるのかなと思います。秋山くんも「秋山会」っていうのをやったりして、そういうふうに自分がやってることを別の視点から広げようって。広げるって言葉が適切なのかわかんないすけど、自分たちが中心になって何かを起こしてみようっていう動きをやってみて、まぁ単純にバンド誘うなら連絡しなきゃいけないし、初めての子にも、年が下だろうと電話して「はじめまして。実は『Afterhours』に出てほしいんですけど」とかもやりますし。
一自分で連絡するんですか?
ロビン:自分でやります、僕らは全部自分でやるんで。なんかそういうの、いいなと思う。僕が若い頃だったらそうやって誘ってもらえたら嬉しかっただろうなと思いますし。それをできる歳になって良かったなっていうのはありますね。あとは音楽を続けてるという、プライドみたいなのがどっかにあるんですよ。続けられているというか、続けていくのは大変なことなんで、とっても。やっぱり簡単じゃないんで。
一ロビンさん今おいくつでしたか。
ロビン:43です。
一若い頃は良くも悪くも自分のことしか考えられない。でも40、50を超えてくるとだんだん周りも見えてくるし、周りの人のために自分が動こうっていう気にもなってくる。
ロビン:ありますあります。だいぶそれだと思います。まぁ丸くなったと言うんですかね。わかんないですけど。
一でもdownyはdownyですよね。そういう物分りの良さが音楽に出てるかって言ったら、全然出てない。
ロビン:そうなんすよ。よく話しますけど、沖縄に住んでようと1ミリも沖縄っぽい音楽にならない(笑)。全然ならないですよ。僕夏場なんか毎日海行くくらい海が好きですけど、1ミリもそういうのは出てこない。全然わかんないですよね。でもそれが僕が出す音なんでしょうね。
一ご自分の内面から出てくるものがそうであると?
青木:でも内面もそんなに暗い人間じゃないですからね、今は。昔はともかく。むしろ社交的なほうですしね。なんでなんでしょうね? これは自分でもよくわかんないです。ただ作るときはこうなります、何をやっても。弾き語りもこんな感じになります。とにかく根本にあるのは人と違うことがやりたい、ということ。新しい音楽もそうですけど、聴けば聴くほどやりたいことは狭まるんじゃないですかね。だって(他の人に)既にやられちゃってるわけなんで、どんどんどんどん、隙間産業じゃないですけど。たぶんそういうことなんじゃないかなと自分では判断してるんですけど。
一常に新しいことを、常に人とは違うことを。
青木:そうです。downyのコンセプトはそれかもしれないです。ほんとに。常に。
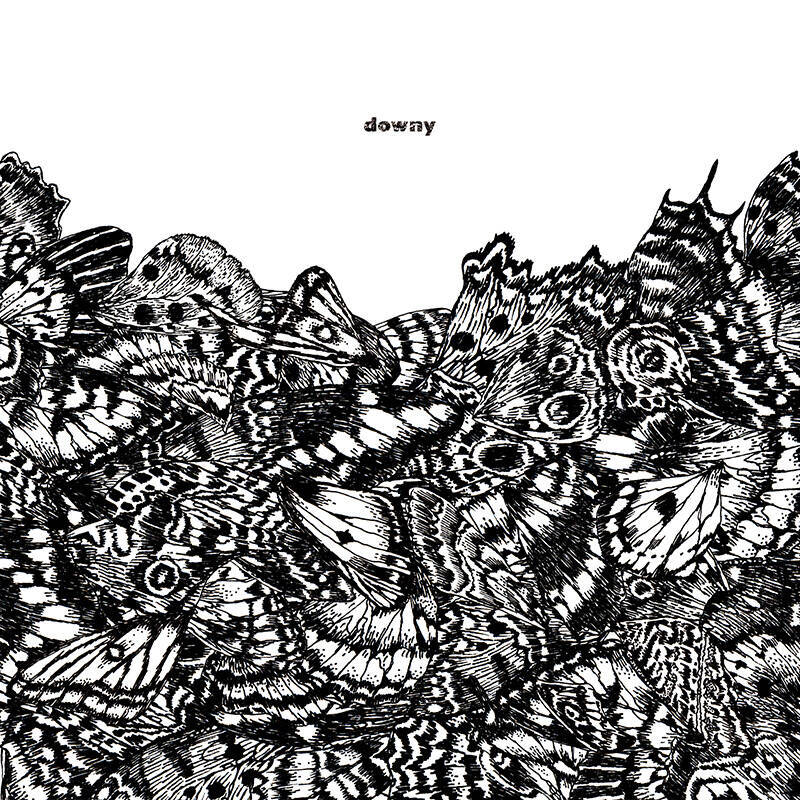
downy
「第七作品集『無題』
2018年3月18日(水)リリース
TOUR『雨曝しの月』
2020年6月6日(土)梅田Shangri-La
2020年6月7日(日)名古屋UPSET
2020年6月13日(土)渋谷WWW X
アルバム特設サイト:
http://downy-web.com/7/

















![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








