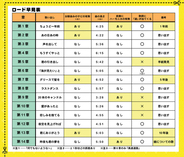6月にリリースされた最新シングル「TUYA」のMV撮影で日本を訪れたロザリア。今世界で最も注目を集めるポップスターにして、大の親日家としても知られる彼女が、日本に恋した理由とクリエイティブの哲学を大いに語る。東京・人形町をロケ地に、カナダ出身の国際的フォトグラファー/映像監督ザビエル・テラが撮影した独占撮り下ろしフォトも必見。
ここではロザリアのカバーストーリー実現を記念して、彼女の歩みを振り返るコラムをお届けする。スペイン出身の彼女が世界中を魅了してきた理由を文筆家/ライター・つやちゃんに解説してもらった。

Photo by Xavier Tera
世界中で最も議論の的になっている存在
同時代に生きていることにこの上ない幸福を感じる――いつの時代も、そういったポップスターは存在する。
改めてロザリアの過去作を振り返ってみると、実に奇妙な歩みに見える。1992年にスペイン・バルセロナで生まれたこの音楽家は、キャリア初期はバーやレストランでフラメンコを歌うシンガーだった。2016年にスペイン人ラッパーのC・タンガナと「Antes de morirme」でコラボレーションしスペイン国内で大ヒットを記録していたりもするが、まだこの時は現在のアバンギャルドな才気は顕在化していない。2017年にリリースしたデビューアルバム『Los Ángeles』もスパニッシュ・ギターを軸にした純正のフラメンコであり、非凡な歌唱力が観察できるものの、ジャンルの壁を解体していくような仕草は見られない。
大きな変化に踏み出したのは2018年の2nd『El Mal Querer』だ。
続いて、高まる評判の中で満を持して発表したのが2022年の『MOTOMAMI』であり、その後の躍進についてはもはや説明するまでもないだろう。各国で評価と売上を高い次元で両立させ、女性アーティストのスペイン語作品として多くの記録を打ち立てた。
とりわけ強い印象を与えたのは、コーチェラ・フェスティバル2023でのステージある。視覚的ギミックを効かせた舞台は、オンライン配信を前提とした音楽フェスでの新たな表現形式を提示する気概にあふれていた。あれだけ大きな舞台で、あくまでストリート感覚に根ざした官能性を世界中にプレゼンテーションするというコンセプト力/身体性/胆力に、皆が感嘆の声をあげたのは記憶に新しい。
この投稿をInstagramで見るColumbia Records(@columbiarecords)がシェアした投稿
数々の魅力的なステージを経ることで、なおのこと作品や楽曲のさまざまな角度での分析・考察も進んでいく。『MOTOMAMI』の衝撃については、レビューサイトMetacriticで2022年に最も多くの投稿され議論されたアルバムになったという事実が示す通り、すでに世界中で多くのリスナーや批評家が言葉を尽くし音楽的・社会的意義を熟議している。そして本作が未だ語り尽くせないのは、全編に渡り際どいバランス感覚が支配しているからではないだろうか。
深い洞察にもとづく折衷、レゲトン・フェミニズムの更新
『MOTOMAMI』を初めて聴いた時真っ先に思ったのは、安定と不安定が自然に同居しているという奇妙さだった。それは、「”ポップ”と”実験”のせめぎ合い」と言い換えるほどには単純化できない複雑なニュアンスであろう。本作が多くの音楽ジャンルを取り入れているのはすでに指摘されている通りだが、強調したいのは、それらが少ない音数によって極めてミニマルな形でまとめあげられているということ。通常、多種に渡るビートやリズムの折衷というのは足し算になりがちで、どこか継ぎ接ぎ感が出てしまう。ところが、ロザリアの制作陣のアプローチは少々異なる。
それに関連して、ロザリアは次のように話す。
フラメンコはもちろん、ラテンアメリカの音楽、レゲトンやダンスホール、あとはジャズやブルーズ……多種多様な音楽からあの作品(『MOTOMAMI』)は影響を受けています。でも、私にとってはそれらの音楽が別々のものには思えないんですよね。
(9月25日発売「Rolling Stone Japan vol.24」より)
この感覚は重要だ。つまり、異なる領域のものをばらばらの存在と捉えず「一体感を持っているように」受け止めるということ。また、それらを可能にしているポイントとして、彼女は当インタビューでしきりに自らの創作活動が「伝統」に根ざしていることを強調する。伝統こそが創作の指針であり、対象を刷新していくための秘訣であると。例えばロザリア自身から語られる日本文化への造詣の深さには舌を巻くが、そういったルーツ理解に対する距離感こそが、前述するところの「”料理”そのものではなく”素材”まで解体したうえでの折衷」を可能にしているのだろう。現代においてジャンルフルイドな音楽の創作は当たり前になったからこそ、彼女の深い洞察にもとづいた手腕は際立って映る。
『MOTOMAMI』が多くの曲で規則正しいリズムを使っている点も見逃せない。実験的な作品と称されるが、一曲の中に多様なリズムを複雑に組み合わせるような手法は実は本作ではあまり採用されていない。たとえば冒頭の「SAOKO」「CANDY」はじめ各所で使われているレゲトンのリズム自体、極めて規則的なものだ。これは、ロザリアが有限性を持ち込んだうえで多様な実験にトライしているから、とも言える。何もない真っ白な無限のキャンパスの上でゼロから実験を始めるのではなく、既存の規則性高いリズムパターンを導入し実験の幅を有限の範囲に絞ったうえで様々な音楽性を投入していく。裏を返せば、これはレゲトンという音楽の強みを活かしているということでもある。現代はあらゆるジャンルのデータベースが揃い何でもありの実験が可能になった時代だからこそ、一定のルールや縛りといった有限性を持ち込むことで面白い試みが可能になることが多い。それは、数多くあるジャンルの中でも、レゲトンという規定のリズムを強く持つ音楽こそが近年ポップミュージックの可能性を推し広げていることからも推察される。
思えば、レゲトンやラテン・トラップという領域は、(ヒップホップがそうであるように)圧倒的な男性優位社会であり、多くの女性アーティストがその中で闘ってきた過去がある。野心あふれる挑戦でかつてない地平を切り拓いているロザリアはフェミニストを自覚してもいるが、その通り、「BIZCOCHITO」で”私はこれからもずっと、あなたのビスコチートにはならない”と歌う。これは2004年にリリースされたWisinとダディ・ヤンキーの曲「Saoko」のオマージュであり、レゲトンへの敬意と、女性としての意志ある表明が同時に宣言されている点がポイントだ。このジャンルにおいては90年代からアイヴィー・クイーンが客体化された女性像に対する異を唱えてきた歴史があるが、ロザリアは強気でバッドな態度を誇示することでそれを音楽へと接続し強度を高め、先頭に立ってレゲトン・フェミニズムを更新している。その躍動感を同時代に追いかけられるというのは、この上ない歓びであろう。

「Rolling Stone Japan vol.24」
予約は上記リンクから
発行:CCCミュージックラボ株式会社
発売:株式会社CCCメディアハウス
2023年9月25日発売
価格:1100円(税込)