「Becoming」に焦点を当てた意図
バーナード・マクマホン監督と脚本兼プロデューサーのアリソン・マクガーティは、レッド・ツェッペリンのドキュメンタリーを作るにあたって、最初から障害があることを承知していた。しかもバンド自身の協力を得て作るとなればなおさらだ。彼らは徹底して自らのレガシーを守り続け、神秘性を保ち、これまで同様の映画企画を数多く退けてきたからだ。マクマホンはこう語る。「ツェッペリンの映画が実現する可能性なんて、まったくないと思っていました」
バーナード・マクマホン監督のコメント映像
さらに難しいのは、映画の中身をどうするかという問題だった。というのも、ツェッペリンの映像は、70年代に『Led Zeppelin IV』を持ってなかった人間を探すのと同じくらい見つけにくいのだ。ロバート・プラントは製作前の会合で、彼らの悪名高きマネージャー、ピーター・グラントの話を持ち出し、こう言った。「これは語り得ない物語だと思う。ピーターは絶対に撮影なんか許さなかったから」。マクガーティによれば、「グラントは容赦なくフィルムを引き抜き、撮影者を会場から叩き出した」そうだ。
それでもマクマホンとマクガーティは制作を進め、『レッド・ツェッペリン:ビカミング』が完成した。
【本編映像】ツェッペリンのパフォーマンス映像
ただし本作には、バンドの歴史のうち最初のアルバム2枚よりあとの話は一切登場しない。ツアーでの放蕩三昧もなければ、「Kashmir」や「Stairway to Heaven」の制作秘話もない。1980年のドラマー、ジョン・ボーナムの死を涙ながらに語る場面もない。1969年のアメリカ・ツアーについて、プラントが「ドラッグとたくさんの女の子」と遠回しに触れる以外に、映画に登場する女性は妻や恋人の映像に限られている。『レッド・ツェッペリン:ビカミング』が焦点を当てるのは、彼らが子供から音楽家へと成長していく形成期であり、その到達点として描かれるのは1970年、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでの勝利のステージだ。マクマホンはこう説明する。「宇宙開発競争をテーマにした映画なら、物語は1950年代から始まり、最終的にはニール・アームストロングとバズ・オルドリンが月に着陸して地球に帰還するところで終わるでしょう。それが終着点というものなんです」
ツェッペリン・ファンにとってはその構成が「困惑(dazed)」かもしれないが、マクマホンによれば、彼とマクガーティは当初から『レッド・ツェッペリン:ビカミング』で「Becoming(成り立ち)」に焦点を当てるつもりだったという。120分の作品を映画館で上映し、音響的に没入できる体験を最大限提供する構想だったのだ。
「その先の話は自分には響かなかったんです」と彼は言う。「1970年までは、起こることすべてが彼らに固有のものでした。4人の個性が組み合わさり、彼らが下す決断や選ぶ道筋がすべて唯一無二で、巨大な成功へとつながっていく。でも、いったん成功を収めてしまえば、その後の出来事は他の成功例と大差なくなってしまう」
マクガーティはこう付け加える。「アルバム、ツアー、アルバム、ツアー、アルバム、ツアー……」
マクマホンもZoom画面でうなずいた。「この人とあの人が仲違いする。誰かがドラッグ中毒になる──そんな話は何度も聞かされてきました。でも、彼らがどういう人間なのかは一度も明かされてこなかった。私生活での彼らを知っている人なんていなかったでしょう」
バンド側の信頼を勝ち取るまで
この限られた時代設定は、バンドにとっても好都合だったはずだ。
「最初に会ったとき、彼らは乗り気ではありませんでした」とマクマホンは認める。「でも絵コンテを一緒に見ていくと、まるで彼ら自身の幼少期を一緒に辿っているような感覚になったんです」。ペイジとの7時間に及ぶ面談で、彼らが結成直後に「トレイン・ケプト・ア・ローリン」をほぼ1時間ジャムしたスタジオの写真を見せたとき、マクマホンはひらめきを感じたという。「ジミーの顔に喜びが浮かぶのを見て、彼がまるで当時に戻ったかのように思い出をたぐり寄せているのが分かりました。その感情が確かに蘇っていて、『ああ、これはうまくいくかもしれない』と心の中でつぶやいているのが伝わってきたんです」
【本編映像】「トレイン・ケプト・ア・ローリン」を最初に演奏したことが語られる
マクマホンはまた、彼が手がけた2017年のドキュメンタリー・シリーズ『アメリカン・エピック』(マクガーティも共同制作)にバンド側が反応したと考えている。20世紀初頭のアメリカン・ルーツ音楽を扱った作品だ。「チャーリー・パットンの系譜に自分たちを位置づけられたこと、そしてその映画が音楽の核心や影響力、その成立を掘り下げる手法を取ったことに、彼らも心を動かされたのだと思います。私たちは『American Epic』と似た語り口を提示したんです。ただし対象は彼ら自身でした」
もっとも、製作者たちがまったく試されなかったわけではない。
バンドの了承を得て、監督と脚本家はツェッペリンの旧友からエンジニアのグリン・ジョンズまで、100人以上の関係者にインタビューを行った。最終的にそれらの会話は主に事実確認のために使われ、映画にはほとんど盛り込まれなかった。「ファンはずっと、メンバー自身が語る物語を待っていたんです」とマクガーティは言う。「彼らが自分の物語を語ったことは一度もなかった。だからこそ、彼ら自身の口で語らせるべきだと思ったんです」。インタビュー中、メンバーの記憶を呼び起こすために、二人は古い建物の写真を見せたり、音楽を大音量で流したりした。
ジョン・ボーナムの秘蔵映像も、プラントは語る「これが僕の人生だ」
とはいえ、予想されていた通り、当時のツェッペリン映像はほとんど残っていなかった。製作陣はやがて、取材嫌いで知られるジョン・ボーナムが70年代初頭に応じた未公開インタビュー3本を発掘し、さらに彼の妹を通じて、父親が撮影した幼少期のボーナムのホームムービーを手に入れることができた。また1969年のバース公演を密かに撮影した映像が存在することを知ると、マクガーティはロサンゼルスからイギリスへ飛んだ。彼女の言葉を借りれば、向かった先は「映画『チキ・チキ・バン・バン』の風車が撮影された、小さな中世の村」とのこと。
【本編映像】ロバート・プラントが故ジョン・ボーナムとの出逢いを語る映像
マクマホンとマクガーティによれば、映画の編集方針については自分たちが主導権を握っていたという。2021年のヴェネツィア映画祭では、ペイジがラフカットの上映に立ち会った。その後ロンドンでの上映会に姿を見せたプラントは、マクガーティに向かって「これが僕の人生だ」と言葉を残した。プラントの家族は、彼が音楽を志したことで両親に家を追い出されていた事実を知らなかったらしく、その反応についてマクガーティは「とても感動的でした」と振り返っている。
では、ツェッペリンの後年を描く続編はあるのか。製作陣ははぐらかす。マクマホンは「そんなことは一度も考えたことがない」と言い切る。「これこそが僕らが作りたかった映画なんです。まるでエベレストに登るような挑戦でした。
伝記映画ではないものの、『レッド・ツェッペリン:ビカミング』は『ボヘミアン・ラプソディ』や『エルヴィス』、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』のように、21世紀に生まれた世代へ”古きロックの神々”を紹介する役割も果たすかもしれない。マクマホンはそれが狙いではなかったとしつつも、そうした可能性は想像できると話す。
「子どもたちが劇場に足を踏み入れ、スピーカーから鳴り響くあの音楽を耳にした瞬間、きっと何人かは思うはずです──『自分にもできるんじゃないか』って。それは一種の号令なんです。君にもできる。必要なのは仲間が3人と、バンドを守るもうひとりだけ。100ものサンプルも、何千人もの弁護士も、作曲のクレジットを15人のエンジニアに分け合う必要もない」
そして彼は付け加える。「それに、あの衣装を着たくない人なんていますかね? 最高にクールじゃないですか」
『レッド・ツェッペリン:ビカミング』
監督・脚本:バーナード・マクマホン(「アメリカン・エピック」)
共同脚本:アリソン・マクガーティ
撮影:バーン・モーエン 編集:ダン・ギトリン
出演:ジミー・ペイジ ジョン・ポール・ジョーンズ ジョン・ボーナム ロバート・プラント
2025年/イギリス・アメリカ/英語/ビスタ/5.1ch/122分
日本語字幕:川田菜保子/字幕監修:山崎洋一郎
原題:BECOMING LED ZEPPELIN
配給:ポニーキャニオン 提供:東北新社/ポニーキャニオン
2025 PARADISE PICTURES LTD.
公式サイト:https://zep-movie.com/















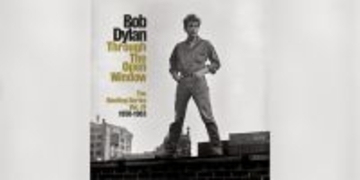










![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








