ラホールで出会った故郷の音楽
―1985年生まれのあなたが育ったパキスタンのラホールは、どんな街だったのでしょうか。
アルージ:90年代のラホールは、美しくてロマンティックで……まるでタイムカプセルに時間が封じ込められたような場所だった。そんな街で、11歳から高校を出る20歳過ぎくらいまでの”大人になる前”の時期を過ごせたのは、本当に幸運だったと思う。今は街を見るとどこも高速道路や地下道とかだらけだけど、当時はとても美しく、緑豊かで、街全体がまるで古い大きな庭園のようだった。ラホールの人たちは音楽やアート、文学といった文化への関心が高い人たちが多かったので、街としての文化度が高かったと思う。
当時は音楽をかけるラジオ局もたくさんあって、ジャンルも色々。新しいものだけでなく、古い音楽も溢れてたし、俳優たちの朗読劇があったりして。地域や社会の中に、文化に対する審美眼のような精神が根付いていて、インディーの音楽やストリート劇、舞台の翻案なども多かった。夜になると、地元の音楽家が集まって古典パキスタン音楽のコンサートが開かれ、家族連れや多くの人が集まっていた。
私も、何に恥じることもなく、複雑に考えすぎることなく、ごく自然体で、パキスタン人として生きていた。そしてパキスタンの──パキスタンになる前、インドになる前、ムスリムをめぐる対立とかもない──歴史や文化や伝統を、ただシンプルに、純粋に、受け止めていたんだと思う。その頃が本当に懐かしい。あの時代に10年間を過ごせたから、余計ラホールという街が今でも大好きなんだと思う。
―10代の頃に体験した90~2000年代のパキスタンの音楽ってどういうものでしたか?
アルージ:インディー系の音楽シーンが盛んで、ポップバンドもラップバンドもいた。西洋で言うところのラップのような、歌詞を早口で話すように歌うスタイルが、パキスタンにも昔から存在してた。ジュヌーン(Junoon)は世界中をツアーした有名なバンドで、私が初めて行ったコンサートも彼らだったけど、国内では地元のポップミュージックも当然人気があった。
詩や音楽の豊かな伝統を持つ国には、自然とそういうシーンが形成されるし、市やラジオ、テレビのプログラムによって支えられ、音楽活動を続けるためのインフラや必要なリソース、資金が提供されていた。ストリングス(Strings)とかヴァイタル・サインズ(Vital Signs)のようなバンドが活動していたし、ごく自然にそういうのも聴いてたって感じ。私が最初に行ったコンサートもジュヌーンで、ごく自然にそういうのも聴いてたって感じ。
ジュヌーン
―過去のインタビューでもパキスタンのカッワーリー音楽の巨匠、ヌスラット・ファテ・アリ・ハーンの話をされてました。カッワーリー音楽は10代のあなたにとっても身近なものだったのでしょうか?
アルージ:両親が車の中でいつもヌスラットを聴いてたから、私も7歳くらいの頃から耳にしてた。ヌスラットは国民的な人気があったから、コーヒーショップでも普通にかかってたし、アビダ・パルヴィーン(Abida Parveen)もよく聴いてた。クラシカル(古典音楽)、セミ・クラシカル、カッワーリー、ガザル……その境界がはっきり引かれていたことは昔からなかった。今もそう。車や店でラジオをかけても、その全部が流れてくる。カイリー・ミノーグの次にヌスラットの曲がかかるというように。生活や日常に織り込まれているというか、私たちにとってのポップミュージックだから。
―興味深いです。日本では伝統的な要素が入った音楽を街や家で耳にすることって、滅多にないんですよね。
アルージ:もちろん、クラシカルな音楽にもいくつかの層があって。たとえば純粋な伝統民謡や極めてクラシカルな音楽──1曲25分もするような長尺曲がコーヒーショップでかかるなんてことはない。
歴史、社会、フェミニズムとの向き合い方
―あなたの音楽の中にあるパキスタン的な要素は、地元で暮らしていた頃に自然に身に着いたものもあれば、アメリカに移住してからリサーチして発見した部分もあるのかなと。
アルージ:そうだと思う。人って慣れ親しんだ土地や言語から離れると、かえって興味が深まるものだよね。私の場合もそうで、ホームシックという形で表れた。ジャズを勉強するためにパキスタンを離れたら、故郷の音楽が恋しくなったの。そこからもっと深く探るようになっていった。ザキール・フセイン(Zakir Hussain)といった歌い手はもともと知ってたけど、シェーナイ(Shehnai)やヴィーナ(Veena)といった古典楽器の奏者まで掘り下げるようになった。といっても、本格的に勉強したわけじゃないけどね。古典音楽には構造やスケール、調性といったルールがたくさんあるけど、そういう知識は全然持ち合わせてない。
中でも特に好きだったのは、ベーグム・アクタル(Begum Akhtar)。彼女は私にとってのスピリチュアルな先生。私が聴き始めた時には、もうこの世にはいなかったけど、聴いているだけで魂が導かれるような気がした。(フォークシンガーの)レシュマ(Reshma)もそんな一人。
バークリー音大に通ってた2000年代初め、まだSpotifyはなかったけど、YouTubeにはたくさんのレアな音源が上がっていた。カッワーリー・グループのファリード・アヤーズ(Fareed Ayaz)を聴き、そこから彼らの父親ムンシ・ラジウッディン(Munshi Raziuddin)も聴くようになり、さらにその前の世代の人たちに遡っていって……まるで音楽の家系図を辿るみたいになって、それが私には面白かったのよ。「すごいボーカリストだな」と思って掘り下げていったら、その母親もすごかったの!
ベーグム・アクタル
レシュマ
―パキスタンの古典音楽で使われる伝統楽器を演奏してみようと思ったことはなかったんですか?
アルージ:それは無理! 2歳から始めてないと、一生かかる世界だから!(笑)。好きなのはバンスリーというフルート。ハリプラサド・チョウラシア(Hariprasad Chaurasia)や、私の1stアルバムで吹いてくれたバキール・アバス(Baqir Abbas)など、素晴らしい奏者が大勢いる。シタールも昔から大好き。
でも、古典楽器を演奏するには、自分は何者で、どこに立っているのかを知る必要がある。ただ「自分にもできる!」だけじゃなく、己を知る……できることとできないことを理解することが大切。
ハリプラサド・チョウラシア
アルージとシタール奏者アヌーシュカ・シャンカールの共演映像
―NYでもパキスタン人もしくはパキスタンにルーツを持つ人との音楽的な交流はありましたか?
アルージ:NYのパキスタン人ミュージシャンは、数としては意外と多くはないんだけど、それでも強いコミュニティはある。もちろん、私はほとんどの人を知っている。でも、住んでいるミュージシャンは少ないし、古典楽器の演奏者は少ない。多くはギグでNYを訪れ、また去っていく、という感じ。それに比べるとインドの古典音楽を演奏する人たちのほうが多いかな。
―インド系の人たちとは交流はあるんですか?
アルージ:もちろん。みんな仲間みたいなものだから。

Photo by Shreya Dev Dube
―ところで『ソング・オブ・ラホール』という映画、ご存知ですか?
アルージ:ええ。
―あの映画は日本でも映画館で公開されたんです。過激なイスラーム原理主義によって音楽が抑圧されて、その苦境から音楽を蘇らせようとする話ですよね。
アルージ:『ソング・オブ・ラホール』は、とあるスタジオのオーナーと、スタジオミュージシャンたちの物語。それまで映画音楽はミュージシャンによって録音されてきたのに、予算が削られ、バーチャルな楽器に取って替わるようになったため、映画音楽で飯を食っていたオーケストラの音楽家たちの仕事がどんどん減ってしまった。彼らは古典音楽でもないしポップスでもないので、完全に路頭に迷ってしまったわけ。スタジオのオーナーは裕福な、フィランソロピスト的な人だったけど、このままじゃスタジオを続けられない、ってことになって。要するに、映画のサウンドトラックの仕事をめぐる現実というか、ミュージシャンたちの葛藤や生活を追った映画だった。パキスタンの音楽業界には、そんなふうに波があって、70年代には特定の人物のおかげで盛り上がったこともあったし、90年代にもいい時期はあったって感じ。
―あなたはガザルをやっていた女性のアーティストに言及することが多い印象ですが、それはガザルが歴史的に女性アーティストが主体的に活躍できた領域だったから、というのも理由にあったりするんですか?
アルージ:私は自分のレパートリーにガザルの、特に詩の要素を取り入れてきた。他にもトゥムリや、他の形式を少しずつ取り入れている。そんなふうにルールに縛られず、ガゼル、カワーリー、トゥムリといろんなジャンルの要素を少しずつ取り入れて、自分だけの自由な「音のキルト」を作れるのは、正式に古典音楽を勉強してこなかったから。でも人はジャンル分けしたがるから、私は「ガザルを歌ってる人」って言われてしまう。
私のごく初歩的な理解では、本来ガザルと呼ばれるには、いろんな形式上の技術的条件――伴奏や歌い方、詩の構造や文脈まで含めて――を満たさなきゃならない。でも私がやってることはそれとは全然違う。だから「ガザルを詳しく語って」と言われても、私には難しい。そこまで知らないし、ガザルは一つではないから。それに女性だけが歌うものでもない。言ってしまうなら、Longing(手に入れてないものへの憧れ)を歌うバラードって感じ。でもバラードと言い切ってしまうのも違うかもしれない。バラードは普通ゆっくりした曲調だけど、ガザルには軽やかに楽しげに ”手の届かない相手やものへの憧れ” を歌った歌もあるから。
これが私なりのガザルのイメージ。そして、そこからいくつかの要素を拝借している。なぜなら、私自身の作品の一番大きなテーマの一つが、LongingとDistance(距離)だから。つまり「それはいずれ起きるのか?」「もうすでに起きてしまったのか?」「それともこれから起きるのか?」……そんなふうに物語を間接的に語る手法が大好きだから、私は。
―なるほど。
アルージ:前振りが長くなっちゃったけど、あなたの質問に答えるなら……私がガザルの詩や歌い方に惹かれたのは、遊び心があって、つかみどころがないからかな。でも、それが女性の領域だったかと言われたら、そうではないと思う。もちろん女性シンガーは大勢いて、その存在は無視できないし、それがこの音楽のすごいところ。名前を挙げ始めたら何時間でもかかるくらい大勢いる(笑)。でも同時に素晴らしい男性シンガーもいるから。
―ちょっとだけ名前を挙げてもらえますか?
アルージ:レシュマ、マダム・ヌール・ジャハン(Noor Jehan)、イクバル・バーノ(Iqbal Bano)、ファリーダ・カーンム(Farida Khanum)、ワーリ・ハミード・アリ・カーン(Wali Hamid Ali Khan)とメフディ・ハッサン(Mehdi Hassan)は男性。アッタウラ・エサケルヴィ(Attaullah Esakhelvi)はパンジャビ・フォークの人だと思う。Spotifyに「Pakistani Baelist」というプレイリストがあるからチェックして。その名の通り、パキスタンのbae=babe(女性)たちのリスト。ベテランから新人まで、人気のある曲からマニアックな曲まで集めてあるから。
「Pakistani Baelist」はアルージ制作のプレイリスト
―パキスタンの伝統に疎いので初歩的な質問ですみません。あなたはガザルの古い詩を取り上げたりしてますが、パキスタンではガザルは一般的に聴かれていて、普通に流れているものなんですか?
アルージ:ええ。
―ポピュラーソングみたいなものと考えてもいいんですか?
アルージ:そう。20歳くらいの子にも「好きなガザルの曲」があるはず。
―あなたはよくフェミニズムに関する言及をしています。調べたらパキスタンにもフェミニズムの強固な歴史があるみたいですね。WAFという団体があったり、早くから女性が首相に就任した国でもあったり、オーラト・マーチ(Aurat March)と呼ばれるデモが行われていたり……そういったパキスタンのフェミニズムの歴史についてあなたはどう見ていますか?
アルージ:パキスタンの女性たちは非常に強く、打たれ強い。彼女たちは「ノー」と言われても引き下がらない。社会のあらゆる分野で素晴らしい活躍をしてきたし、あなたが言う通り、政治の分野にも進出してる。彼女たちの行動を妨げられるものは何もなく、そうさせたのは、何よりも彼女たち自身の力。そう思うのは、パキスタン社会全体として、本当の意味で女性を支えるのだとしたら、まだやるべきことはたくさんあると思うから。もしパキスタンの女性が素晴らしいと言われるなら、それは社会のおかげじゃなくて、彼女たち自身の力なのだと思う。
でも、私はここしばらくパキスタンで起きていることには関わっていないし、こちらに引っ越してきてからは、パキスタンで過ごす時間はほとんどなくて、そんなに振り返ることもなかった。それでも全体的には機能していて、大丈夫そうだという感覚はある。もちろん、昔からずっと続いている問題は相変わらずあって、家父長制は健在だし、ミソジニーも女性への暴力も減ってない。でもそれはどこにでもある問題でしょ。ニューヨークで夜中の3時にタクシーで帰宅する時、私たち女性は無意識のうちに、常に命の危険を感じている。ただ場所によって、その度合いが違うというだけかな。
世界には他にも色々な問題があって、戦争も起きている。フェミニズムの問題も、結局は「自由であるかどうか」ということに尽きる。女性が自由に生きられる権利のための戦いであり、それは今起きているあらゆる問題にも共通している。自由に生きること、やりたいことをできること、そうした人間としての権利や居場所、それがどこであろうと関係なく、皆がそれを求め、戦い、今の状況を作っているんだと思う。
日本に届けるスペシャルな一夜
―最近、たまたまギリシャ人ベーシストのペトロス・クランパニスにインタビューしたんです。ペトロスはあなたの長年のコラボレーターとしても知られています(※今回のアルージ来日公演は不参加)。あなたの音楽にペトロスが必要なのは自分のルーツの伝統も視野に入れたハイブリッド性が共通しているからかなと思ったのですが、どうですか?
アルージ:それが理由だとは思わないけど、確かに私たち、音楽的にお互いが考えてることが、ある程度読めてしまう。言葉でいちいち説明しなくても、楽譜を見せ合わなくても演奏できてしまう。そのことに初めて気づいたとき、「そういうことなんだ!」という閃きがあった。まさに強いエネルギー。それが、あなたが言っていることなのかもしれないかもね。
ペトロスは感覚として、伝統的なギリシャ音楽を自分の中に取り込んでいるけれど、決して伝統的なミュージシャンではない。そしてジャズも深く学んでいる。そういうところが私とまったく一緒。でも面白いのは、私たちが「それはこういうものだ」と名前をつけたり、説明しなかったこと。ただ、自然に起きていることを信じて、楽しんだ。お互いの音楽のテレパシーを信じあった、という感覚。それが感じられる相手がいるということが、ミュージシャンにとってどれほど貴重なことか。
―ビルボードライブでの来日公演では、テリー・ライリーの息子でもあるギタリストのギャン・ライリーも参加するそうですが、どんな感じになりそうですか?
アルージ:ギャンはしばらくポール・サイモンのツアーに参加していたから、彼とまた一緒にできることにワクワクしている。私たちもこの1年間ツアーを重ねてきて、ライブでの表現も進化してきた。きっと新鮮でこれまでとは違うものになると思うし、日本のためにスペシャルなものを用意しようと思っている。ギャンのお父さんが来たりもするのかな。
―え、テリー・ライリーも出るんですか?
アルージ:意味もなくグランドピアノを用意しておこうかな(笑)。まあそれはともかく、とても楽しみ。
【関連記事】
アルージ・アフタブが語る、グローバル・ミュージックの定型に縛られない「余白」の美しさ
アルージのライブにて、ギャン・ライリーのギターソロ

アルージ・アフタブ来日公演
2025年10月28日(火)・29日(水)ビルボードライブ東京
1st Stage OPEN 16:30 / START 17:30
2nd Stage OPEN 19:30 / START 20:30
>>>詳細・チケット購入はこちら
出演メンバー:
Arooj Aftab(Vo)
Gyan Riley(Gt)
Zwelakhe Duma Bell le Pere(Ba)
Engin Gunaydin(Dr)

『Night Reign』
発売中
再生・購入:https://arooj-aftab.lnk.to/NightReign











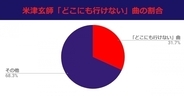






![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








