
TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」月~木曜日の11時から放送中!10月11日(月)「スーさん、これいいよ!」のゲストは、イラストレーターの上大岡トメさんでした!上大岡トメさんですが・・・ ■東京生まれ横浜育ち。東京理科大学工学部建築学科を卒業後、建設会社を経て、イラストレーターになられます。
 そんな「介護の予習」について、さらに詳しいことが上大岡さんの本「マンガで解決 親の介護とお金が不安です」で読めます。
そんな「介護の予習」について、さらに詳しいことが上大岡さんの本「マンガで解決 親の介護とお金が不安です」で読めます。
■移住した山口県から ご両親の遠距離介護をされており、この度、自身の体験をもとに「マンガで解決 親の介護とお金が不安です」という本を出版されました。「親の介護とお金」の不安を介護問題にくわしいファイナンシャルプランナー黒田尚子さんに聞いて、出版されたそうです。「介護なんてまだまだ」「そろそろ介護が必要かも」という人も今からできること、知っておいたほうがいいことあるそうです。ぜひ「介護の予習」を。そこで、今回は上大岡さんに「介護の予習」のポイントを2つ教えていただきました。『介護は、親自身の“お金”でやることが前提!』 上大岡さん自身、一番心配なのがお金だったそうです。 これから介護・医療に、どのくらいかかるのか、そして、足りるのか・・・黒田さんの答えは「介護は、親のお金(年金・資産)の中でやることが大前提」 「だから足ります!」 子育てや教育は期間が見えていますが、介護はどのくらいになるかわかりません。子が無理をしたり、見栄をはっても続きません。ですから、介護にまつわる費用は、親の介護保険や資産でまかなうことが原則です。それに、お金をかければ“いい介護”が受けられるとも限りません。▼介護に必要な3本柱があります。 それは「お金・情報・ネットワーク(人脈)」このバランスが大事です。
例えば、高齢者ホームなどは、お金だけあっても、合う施設に出会えるわけではありません。 どの施設がいいのか。地域の中での情報や人脈が大事なんです。▼オススメなのが、友達で介護の先輩をみつけておくこと。 上大岡さん自身も困ったことがあると、すぐに相談されているそう。介護する年代になると、お互い見栄もなくなり、情報共有しやすいそうです。『待っていても情報はやってこない!まずは「地域包括支援センター」に行こう!』 介護に関する情報は、時期がきても政府や自治体が教えてくれるわけではありません。介護保険はもちろん、地域の情報は自分でとりにいかないといけないんです。これを知らないと本当に大変です。もちろん、制度を細かく理解するのは難しいので、さきほど言ったように、友達で介護の先輩をみつけておくこと。 ▼そして最初に一番頼りになるのが「地域包括支援センター」なんです。介護認定されなくてもカルテを作ってくれたり、地域にもよりますが、なんでも教えてくれるそうです。
ちなみに、介護未満でも大丈夫。介護はジワジワはじまるだけでなく、いきなり始まる場合もあります。昨日まで元気だとあしたもあさっても元気なわけではありません。▼それでもボンヤリした認識の方は「75歳」を区切りに考えてみて下さい。 健康状態に限らず、介護の区切りは75歳。この年齢が近づいてきたら、遠距離・近距離に限らず、コミュニケーションをとって親の状態を把握しましょう。定期的に電話したり、用事がなくても帰れるときは帰る(顔を見に行く)って、些細な変化をチェックしましょう。Q:ちなみに、親の資産、どのぐらいあるか把握しておきたいけど、どうやって切り出せばいいですか?▼確かに、親子でお金の話をすることになれていない方のほうが多いのでは。親のタイプにもよりますが、いきなり本丸ではなく、「友達のお母さんが救急搬送されたけど、お金がおろせなくて困ったんだって」など実例をまじえて危機感をもってもらいましょう。▼またそんな資産がわかっても、預金は基本的には本人しか引き出せません。 もしもの時に備えて、「代理人キャッシュカード(家族カード)」を作ることをオススメします。

監修は、ファイナンシャルプランナーの黒田尚子さん。主婦の友社から税込み 1,485円で販売中で、電子書籍でも読めます。
編集部おすすめ
トピックス
ニュースランキング
-
1

がん公表「GTO」生徒役女優、芸能界引退を発表「自分らしく自由に新しく」【全文】
-
2

上戸彩「最初の1ページ目は衝撃的な写真」15年ぶり写真集
-
3
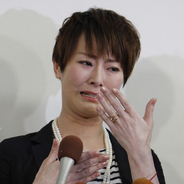
遠野なぎこさんは広末涼子より“取り扱い注意”な女優だった…事務所もお手上げだった(城下尊之/芸能ジャーナリスト)
-
4

小島瑠璃子、夫・北村功太さんの訃報を報告「突然の別れを受け入れられません」
-
5

「モヤさま」第5代目アシスタントは新人・齊藤陽アナ 田中瞳アナ「三村さん大竹さんに盛大にツッコまれる光景目に浮かぶ」
-
6

綾野剛、主演映画『でっちあげ』“真実を疑う物語”に圧倒的なリアリティをもたらす演技の深み
-
7

今夏で芸能界引退の道重さゆみ、ファンに囲まれた笑顔のリリイベSHOTに反響「幸せな空間」「衣装かわいいっ」
-
8

板野友美、ブランド経営者としての悩みを告白「子供いるっていうのもあるけど…」
-
9

「怖い」広末涼子が釈放直後に車内で見せた“急変ぶり”にネット騒然…送迎組の“風貌”にもツッコミ
-
10

山口達也さんのイケメン長男がLDH所属へ!
-
11

東野幸治、挑戦的な選挙特番で「大激論」へ 「選挙に行くきっかけにしてほしい」
-
12

「それはあなた個人の感想でしょう」と言われたときの正しい対処法は? 世界は「真偽・善悪」の二元論では説明がつかないことだらけ
-
13

ムキムキのイケメンTBSアナ・齋藤慎太郎が結婚「仕事に(+トレーニングに)邁進いたします」
-
14

大沢たかお、ドーナツ頬張る姿に“王騎将軍”の余韻漂う 地上波放送と重なりコメント欄が大盛況
Amazonおすすめランキング PR
更新:2024-09-10 14:44
-
 【Amazon.co.jp限定】HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 (完全生産限定盤) (Blu-ray) (オリジナルA4クリアファイル(Type.B)付)19,800円
【Amazon.co.jp限定】HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 (完全生産限定盤) (Blu-ray) (オリジナルA4クリアファイル(Type.B)付)19,800円 -
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg) 【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]16,500円
【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]16,500円 -
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg) 【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]11,000円
【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]11,000円
更新:2024-09-10 14:44
更新:2024-09-10 14:44
更新:2024-09-10 14:44
お買いものリンク PR















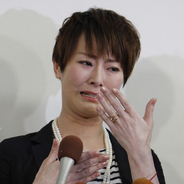














![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


